カスタマー・ハラスメント(カスハラ)対策は、自社の成長戦略を再考する好機となる。行き過ぎた顧客の要求や言動はSNSと匿名性の時代に過熱し、企業経営を揺さぶる。ならば事業主は「働く場、従業員を守る。毅然とした態度で、サービス提供を断ることもある」と意思表示を明確にし、自社の顧客対象を再点検するときだ。
今年4月、全国で初となるカスハラ防止条例が東京都などで施行された。6月にはカスハラ対策を企業に義務付ける改正労働施策総合推進法が国会で可決、成立。企業は「対応方針の明確化」「相談体制の整備」「加害者への対応」などの対策により、カスハラから従業員を守らなければならない。
対策の背景には深刻化する人手不足への対応がある。厚労省の調べでは24年度の労災認定件数は初めて1000件を突破し、その原因のトップ3位にカスハラが入った。個人の離職・退職のリスクはもちろん、現場の士気や戦力低下といった悪循環の始まりを暗示する。組織が根本対策に向き合わなければ、最前線の人材が疲弊する構図は変わらない。顧客と従業員、失うのはどちらが先か。事業主は、対策を先送りするリスクを早急に認めなければならない。
住宅・不動産業界の対策も進む。ある不動産仲介大手は、自社のホームページでカスハラの定義とそれに該当する行為例を示し、サービス提供を断る可能性について言及する。顧客に対して許容範囲を明示化することは、事業主の経営姿勢の約束でもあり、従業員の肉体的・精神的な安全に寄与する点でも意義深い。業界団体もまた、消費者への相談業務に関する対応姿勢や、会員企業の対策を促す指針案の整備を進めている。
自社のターゲット層を改めて捉え直し、明確に意識することで投資すべき戦力の「選択と集中」ができる。事業の優先順位を整理する先に、新サービスのヒントや戦略の芽が眠っているかもしれない。将来顧客の獲得を見据えた戦略の構想や準備期間と捉え、むしろ積極的に向き合うべきだ。今後は打ち出した指針・対策の運用を図りながら、顧客との関係性や従業員の働き方の変化を測定し、磨いていくことが肝要だろう。
一方、企業の対応姿勢に現場も呼応しなければならない。細心の注意を払ってもミスは起こりうると肝に銘じ、顧客からくみ取る力を高め、聞くべき指摘に耳を傾ける謙虚さが必要だ。まともな抗議を見抜けない鈍感さや顧客の声を軽視する態度は致命的であり、優良客も離れていく。
事業主は一連の対策を通じて、顧客と現場社員という両輪を回す役目を負う。ただ、それは社員育成や新たな顧客を獲得する好機となる点を強調したい。負担感の大きさばかりに気を取られ、消極的に振る舞えば形式のみ出来上がるだろうが、真に迫れば達成による成果は確実なものとなる。結局、その熱意が問われている。


















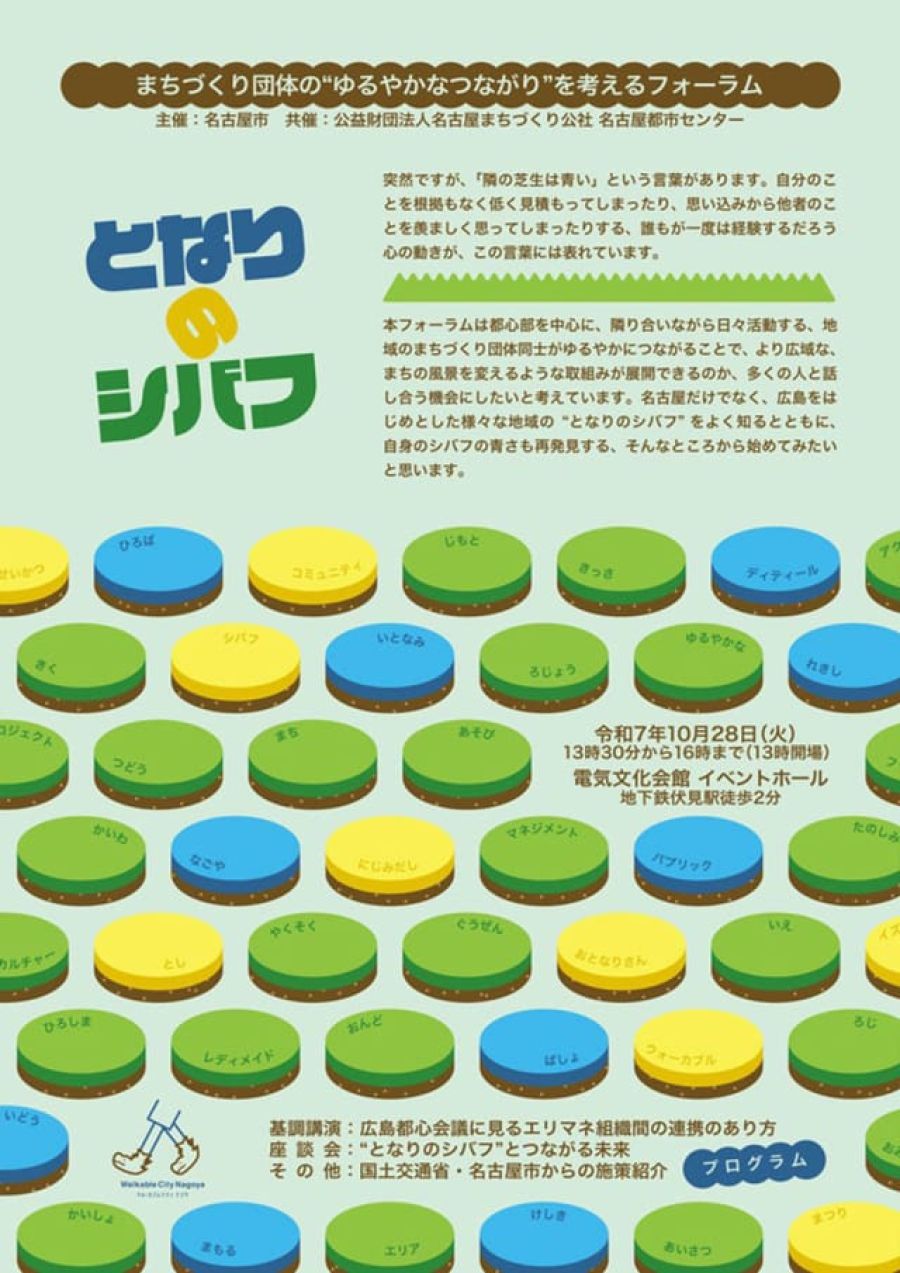
.jpg)
.jpg)

