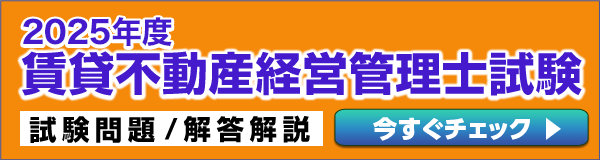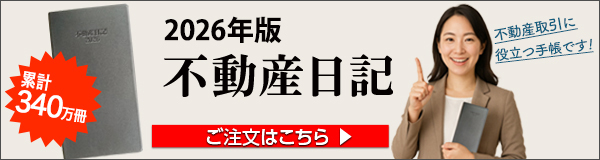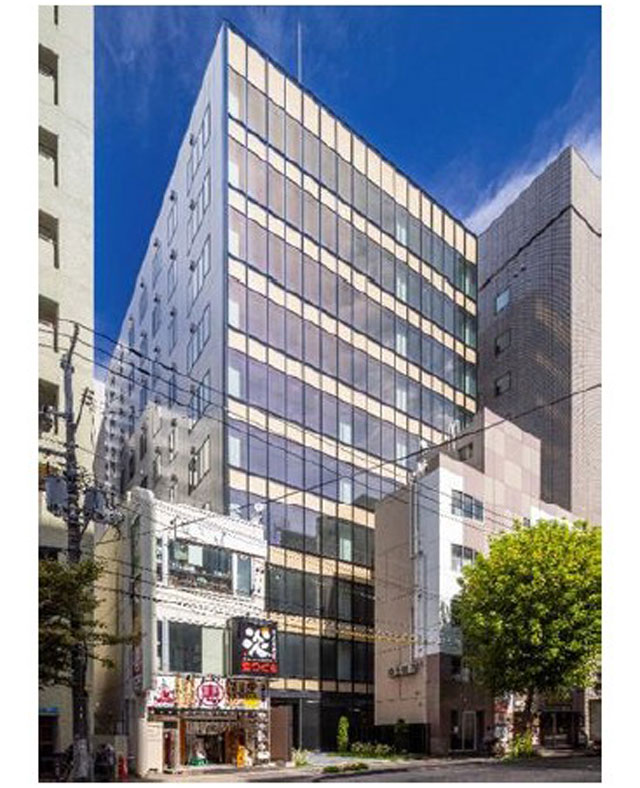残したい情景~文化的歴史的所産を巡る~日本不動産研究所 記事一覧
-
残したい情景~文化的歴史的所産を巡る~ 第30回 宮崎県日南市 一般財団法人 日本不動産研究所 にぎわい取り戻した「油津商店街」 人が集まる再生の好循環
16(平成28)年11月1日、「第10回まち・ひと・しごと創生会議」の安倍総理による冒頭挨拶で、空き店舗等有効活用やまちの再生を図ることについて、以下の事例紹介があった。 「宮崎県日南市油津(あぶらつ)商店(続く) -
残したい情景~文化的歴史的所産を巡る~ 第29回 鹿児島県日置市 一般財団法人 日本不動産研究所 関ケ原の撤退忍ぶ「妙円寺詣り」 畏敬の念と精神を受け継ぐ
「島津に暗君なし」と言われるが、幕末の島津斉彬公と並んで特に有名な君主は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した島津義弘公であろう。義弘公は、関ヶ原の戦いに西軍の一員として寡兵にて参陣し、東軍の勝(続く) -
残したい情景~文化的歴史的所産を巡る~ 第28回 沖縄県沖縄市 一般財団法人 日本不動産研究所 異文化チャンプルーなコザ 色褪せていく基地の街
沖縄県にかつて存在した、カタカナ表記の唯一の市「コザ」。市町村合併でコザ市は消滅したが、沖縄市中心エリアは今でもコザと呼ばれ、その呼び名は沖縄県民の間で広く定着している。 「キャンプ・コザ」 (続く) -
残したい情景~文化的歴史的所産を巡る~ 第27回 北海道札幌市 一般財団法人 日本不動産研究所 空洞化を経て再び人口回帰 札幌に彩を添える工場群
北海道がまだ蝦夷地と呼ばれていた幕末期、ロシアの南進政策に警戒を強めていた幕府は、現在の札幌市東区周辺を食料供給地として開拓することを決めました。二宮尊徳の門下生としても知られ、後に「開拓の祖」と称(続く) -
残したい情景~文化的歴史的所産を巡る~ 第26回 宮城県仙台市 一般財団法人 日本不動産研究所 仙台の象徴、ペデストリアンデッキ 活気あふれる駅前の空中広場
――夜の仙台駅前。大型ビジョンを望むペデストリアンデッキでは、日本人初の世界ヘビー級王座を賭けたタイトルマッチに人々が沸いていた。訳あって街頭アンケートに立つ会社員・佐藤(三浦春馬)の耳に、ふとギターの(続く) -
残したい情景~文化的歴史的所産を巡る~ 第25回 青森県青森市 一般財団法人 日本不動産研究所 進むコンパクトシティ化 夜店通りも再び街の顔に
青森市は青森県のほぼ中央に位置する県庁所在地で、人口約28万人の都市である。重要港湾である青森港からは青函連絡船が就航し、北海道と結ぶ本州の玄関口として長らく栄えたが、88(昭和63)年の青函トンネル開通に(続く) -
残したい情景~文化的歴史的所産を巡る~ 第24回 岩手県盛岡市 一般財団法人 日本不動産研究所 誉れ高い「南部駒」の供給地 岩手が誇る馬事文化の継承を
みちのくの初夏の風物詩「チャグチャグ馬コ」が、岩手県盛岡市で毎年6月に開催される。 「チャグチャグ馬コ」とは、華麗な装束をまとった100頭近くの馬が、隣接する滝沢市の鬼越蒼前神社から盛岡市中心部に位置(続く) -
残したい情景~文化的歴史的所産を巡る~ 第23回 秋田県山本郡藤里町 一般財団法人 日本不動産研究所 鉄道も国道もない町の宿泊体験 大自然の四季をあるがまま
世界自然遺産である白神山地の麓にある藤里町は、秋田県の内陸北部に位置し、行政区域の大半は山林が占め、自然豊かな町である一方、町内に鉄道はなく、国道もない。 藤里町の人口は、75(昭和50)年の国勢調査で(続く) -
残したい情景~文化的歴史的所産を巡る~ 第22回 山形県大蔵村・飯豊町 一般財団法人 日本不動産研究所 「日本で最も美しい村」宣言 市場価値で測れない原風景
農業王国山形は米の生産量全国4位である(農林水産省「平成30年産水陸稲の収穫量」)。県内の稲作地帯では広大な庄内平野が有名だが、平地は限られるため、山間部の傾斜地に先人が苦労して開墾したであろう棚田もみ(続く) -
残したい情景~文化的歴史的所産を巡る~ 第21回 福島県白河市 一般財団法人 日本不動産研究所 異世界への入り口に思いを馳せる 詠み継がれてきた幻の古関
夏の甲子園、東北勢は8強に2校が入る活躍を見せたが上位校の壁は厚く、準々決勝で姿を消した。東北の人々は皆「今年も甲子園優勝旗は白河の関を越えられなかったか」と肩を落とした。 東北勢は甲子園で優勝した(続く) -
残したい情景~文化的歴史的所産を巡る~ 第20回 東京都中央区 一般財団法人 日本不動産研究所 江戸の風情が残る月島・佃界隈 レトロ・モダン継承の策を
「下町」とは、都市の市街地のうち低地にある地区、あるいは主に商工業者などが多く住んでいる町と定義される。東京では浅草や神田、佃、月島などがあげられるだろう。商・住・工混在の庶民の町並みは、あらゆる歴(続く) -
残したい情景~文化的歴史的所産を巡る~ 第19回 埼玉県上尾市 一般財団法人 日本不動産研究所 清酒出荷全国5位の酒どころ 老若男女の集う蔵まつり
JR上尾駅東口の駅前商業地域を抜け、旧中山道(国道17号線)を街道沿いに北東に進むと、飲食店や共同住宅等が建ち並ぶ中に一際目を引くモダンな建物が見える。埼玉発祥の有名な日本酒銘柄の一つ「文楽」を製造する「(続く) -
残したい情景~文化的歴史的所産を巡る~ 第18回 茨城県水戸市 一般財団法人 日本不動産研究所 下町を流れる備前堀 風情漂う歴史ロードへ一体整備
水戸市は人口約27万人を有する茨城県の県庁所在地で、現在の中心市街地はJR水戸駅北側の台地状のエリアに形成されている。江戸時代の頃、水戸城は那珂川とその支流の桜川によって浸食された舌状台地の先端に位置し(続く) -
残したい情景~文化的歴史的所産を巡る~ 第17回 栃木県宇都宮市 一般財団法人 日本不動産研究所 空き店舗への出店に補助金 個性ある商店街に再生
「ユニオン通り商店街」は、JR「宇都宮」駅の西方約2キロに位置し、東西約400メートルの直線型の商店街である。昭和27年に結成された商店街であり歴史は古く、東武宇都宮線「宇都宮」駅(東武百貨店)を介して、宇都(続く) -
残したい情景~文化的歴史的所産を巡る~ 第16回 群馬県前橋市 一般財団法人 日本不動産研究所 「生糸の市」伝える広瀬川河畔 活性化へ景観を保全、活用
前橋市の中心市街地を流れる広瀬川は柳と桜の名所として知られており、河畔には散策路や緑地、あずま屋等が整備され、市民の憩いの場となっている。 弁天通りから広瀬川を下流方向に少し進むと、川の水が斜面を(続く) -
残したい情景~文化的歴史的所産を巡る~ 第15回 新潟県新潟市 一般財団法人 日本不動産研究所 無地番地に続く人情横丁 埋め立てで消えた柳都
オフィス街から近い場所にひときわ目を引く商店街がある。ユニークな小規模店舗が建ち並ぶ「人情横丁(正式名称=本町中央市場商店街)」は、新潟市で最も古い商店街の一つであり、1951年(昭和26年)に新潟市中央区に(続く) -
残したい情景~文化的歴史的所産を巡る~ 第14回 山梨県笛吹市 一般財団法人 日本不動産研究所 進む過疎化、失われゆく原風景 山村集落を守る地方創生を
甲府盆地と富士山の間に横たわる御坂山系の中間部分、富士川の支流芦川の上流にある山里旧芦川村(笛吹市芦川町)、その最上流に上芦川集落がある。谷間を東から西に流れる芦川の北側の斜面に沿って約1キロに渡り形(続く) -
残したい情景~文化的歴史的所産を巡る~ 第13回 長野県須坂市 一般財団法人 日本不動産研究所 〝蔵の町〟整備に市が補助 製糸で栄えた町並みを後世に
長野駅から長野電鉄で約30分、長野盆地東部の千曲川を挟んだ長野市の対岸にリンゴやブドウ等の果樹と機械・電子機器等の工業を中心とした農工業都市、須坂市がある。 現在は、長野市のベッドタウンとしても発展(続く) -
残したい情景~文化的歴史的所産を巡る~ 第12回 長野県伊那盆地 一般財団法人 日本不動産研究所 日常に根付いた昆虫食 地勢が育む独自の文化的所産
「信濃国は十州に 境連ぬる国にして 聳(そび)ゆる山はいや高く 流るる川はいや遠し 松本伊那佐久善光寺 四つの平は肥沃の地 海こそなけれ物さわに 万(よろ)ず足らわぬ事ぞなき」 制定50周年を迎えた県(続く) -
残したい情景~文化的歴史的所産を巡る~ 第11回 千葉市花見川区 一般財団法人 日本不動産研究所 輝ける旧検見川無線送信所 国際放送の先駆けの舞台
土地区画整理事業が進む閑静な住宅地にいかにも堅牢で、しかし、どことなく凝った設計の建物がポツンと立っている。場所は、千葉市の花「オオガハス」が発掘された花見川区検見川町、建物はコールサインJ1AAで名高(続く)