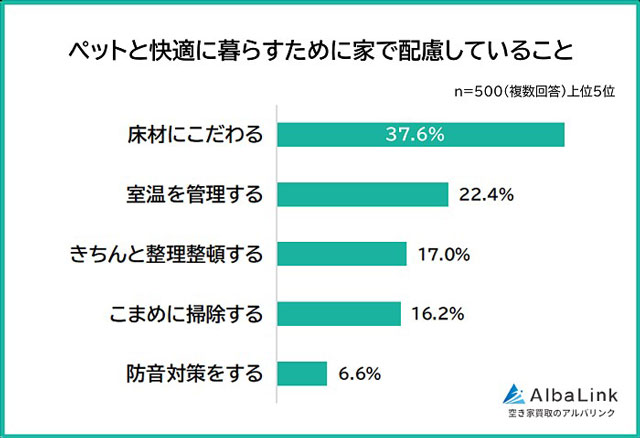令和時代の賃貸ビジネス ~コンサルタント沖野元の視点~ 記事一覧
-
「令和時代の賃貸ビジネス」 ~コンサルタント沖野元の視点~ 第66回 個々人が何者かを問われる時代になる
先日、筆者が所属する(一財)日本不動産コミュニティー(J―REC)の毎年恒例のキックオフミーティングが東京駅前の会場で行われ参加してきた。J―RECは「全ての人に不動産の知識を」という理念のもとに不動産実務検定と(続く) -
「令和時代の賃貸ビジネス」 ~コンサルタント沖野元の視点~ 第65回 専門性を磨く 公認不動産コンサルマスター資格
前回は不動産業従事者にとって必須の資格として宅地建物取引士と賃貸不動産経営管理士をあげた。今回はこの2つの資格を取得した上でさらに専門性を高めるためにどのような資格が良いかを考察してみたい。 (続く) -
「令和時代の賃貸ビジネス」 ~コンサルタント沖野元の視点~ 第64回 必須の資格としての宅建士と賃管士
昨今の多死社会による空き家の増加や大相続時代への突入といった社会情勢の変化により不動産業はますます専門知識が求められるものとなってきている。専門知識を対外的に示す最も分かりやすいものは資格である。筆(続く) -
「令和時代の賃貸ビジネス」 ~コンサルタント沖野元の視点~ 第63回 より良い写真につながるホームステージング
前回は一般社団法人日本ホームステージング協会主催のフォーラムで報告された白書で、不動産仲介ではすべての物件にホームステージングを実施するのが最多になったことや自社でのホームステージングが増えているこ(続く) -
「令和時代の賃貸ビジネス」 ~コンサルタント沖野元の視点~ 第62回 自社でホームステージャーを育てるメリット
今月11日に東京国際フォーラムで開催された一般社団法人日本ホームステージング協会主催の「ホームステージングフォーラム2024」に行ってきた。熱気に包まれた会場で国内におけるホームステージングの機運の高まり(続く) -
「令和時代の賃貸ビジネス」~コンサルタント沖野元の視点~ 第61回 社宅代行、分譲賃貸の留意点とは
本稿では2回にわたって東京都下のファミリータイプ分譲賃貸を商品化して客付けするまでの流れを書いてきた。この物件に申し込みしたのは米国在住の大手法人にお勤めの方で、本社勤務になり帰国するため家を探して(続く) -
「令和時代の賃貸ビジネス」 ~コンサルタント沖野元の視点~ 第60回 大手法人契約でも「再契約型」定借を容認した事例
前回、弊社で管理を受託したファミリータイプの区分を賃貸に出すまでに商品化していく流れについて書いた。今回は商品化した物件に客付けしていく中で得られたものについて共有したい。 都内の郊外に位置する(続く) -
「令和時代の賃貸ビジネス」 ~コンサルタント沖野元の視点~ 第59回 自宅賃貸で見落としがちなビジネス視点
最近、弊社で管理を受託したファミリータイプの区分を賃貸に出して直に客付けした。この物件を成約するまでの一連の流れを振り返りながら、取引の各段階において得たものを共有したい。 当該物件は現在の所有(続く) -
「令和時代の賃貸ビジネス」~コンサルタント沖野元の視点~ 第58回 シアトル滞在記(4) ITツールの根底にあるフィロソフィー
米国シアトルのエージェント宅にホームステイした話の続きである。私のホストだったタンさんの営業を身近で見た米国不動産エージェントの営業をサポートしているITツールとそれを日本が容易に真似できない理由につ(続く) -
「令和時代の賃貸ビジネス」~コンサルタント沖野元の視点~ 第57回 シアトル滞在記(3) 本場のホームインスペクションを見学
引き続き7月に滞在した米国シアトルでの経験を共有したい。シアトルの不動産エージェント宅にホームステイして米国不動産の仕組みや不動産エージェントの働き方を学ぶというものである。筆者をホストとして受け入(続く) -
「令和時代の賃貸ビジネス」 ~コンサルタント沖野元の視点~ 第56回 シアトル滞在記(2) 独自の集客戦略とホームステージング
前回に続き米国シアトルでの経験を共有したい。 筆者が滞在したのはシアトルのトップ1%エージェントであるタンさんのお宅である。タンさんは3人家族で奥様と中学生の男のお子さんがいる。滞在中タンさんご家(続く) -
「令和時代の賃貸ビジネス」 ~コンサルタント沖野元の視点~ 第55回 シアトル滞在記(1) 米国エージェントとブローカーの関係
7月中旬に1週間ほど米国シアトルに滞在してきた。 これは私が事務局をお手伝いしている一般社団法人日米不動産協力機構(JARECO)のシアトルホームステイプログラムに参加したものである。このプログラムは米国(続く) -
「令和時代の賃貸ビジネス」 ~コンサルタント沖野元の視点~ 第54回 空き家に関する媒介報酬見直しとコンサル業務促進
前回に引き続き、国土交通省が策定した「不動産業による空き家対策推進プログラム」(以下当プログラム)の内容について考察していきたい。 当プログラムは大きく2つの内容に分けられている。1つは「流通に適し(続く) -
「令和時代の賃貸ビジネス」~コンサルタント沖野元の視点~ 第53回 空き家の現場に宅建業者がいない理由
6月21日、国土交通省は「不動産業による空き家対策推進プログラム」(以下当プログラム)を策定した。今回はこの内容を踏まえて考察したい。 今年4月、総務省による「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集(続く) -
「令和時代の賃貸ビジネス」 ~コンサルタント沖野元の視点~ 第52回 定期借家物件の割合と競争力の関係とは
前回に引き続きアットホームによる「定期借家物件の募集家賃動向(2023年)」の内容について考察していきたい。 ◇ ◇ ◇ まず賃貸アパマンに占める定期借家物件の割合を見てみると、賃貸マンショ(続く) -
「令和時代の賃貸ビジネス」~コンサルタント沖野元の視点~ 第51回 建物構造とエリアで差が出た定期借家募集家賃
今年もアットホームによる「定期借家物件の募集家賃動向(2023年度)」がリリースされたため、この内容について考察していきたい。 ◎ ◎ ◎ 今回は特に東京都内のマンションとアパートにおける(続く) -
「令和時代の賃貸ビジネス」 ~コンサルタント沖野元の視点~ 第50回 家賃値上げの適切なタイミングとは
前回は家賃値上がりの実態とその要因について書いた。今回はもし値上げするとしたらどのタイミングで行うのが適切かについて考察してみたい。 ◎ ◎ ◎ まず家賃値上げを行うには借主側にその土(続く) -
「令和時代の賃貸ビジネス」 ~コンサルタント沖野元の視点~ 第49回 家賃値上がりの実態と その要因
4月10日の日経新聞朝刊に「物価高、家賃も動かす」というタイトルの記事が掲載された。記事では消費者物価指数で賃貸住宅の家賃を示す指数が上がっていることや大手管理会社が契約更新時に家賃の値上げを打診して(続く) -
「令和時代の賃貸ビジネス」 ~コンサルタント沖野元の視点~ 第48回 電子契約は業務効率アップに貢献 特に定期借家契約
前回に引き続き電子契約についてである。 まずは電子契約に先駆けて解禁となっていたIT重説について確認しておきたい。「IT重説」は2年間の社会実験を経て平成29(2017)年10月から本格運用が始まった。流れと(続く) -
「令和時代の賃貸ビジネス」 ~コンサルタント沖野元の視点~ 第47回 不動産の電子契約 お客様の要望が後押し
デジタル改革関連法が施行されてもうすぐ2年を迎えようとしている。その一環として宅建業法も改正され重要事項説明書など宅建業者が交付すべき書類に押印が不要となり、これによって電子契約が可能となった。遅れ(続く)