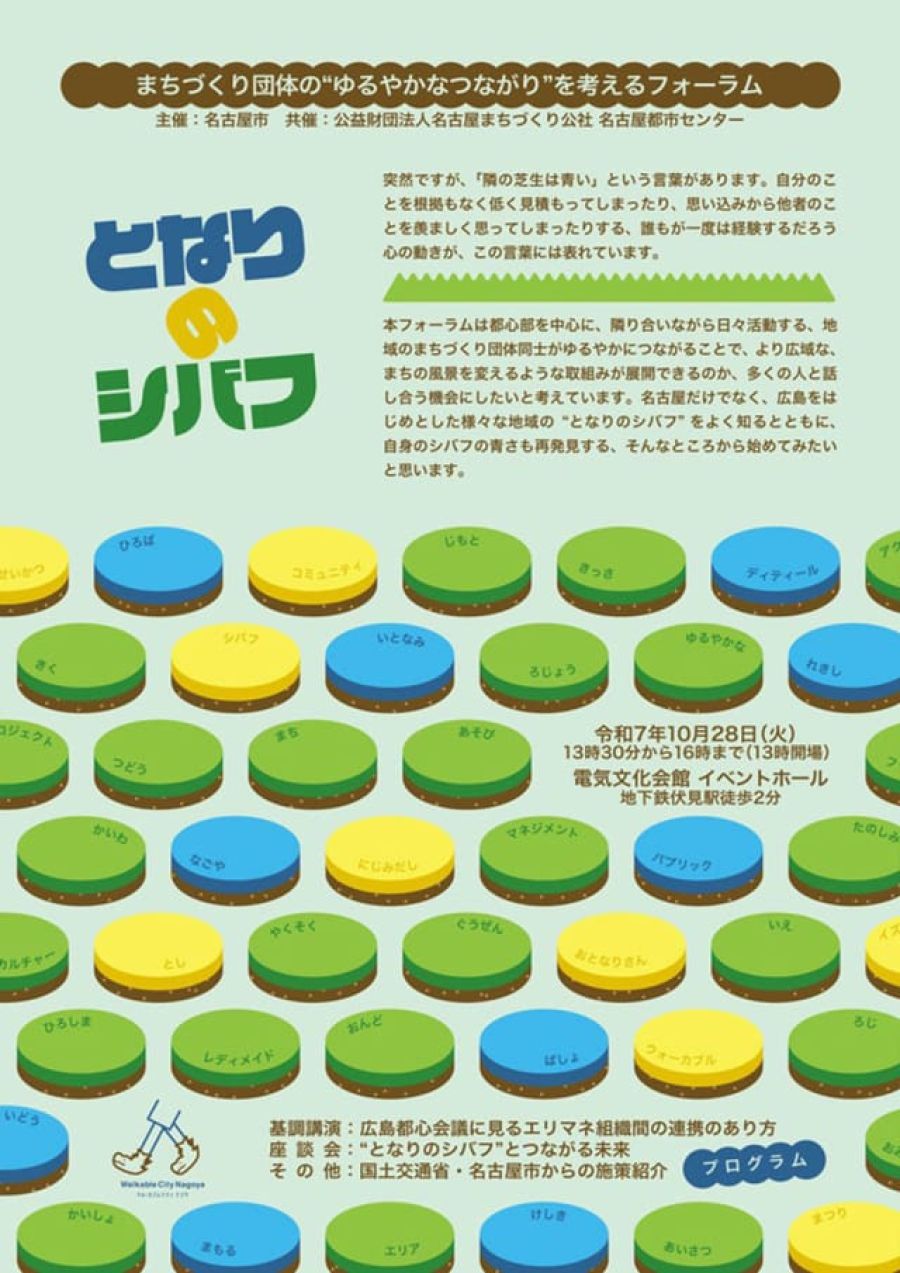被害総額10兆円、全壊した住宅約10万棟、6434人の尊い犠牲。阪神・淡路エリアに甚大な被害をもたらした大地震の発生から20年が経過した。
時間の経過と共に復旧・復興は進み、街にはもう深い〝傷痕〟はない状況だ。ただ、時計の針があの時のままという被害関係者は多数いる。改めて、被害に遭われたすべての方々へ深い哀悼の意を表したい。
犠牲者の多くは、木造家屋の倒壊による圧死だった。特に老朽化した住宅でその被害が目立った。1981年6月の新耐震基準は過去の地震の経験を踏まえて制定されたもので、その基準に適合していたか否かが明暗を左右したといえる。
安心・安全の取り組み
そして震災後、耐震強度を更に上げる観点から、2000年には、「地盤調査の事実上の義務化」「接合止め具などの規定」「耐力壁のバランス計算」などを内容とする法改正が行われた。そのほか、耐震診断の義務化や補修に対する補助など、「安心・安全の住宅建築物」への取り組みは進んだ。東日本大震災でも多大な犠牲が生じたが、津波や原発によるものがその大半だったため、そのことだけを捉えれば、阪神・淡路を教訓として20年間手掛けてきた建物に対する取り組みは、間違った方向ではなかったと言える。
日本人の「強み」
時代が進化するにつれ、希薄になりがちなのが「コミュニティ」。ただ、近年はその重要性が改めてクローズアップされている。思えば、阪神・淡路を始めとする様々な災害からの立ち直りを早めたのがコミュニティだ。
「まさかの時」にそれが発揮される日本人の特質。関東大震災での炊き出しの際、しっかりと列を作り順番を待っている被災者の姿を写した写真が残されている。これは、阪神・淡路や東日本大震災でも見られたことで、その光景を目の当たりにした外国人の多くは、窮地に陥っても礼節を守る日本人の姿に驚愕したと聞く。
「和」を尊ぶ日本人ならではのコミュニティ。時代の変化や流れを問わず強まるコミュニティ形成への機運は、「まさかの時」に威力を発揮する。それは、何物にも代えがたい「強み」になることだろう。
あれから20年。時間は刻々と流れていく。国や行政の取り組みなど、大きな流れを眺めるだけではいけない。個々人がしっかりと「あの時」を胸に刻み、偲び、そして日々の生活に少しでもフィードバックさせていくことが必要だ。
風化させることだけは絶対にしてはいけない。それが、今を生きる我々の責務である。