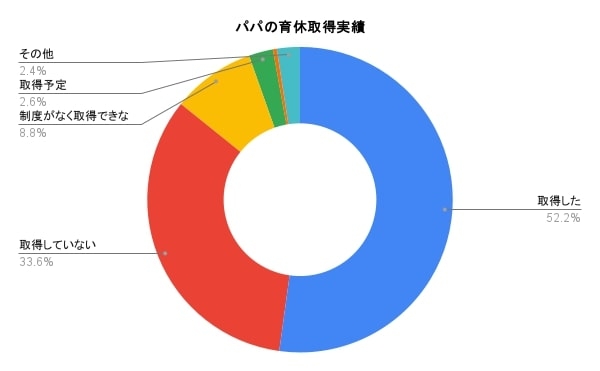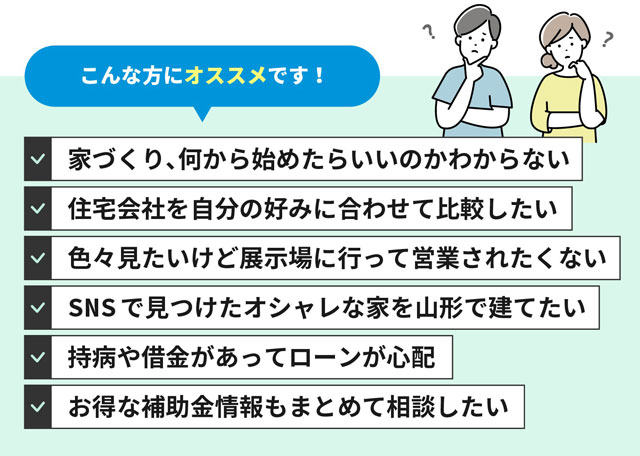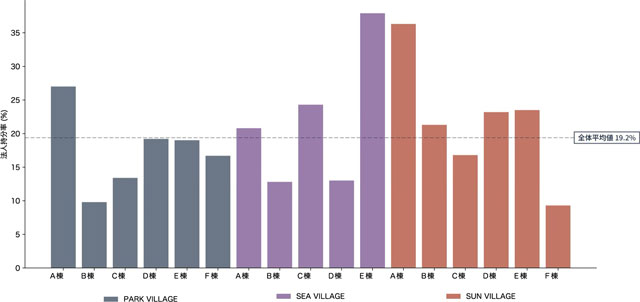日本の住まいは戦後、広さと、プライバシーと、セキュリティを追求し、最も重要なコミュニティを置き忘れてきた。その反省が今、始まっている。
数で表せる価値は相対的
これまで、いい住まいとは何かと問われれば、広い面積、耐震性、最新の設備、優れたデザイン、駅から近く立地に恵まれていることなどが挙げられてきた。しかし所詮それらはいずれもワン・オブ・ゼムでしかない。あるいは単に数量で表せるものが多かった。数で表せる価値は相対的でしかない。
人は社会の一員としてしか生きていけず、住まいは生活の基盤であることを考えれば、いいコミュニティが形成されていることは、住まいにとってワンランク上の重要な価値と言えないだろうか。従って「住宅」がコミュニティ性を備えていないとしたら、そんな窮屈な場所はないのである。
「いやいや、近所付き合いほど煩わしいものはない」という意見も耳にする。しかし、それは「家が生活の基盤」になっていない人の見方ではないだろうか。家が「寝に帰る」だけの所になっていないか。
戦後、都会では多くの勤労者人がそういう生活を送ってきた。まさにそのことへの反省が始まっている。なぜなら、多くの人が地元や地域を省みてこなかった結果、子供の生きる力が奪われ、若者は他者への関心を失い、大人は疲弊していく地域をただ漫然と見過ごすのみ。そして国は活力を失い続けている。
供給側で仕掛けづくり
最近、賃貸住宅や分譲マンションでは住民同士のコミュニティが形成されやすいようにとの仕掛けづくりが盛んだ。中庭を設けたり、各住戸に野菜作りが楽しめる畑を付けたりするのが人気を呼んでいる。戸建て分譲地でもディベロッパーが入居後のコミュニティを促進するため、様々な行事を企画する動きが広まっている。
集合住宅の魅力といえば、隣の住民のことは知らなくても鍵一つで安全な生活ができること、戸建て住宅でも隣近所とはあいさつを交わす程度で互いの生活には干渉しない方が快適な暮らしができると言われてきた。しかし、本当にそれでいいのだろうか。
戦後は家の中にすべての家電製品がそろい、情報機器も備えられるようになったから、家族単位の生活で何の不自由も感じることはなかった。それに引き換え、江戸時代の長屋では便所はもちろん、炊事も洗濯も共同の井戸端が使われていたから、コミュニティは生活を支える基盤そのものだった。もちろん、当時でも人との交流は煩わしかったはずだ。しかし、煩わしさの中にしか、人生は存在し得ないともいえる。戦後の急激な物質的成長の陰で、我々はそのことを忘れていたのではないか。
集合住宅でのコミュニティを確保する伝統的手法の一つとしてコーポラティブ住宅がある。しかし、これまでの累計供給戸数は全国でも1万戸余りといわれ、住宅形式として定着したとは言い難い。
住民参加型の新たな意味
今後増加が見込まれる分譲マンションの建て替えも、見方を変えた住民参加型の住まいづくりだが、5分の4以上の合意という高いハードルがある。だが、コーポラティブでも建て替えでも、実現した建物では入居者同士の良好なコミュニティが長く継続しているという報告が寄せられている。
かつては世帯ごとに「建てる」ものだった住まいが、分譲マンションなどの登場により、多数の世帯が一斉に「買う」ものに変わった。その大変革のなかで、住まいにとって重要なコミュニティをどう編み出せばいいのか。やや研究が遅れたきらいはあるが、これからの業界が取り組むべき大きな課題である。