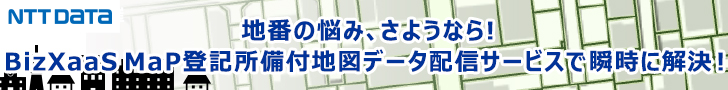「働き方改革」に注目が集まる中、不動産業界も社員の能力向上、人材育成に本格的な関心を向け始めた。AIや不動産テックなど不動産業界を取り巻く技術革新は目覚ましく、人口減少や超高齢社会など未来の不動産市場にも不透明感が増しているからだ。
埼玉県宅地建物取引業協会は1月末、地域密着の不動産事業者が街の活性化や10年後の不動産業界にどう関わっていくべきかを考えるイベント「不動産業者のためのタウンマネジメントスクール」を2日間にわたり実施。多くの不動産業経営者が参加した。
その中で同協会の内山俊夫会長は「今、我々不動産事業者は目先の取引や業務処理に追われがちで、10年後の業界を見据えて仕事をしていない」と警告を発し、不動産業界が今こそ長期的視野を持つことの重要性を訴えた。
一方、産業界全般で個人の働き方に変化が生まれている。単に賃金を得ることを目的とするのではなく、企業のミッションや目的に賛同して働くことを第一義とする若者層が増えている。不動産業界でも、今後はそういう意欲と能力を身につけた人材の発掘が欠かせなくなる。
一人ひとりが専門知識やスキルを持ち、それを生かしながら働くことができる職場を転々とする時代が来るのかもしれない。つまり〝組織〟に縛られるのではなく、〝個人〟が飛躍していく時代だ。
そのとき我が国の不動産業界はどう変わるべきなのか。よく比較されるが、米国のエージェントはそれぞれが顧客の立場に立つ独立したプレーヤーであり、優秀であるほど顧客が付いてくるため、年々収入も上がっていく。
一方、日本の営業マンは会社に所属するサラリーマンだから、どうしても会社と顧客の両方に顔を向けなければならない。それが米国のように顧客の信頼に支えられた職能になり難くしていて、離職率の高さにつながっているとの指摘もある。
約3年前、宅地建物取引主任者から宅地建物取引士へと名称が変更された。「士」となった意義を踏まえれば、米国のように「取引士」一人ひとりが研鑽を積むことでキャリア形成ができる業界構造へ変わっていくことが重要ではないか。そうなれば、就職を考える若い世代の目に、我が国の不動産業が魅力的に映ることになるのではないか。そして、現実にキャリア形成のモデルを示す必要がある。 例えば最近は仲介の仕事をしながら不動産コンサルティング能力を身につけさせたり、金融分野にも知識を広げ、富裕層の資産運用や管理を担える人材を求める企業も出始めている。
これからの不動産業はAIやIT技術の発展もあり、人間が行う業務は更に高度化するだろう。企業存続の鍵を握るのは社員のやる気と資質だが、10年後、20年後の業界の未来を担う人材をどう育てるのかは業界が真剣に考えなければならない問題である。