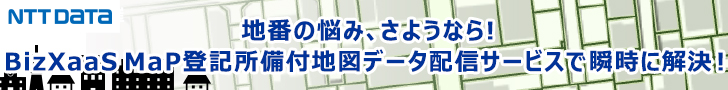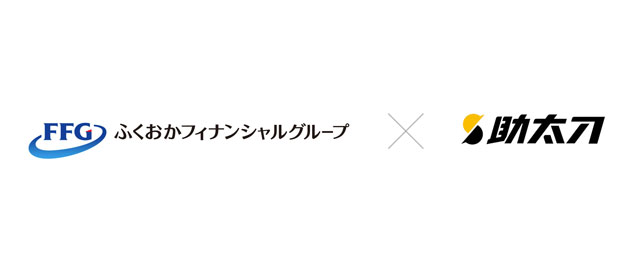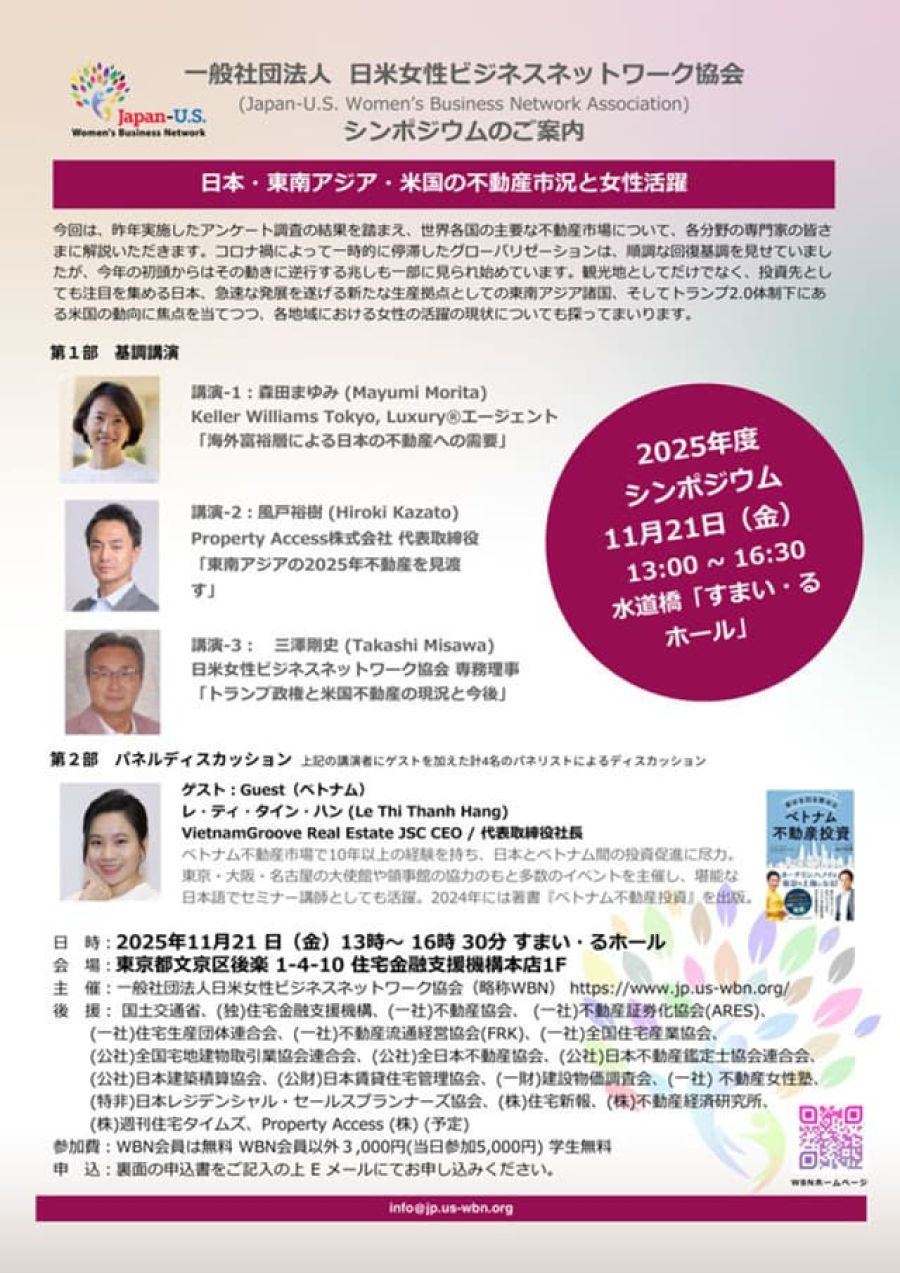コロナ禍の今、我々は時代の目撃者として何を見ているのだろうか。歴史の転換点にいても、それに気付くのは至難の業だとも言われる。首都圏新築マンションの平均価格はバブル期を超え過去最高値を更新中だ。それでも今は異常な低金利だからか、マンション市場は好調さを維持している。
所有権の15%オフ
本紙は昨年9月21日号の1面で、地代前払い方式・期間70年の定期借地権マンションが注目を集めていることについて大きく報道した。
土地を70年間貸すだけで土地価格の70~80%もの地代を一括受領でき、しかも課税は毎年均等課税という地主にとっては夢のような方式を使った定借マンションが大手ディベロッパーによって急増し始めたという内容である。マンションを購入するエンドユーザーにとっては、通常の土地所有権付きマンションに比べ約15%オフで購入できるというメリットがある。
平田明氏(EAJ信託社長)と本郷尚氏(税理士法人タクトコンサルティング税理士)の対談は、これほどのインパクトがある地代前払い方式なのに、世間(含む土地オーナー)ではまったく知られていないという危機感から開かれた。
平田氏は言う。「顧問先に土地オーナーを持つ専門家がこのスキームを知らないため、別の土地活用を提案し、後からオーナーになぜあの時、こういう方法があることを教えてくれなかったのかと責められる危険性がある」。この日、会場には駅前などの一等地に資産を持つ法人などを顧問先に抱える金融関係の専門家らが集まっていた。
地主が知らない
本郷氏もこう話す。「数年前から実践例が目立ち始めたが、まだまだほとんどのオーナーが知らない。当社のクライアントもこんな〝魔法の杖〟みたいな方法があるなんて誰も教えてくれなかったとビックリする」。
前払い方式が制度として定期借地権に加わったのは05年1月からだが、なぜかその後あまり活用されることがなかった。にわかに世間で注目を集めるキッカケになったのが、旧豊島区役所や旧渋谷区役所の建て替え事業である。前者は東京建物とサンケイビルが、後者は三井不動産が担当し、どちらもディベロッパーによって支払われた前払い地代で、新庁舎と付属施設が建設されている。
地代はどちらも土地価格の80%で、借地期間は70年プラスアルファ(工事期間など)となっている。
平田氏は言う。「自治体にとってこの資金調達スキームはPFI(プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)より簡単だし、70年後には再び繰り返すことができる」。
人材がいない
本郷氏は地代一括前払い方式が使われてこなかった要因についてこう語る。「惜しいことにこの方式の魅力を土地所有者にきちんと説明できる人材がいない。大手ディベロッパーには各社一人ぐらいはいるが、とても一人でやり切れるものではない。このプロジェクトは早くても着工までに4、5年はかかる」。
◇ ◇
定期借地権が92(平成4)年に創設された背景には、当時地価が高騰し庶民がマイホームを持てなくなっていた状況がある。しかし、皮肉なことに定期借地権が創設されると同時にバブルが崩壊し地価が下がり始め、日本経済は資産デフレという長いトンネルに突入する。そして30年後の今、再び首都圏マンションが高騰し、一部ではマンションに土地所有権は本当に必要なのかという疑問も出始めている。
当初は月払い地代で期間50年が主流だった定期借地権が、地代一括前払い・期間70年という新たな装いで登場し、再び世間の注目を集めようとしている。固定資産税が土地価格の1%なら、100年で購入価格に到達する。この事実を〝人生100年時代〟の今、時代の目撃者たる我々はどう受け止めればいいのだろうか。