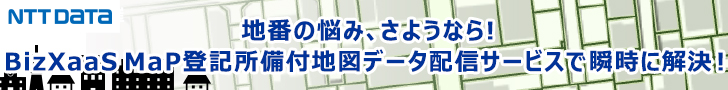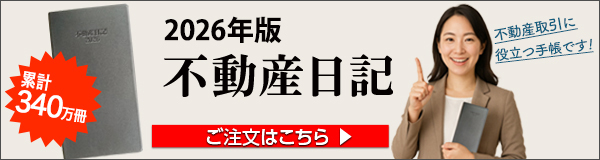【取材協力】
株式会社 JON 取締役営業本部長
眞木 仁(さなぎ じん)氏

株式会社 JON

行政情報を有効活用することの社会的気運が高まるなか、各種データベースの汎用型候補キーとなり得る「所在地番」および「住所」の全国レベルにおける調査体制を確立したほか、不動産登記にかかる高度かつクリーンな分析を可能とする「登記基本情報データベース」の開発に成功するなど、数々のユニークな実績を生み出している。
これらの成果が諸方面に導入されることで、不動産にかかる権利の明確化や取引の安全はもちろんのこと、社会生活における様々な利便や安心につながるものと確信し、さらに新たな事業・サービスの提供に努めている。
<第3回>「相続」に高まる期待
迅速に多くの対象者へ
「登記情報のビジネスにおける有効活用」を想定した際、不動産会社の頭に真っ先に浮かぶのが、「相続による登記」ではなかろうか。不動産登記情報コンサル会社のJON(東京・飯田橋)によると、東京23区内で13年に発生した相続件数は約6.3万件。神奈川県横浜市・川崎市・相模原市で約3.4万件、大阪府大阪市・堺市で約1.7万件に上る。年々増加傾向にある中、15年1月には相続税改正による基礎控除引き下げが控えているため、対象者の増加によりその数は更に拡大基調になることが予想されている。
売却依頼の獲得へ
相続発生の場合、不動産会社のビジネスチャンスは「当該物件の売却依頼」の獲得だ。「相続登記と同時に売り先が決まっている割合は、5%未満」(JON・眞木仁営業本部長)であるため、相続が発生したという登記情報を入手してからの営業案内でも十分間に合うと言える。ただ、相続物件を最終的に売買したケースを見てみると、その期間が1年未満の割合は35%に上り、2年未満までを含めると実に57%に上る(東京23区で過去14年に発生した相続手続きを抽出、JON調べ)。相続人に対していかに迅速に、有益な情報を提供するか。相続ビジネスを考える不動産会社にとっては、非常に重要な事柄となる。
より多くの相続人に情報提供できる有効手段として考えられるのが、ダイレクトメール(DM)の活用だ。登記情報コンサル会社から「相続発生」の登記情報を得て、相続人の「所有者住所」の確認などをした上で不動産会社はDMを発送する運びとなるが、その際に注目すべき事項は「相続物件が非居住かどうか」といったことだ。非居住の相続物件は、売りに出る可能性がより高くなるからだ。

非居住かどうかの推定は、相続発生の登記情報における住所(地番)と所有者住所の比較で行う。相続物件の所在①と、相続した所有者の住所②が合致していなければ「当該相続物件は非居住」である可能性が高いと判断される(表イメージ)。「お住まいになっていないのであれば、売却のお手伝いをします」といった案内がしやすい。
2次相続対策も
また、所有者事項の相続人が「配偶者」である場合、「配偶者に対する相続税の軽減特例」が使われたのではないかと考えるのも、今後のビジネス展開のきっかけになるかもしれない。この「配偶者特例」は、相続財産の価格が「法定相続分相当額」もしくは「1.6億円」のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税はかからないという制度だ。ただ、その配偶者が死亡して被相続人となり、次なる子どもへの相続となった場合に、トータルで考えると納付する税額が増えるケースもある。そのため、地位(じぐらい)の高いエリア、もしくは大きさのある不動産など評価額が高いと考えられる相続物件である場合ほど、将来を考えた「2次相続対策提案」が有効になる。
ほかの不動産会社が行わないような「一歩先を行く〝コンサル型〟」の提案も、他社との差別化を図る有効手段となる。