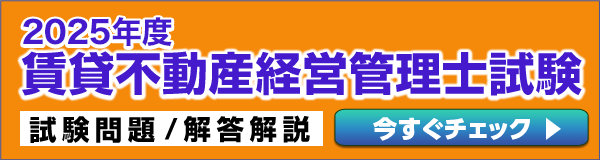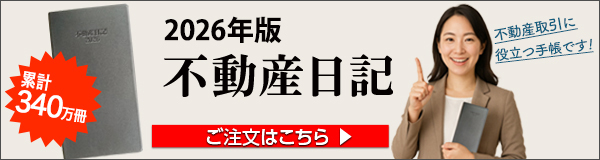新住まいの「ことわざ」 記事一覧
-
松岡英雄新住まいの「ことわざ」 <129> 大は小を兼ねるも長持ちは枕にならぬ
テレビを買い求めた。これまでの32型では字幕の文字が見づらくなったので、52型にしたらさすがに楽に読めるようになった。節電の時期だけに消費電力が気になるが、今のテレビは昔と比べれば電気をくわなくなっ(続く) -
大黒柱 松岡英雄新住まいの「ことわざ」 <128>
五重塔には中央部に心柱(しんばしら)と呼ばれる柱が使われ、耐震性に優れた建物になっているそうだ。東京スカイツリーにもこの心柱の役割を果たす鉄筋コンクリート製の円筒(中は階段室)があり、マグニチュード8(続く) -
縁の下の掃除番 松岡英雄新住まいの「ことわざ」 <127>
湘南新宿ラインは高崎から小田原まで走っている。小田原に向かう電車に熊谷駅から乗ってきたお嬢さんが「母性看護学各論」という表紙の医科大学か専門学校の教科書を熱心に読んでいた。今時の若い人は電車の中(続く) -
松岡英雄新住まいの「ことわざ」 <126> 糠(ぬか)に釘
政治生命をかけて消費増税に突き進んだ野田首相に国民の声は届かなかった。聞く耳を持っていなかった。どこかでマインドコントロールをされたのかもしれない。 結局、大飯原発が再稼働した。筋書き通りに(続く) -
松岡英雄新住まいの「ことわざ」 <125> 所変われば品変わる
大人になってこちらで暮らすようになるまで納豆を食べたことがなかった。存在すら知らなかった。 故郷・岐阜では納豆を食べる習慣がなかった。納豆と言えば、甘納豆だった。食料が豊富でなかった時代だか(続く) -
松岡英雄 新住まいの「ことわざ」 <124> 家貧しくして良妻を思う
貧乏すると、それを切り抜けるために良い妻が欲しいと思う。 実はこの言葉のあとに『国乱れては良相を思う』と続く。国が乱れると立派な宰相の出現が待ち望まれる。中国の戦国時代、政治家の李克(りこく)(続く) -
松岡英雄新住まいの「ことわざ」 <123> 地獄は壁一重
ゴルフはメンタルな部分が多いスポーツだそうだ。入ると思って打ったパットが入らなかったらイライラするに違いない。その苛立ちが次のプレーに影響するだろうことは、ゴルフをしない私にも容易に想像できる。(続く) -
松岡英雄新住まいの「ことわざ」 <122> 家貧しくして孝子あらわる
昔、近所に母子家庭の家があった。子供が5人いて、下の2人は私と年齢が近かったので一緒に遊んだりした。その2人は週に何回か、すぐ上の兄と夕方の駅前で靴磨きの仕事をしていた。そうやって苦しい家計を支えて(続く) -
松岡英雄 新住まいの「ことわざ」 <121> 店を畳む
電力が不足しそうだから今年の夏も節電をしてもらいたいと、電力会社も政府も言っている。言われなくても国民は節電をするつもりである。その覚悟である。 昼間の電気料金を高くすれば、電気を使わないだ(続く) -
松岡英雄新住まいの「ことわざ」(120) 妻子を置く所が故郷
その日は、7時頃に雨はあがったが、東の空は厚い雲に覆われていて、173年ぶりという金環日食を見ることができなかった。 次に関東で見られるのは300年後だそうだから、貴重なチャンスを逃したことになる(続く) -
松岡英雄新住まいの「ことわざ」 <119> 桂玉(けいぎょく)の地
銀座と名付けられた街はいくつあるのだろうか。 ネットで調べてみると、東京23区内には100ほどの○○銀座があるらしい。その代表は戸越銀座だろうか。 もちろん、銀座の本家本元は中央区銀座である。(続く) -
松岡英雄 新住まいの「ことわざ」(118) 壁の穴は壁で塞げ
社会保障と税の一体改革と言うけれど、消費税を増税すれば年金が拡充されるわけではない。消費税率を上げることは一時しのぎである。年金制度は、根本的な見直しをしない限り将来も安定した制度にはならない。(続く) -
松岡英雄新住まいの「ことわざ」 <117> 所を得る
中日ドラゴンズのセカンド、ショートは荒木、井端のコンビで鉄壁の2遊間だった。それが昨年入れ替わった。守備位置が変わることは野球において不思議ではないが、選手のためにコンバートすることが多い。体力が(続く) -
松岡英雄新住まいの「ことわざ」(116) 天と地
東京スカイツリーがいよいよ来週、5月22日オープンする。何かスカイツリーのことを書いておかないといけないような気がして、いざ書こうとしたが、書くことがない。 高さや構造について今更書いてもしか(続く) -
松岡英雄 新住まいの「ことわざ」 (115) 地震のときは竹藪に逃げろ
数年前、藤沢市の生コン業者が強度不足のコンクリートをかなりの長期間にわたって違法販売していた事件があり、工事中のいくつかのマンションが工事のやり直しをせざるを得なくなったことがあった。しかも、そ(続く) -
松岡英雄新住まいの「ことわざ」 (114) 昼行灯(ひるあんどん)
昼間ともしてある行灯のように、ぼんやりしている人、何の役にも立たない人のことをあざけっていう言葉である。 念のため、行灯とは、木などの框(わく)に紙を貼り、中に油皿を据えて灯火をともす道具で(続く) -
松岡英雄 新住まいの「ことわざ」(113) 下種(げす)の一寸のろまの三寸馬鹿の開け放し
電車の連結部分にあるドアを開けっ放しにして通り抜けていく人がいる。風が吹き抜けて座っている人に迷惑をかけることに気がつかない。戸障子は開けたら閉める、としつけられなかったに違いない。しつけられな(続く) -
松岡英雄新住まいの「ことわざ」(112) 風、破窓(はそう)を射て灯火(ともしび)滅し易し
今の電車は窓が開けられないものが多いが、昔の電車は窓を開けることができた。冷房の設備がない時代だったからそれが当たり前だった。窓から入る風は心地良かったが、時には悪戯をすることもあった。 あ(続く) -
松岡英雄新住まいの「ことわざ」(111) 釘付けになる
今上陛下の結婚式は59年4月10日、私は中学2年生だった。どういうわけか、あの日、テレビ中継を見たという記憶が全くない。思わぬ休日を、あるいは幸いとばかり、友人と遊んでいたのかもしれない。皇太子殿下の(続く) -
松岡英雄 新住まいの「ことわざ」(110) 桜伐る馬鹿、梅伐らぬ馬鹿
東京駅の八重洲北口からの日本橋・高島屋に向かって日本橋さくら通りと名づけられた通りがある。 20年ほど前、中学校の在京組の同窓会が日本橋で開かれた帰りにその通りを仲間と歩いたことがあった。56年に植樹(続く)