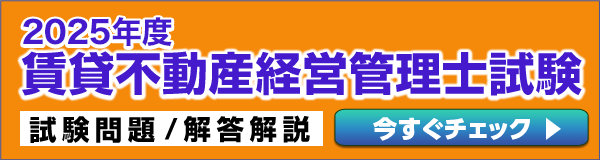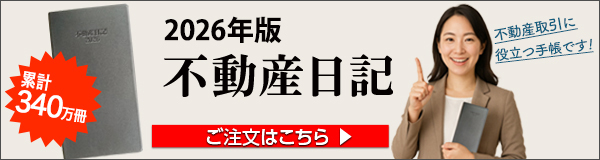新住まいの「ことわざ」 記事一覧
-
嫁は木尻から、婿は横座から貰え 松岡英雄新住まいの「ことわざ」 <190>
ウイークデーの午前中だというのに、たくさんの若い女性が集まって料理をしている。駅前のショッピングモールの中にある料理教室はいつも賑わっている。昔は、煮炊きは母親か祖母が教えたが、今の忙しい子供たちは(続く) -
新住まいの「ことわざ」<189> 一つ屋根の下に住む 松岡英雄
安倍さんは女性が働きやすい国にしたいという。それに応えるかのように、最近、同じ建物内に保育所を誘致したり、学童保育に配慮したマンションが出てきた。子育てにやさしいマンションは共働きの夫婦に支持される(続く) -
新住まいの「ことわざ」<188> 家を破る鼠は家から出る 松岡英雄
オリンピックの招致が決まった途端に臨海副都心のマンションの売れ行きが良くなったという。理由は何であれ売れることは良いことだ。これから売り出す予定の物件担当者もホッとしていることだろう。 消費税が8%(続く) -
新住まいの「ことわざ」<187> 鬼の留守に新宅 松岡英雄
江戸時代は妖怪ブームだったらしい。黄表紙や浮世絵にいろんな妖怪が扱われ、庶民に人気があった。妖怪が時の権力者をとっちめるという筋書きなども支持された理由のようである。妖怪の例としては、河童、天狗、鬼(続く) -
新住まいの「ことわざ」<186> 国を治むる本は、家を斉(ととの)うるにあり 松岡英雄
49年前の10月10日、東京は秋晴れの素晴らしい天気だった。下宿の大家さんのご厚意で一緒に白黒テレビで開会式を見ていた。 大学1年生、テレビも新聞もない下宿生活をしていたので、せっかくのオリンピックをリア(続く) -
新住まいの「ことわざ」<185> 隣の喧嘩に余所(よそ)の火事 松岡英雄
吉永小百合さんは本名か、それとも芸名なのだろうか。彼女がデビューした頃、小百合という名前が新鮮だった。歳老いて、小百合は似合わないのではないかと思ったが、どうして、彼女は名前に相応しい女性として今も(続く) -
新住まいの「ことわざ」<184> 天井の節穴を数える 松岡英雄
豆電球の薄暗い灯りの中に浮かぶ天井の板目の模様はいろいろな形に見える。人の横顔に見えたりするとちょっと楽しい気分になった。地方から出てきた大学1年生の東京暮らしは、最初の間は寂しくて、下宿の天井がず(続く) -
新住まいの「ことわざ」<183> 家の高いより床の高いがよい 松岡英雄
1960年安保の時は西田佐知子さんの「アカシアの雨がやむとき」が、70年安保の時は藤圭子さんの「圭子の夢は夜ひらく」が、活動家の間でよく歌われたという。 60年安保の時は中学3年生、70年安保の時は社会人3年(続く) -
新住まいの「ことわざ」<182> 大風吹けば古家の祟り 松岡英雄
国交省に設置された「中古住宅の流通促進・活用に関する研究会」(座長・中城康彦明海大学教授)が、「木造戸建は約20年で価値ゼロという『常識』が中古住宅流通市場にも担保評価にもいわば『共有』されており、相互(続く) -
新住まいの「ことわざ」<181> 夏炉は湿をあぶり冬扇は火をあおぐ 松岡英雄
企業のなかには「追い出し部屋」と呼ばれる部署があるという。 要らなくなった社員を退職に追い込むための部署だから、会社側はもちろん否定するがその存在は公然の秘密となっている。「出向」もまた追い出しと(続く) -
家に諫むる子あればその家必ず正し 松岡英雄新住まいの「ことわざ」 <180>
一人の生命は全地球より重いというが、最近は随分軽くなってしまったような気がしてならない。殺人事件はテレビや映画の世界と同じように頻発している。金が欲しかった、邪魔になった、など理由は様々だが、そんな(続く) -
新住まいの「ことわざ」<179> 風呂屋の亭主 松岡英雄
富士山が世界遺産に登録されたことはまずはめでたしである。自然遺産でなかったことを残念がる声もあるが、日本人と富士山の関わりからすれば文化遺産のほうが相応しい。自然遺産にならなかったことは、自然保護に(続く) -
新住まいの「ことわざ」<177> 夏座敷と鰈とは縁端が良い 松岡英雄
母方のただ一人の叔父さんが結婚して間もない夏休み、新居に遊びに行ったことがあった。小学3年生のころである。ちょうどお嫁さんの弟(私と同じくらいの年齢だった)も来ていて、一緒に海水浴にお嫁さんが連れてい(続く) -
新住まいの「ことわざ」<176> 男は家を作り、女は家庭を作る 松岡英雄
「ワイルドだろぉ」「なでしこジャパン」「ゲゲゲの」を覚えておられるだろうか。過去3年間に流行語大賞を受賞した言葉である。 気が早いが、今年の大賞は「アベノミクス」で決まりであろう。しかし、巷ではもう(続く) -
新住まいの「ことわざ」<175> 棚から牡丹餅は落ちてこない 松岡英雄
何事もせずに幸運がまいこむなどと思ってはならない。努力もしないで利をあてにしてはいけないということ。労せず幸運を得ることは『棚ぼた』である。 東京スカイツリーの展望台に開業1年間で来場したのは638万(続く) -
新住まいの「ことわざ」<174> 家を出るとき茶を飲めば災難にかからぬ 松岡英雄
三陸地方では、明治の先人が津波の到達点に石碑を建立しその教訓を記した。しかし、時が経つにつれ碑は雑草に埋もれ、津波の記憶と共に忘れ去られてしまった。それではいけないと、東日本大震災の津波到達点に桜を(続く) -
新住まいの「ことわざ」<173> 蝦夷(えぞ)で暮らすも一生、江戸で暮らすも一生 松岡英雄
旧市街と新市街の違いは音だという。人の話し声や子供の泣き声が聞こえてくるのが旧市街、クルマの騒音ばかり聞こえてくるのが新市街。テレビのインタビューで欧州の都市に住む人が答えていた。 言われてみれば(続く) -
新住まいの「ことわざ」<172> 上棟式がすんでから雨が降ると栄える 松岡英雄
藤沢周平に「驟(はし)り雨」という短編がある。 めぼしをつけた商家に盗っ人に入ろうとした研ぎ職人の男が急に降り出した雨を避けて、八幡神社の軒下で雨宿りをしているところへ、取り分で揉めているばくち打ち2(続く) -
新住まいの「ことわざ」<171> 可愛い子には普請をさせよ 松岡英雄
今年は伊勢神宮の式年遷宮の年である。式年遷宮とは、一定の年数を経過するごとに神殿を造営し、ご神体を移すことである。伊勢神宮は20年目、出雲大社は60年目、今年は出雲大社の遷宮の年でもある。 それにして(続く) -
新住まいの「ことわざ」<170> 板に付く 松岡英雄
板は家を建てる材料として欠かせないものだが、日本語はその「板」を巧みに使い分ける。広辞苑によれば、(1)材木を薄く平たくひきわったもの(2)金属や石などを薄く平たくしたもの(3)板敷の略(4)板付蒲鉾の略(5)板(続く)