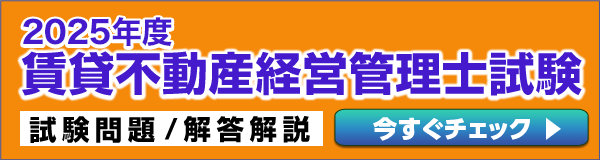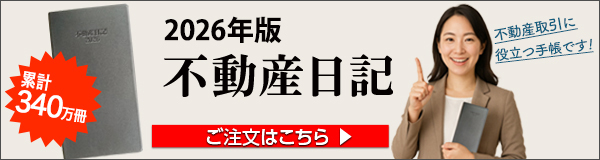新住まいの「ことわざ」 記事一覧
-
暖簾に傷が付く 松岡英雄新住まいの「ことわざ」 <109>
海外不動産事情視察旅行でスイスのベルンを訪れた時、視察の合間に街角の時計屋さんを覗いた。店番をしていた妙齢のご婦人に半分以上理解できない英語で熱心に勧められ、「ジャストルッキング」と言い出せなくて、(続く) -
暖簾に腕押し 松岡英雄 新住まいの「ことわざ」 <108>
暖簾は商店の入り口などに張られる布で、屋号・商号や家紋などが染め抜かれていることも多い。直接、風や光が入るのを防いだり、寒さよけとして取り付けられたのが始まりと考えられている。 外から内部を見えに(続く) -
「窓の雪」 松岡英雄 新住まいのことわざ(107)
3月は卒業式の季節である。「蛍の光、窓の雪……」と送る歌が聞こえてくる風景が懐かしい。 中国、晋の孫康(そんこう)が、貧しさに油が買えず、雪明かりで書を読み、学問に励んだという故事から苦学することをた(続く) -
「畳の上の水練」 松岡英雄 新住まいのことわざ(106)
大学4年のときにクルマの免許をとったが、ついに一度も運転することはなかった。完全なペーパードライバーである。 したがって、運転はできないし、もう、運転しようという気もない。更新だけはしてきた(続く) -
「驚き 桃の木 山椒の木」 松岡英雄 新住まいのことわざ(105)
雛祭りが終わったらすぐに雛人形を仕舞わないと娘の婚期が遅れるという根拠のない言い伝えがあり、親としては半信半疑ながら、それでも翌日には片付けてきた。長女の婚期が遅れたのでやきもきした時期もあったが、(続く) -
「梁上(りょうじょう)の君子」 松岡英雄 新住まいのことわざ(104)
盗人、泥棒のこと。転じて、ねずみの称。中国、後漢の陳寔(ちんしょく)が梁(はり)の上にひそむ泥棒を見て、悪い習慣が身につくと、あの梁の上の君子のようになるのだと子供に言って聞かせたという故事から。「梁」(続く) -
「七つの倉より子は宝」 松岡英雄 新住まいのことわざ(103)
昔のお大尽の家には必ず倉があった。白壁となまこ壁の組み合わせはたいへん美しく、子供心にも憧憬の念で眺めていた。戦後の貧しさの中で生きていた子供にも、倉は富める者の象徴であることがうすうす感じられてい(続く) -
「御蔵(おくら)にする」 松岡英雄 新住まいのことわざ(102)
永井荷風は麻布市兵衛町にあった自宅を偏奇館と名づけていた。ペンキ館のしゃれである。荷風はそれ以前、大久保余丁町にあった実家の屋敷内に増築した小庵にも断腸亭と名づけている。偏奇館は1920(大正9)年、外国(続く) -
「置烏(おくう)の愛」 松岡英雄 新住まいのことわざ(101)
烏(カラス)はとても賢い動物で、車に木の実を轢かせて割るところがテレビで放映されたりする。鵠沼海岸にいる烏は、観光客が食べているハンバーガーを一瞬の隙に奪っていく。鳴き声は不吉なものとされ、『家の近く(続く) -
「軒を貸して母屋を取られる」 松岡英雄 新住まいのことわざ(100)
近頃は軒の深い家が少なくなってしまった。 狭い敷地を有効に利用しようとすれば、軒や庇を浅くせざるを得ないし、また、技術の進歩により、風雨に強い壁や窓ができたおかげで、それほど軒先を必要としなくなっ(続く) -
「医者の玄関構え」 松岡英雄 新住まいのことわざ(99)
東京23区には坂がいくつあるのだろうか。歩いて調べた人によれば、700を超えるという。富士見坂は20幾つあるそうだ。もっとも地名だけで富士山は見えなくなってしまったところが多いらしい。 坂といえば、江戸(続く) -
「朝起きの家には福来たる」 松岡英雄 新住まいのことわざ(98)
朝7時前からバス停に並んでいる人がたくさんいる。東海道線辻堂駅まで10分ほどである。駅前にテラスモールという湘南地区で最大のショッピングセンターが昨年11月にオープンし、今、話題のスポットである。辻堂駅(続く) -
「門松は冥土(めいど)の旅の一里塚」 松岡英雄 新住まいのことわざ(97)
「めでたくもありめでたくもなし」と続く。一休禅師の歌とされている。正月の門松は本来めでたいものとされているが、門松を立てるたびに歳をとり、死に近づくことになるので、死への道の一里塚のようなものだの意(続く) -
「我が家に勝る所無し」 松岡英雄 新住まいのことわざ(96)
年賀状を書く時期になった。段取りの良い人はもう投函されていることだろう。クリスマスが過ぎないと書く気にならない人もいるに違いない。東北地方では年賀状を出せない人がたくさんいる。12月はいやおうなく今年(続く) -
「住めば田舎も名所」 松岡英雄 新住まいのことわざ(95)
私にはひとりの姉がいる。9歳離れている。 尾張一宮で暮らしている。親元から出たのが30年ほど前。独身を通している。まだしっかりしてはいるが、いつボケるか、動けなくなるか心配で不安である。 私のマン(続く) -
「雪隠(せっちん)と仏壇」 松岡英雄 新住まいのことわざ(94)
東北地方には、庭に御御堂が建っている古民家が多くあるという。御御堂は仏間が独立して離れになったものである。御堂は仏像を安置した堂であるから、本来はお寺に建っているものである。 「おみどう」という言(続く) -
「売り家と唐様(からよう)で書く3代目」 松岡英雄 新住まいのことわざ(93)
昨年3月、退職するときに、マンション管理会社の二代目社長さん数人が集まって送別会をしてくださった。マンション管理業界もディベロッパー系の管理会社を除けば、業績を維持拡大していくことは大変であるが、独(続く) -
「親孝行と火の用心は灰にならぬ前に」 松岡英雄 新住まいのことわざ(92)
年金の支給開始年齢を65歳から68歳に引き上げるという厚生労働省案については、来年の通常国会には法案提出はしないということになったが、いずれ再浮上してくることは間違いない。年金は入りと出との兼ね合いだか(続く) -
「箪笥の肥やし」 松岡英雄 新住まいのことわざ(91)
「断捨離(だんしゃり)」という言葉が広まっている。この言葉は、ヨガの「断行(だんぎょう)」「捨行(しゃぎょう)」「離行(りぎょう)」という考え方を応用して、人生や日常生活に不要なものを断つ、また捨てることで(続く)