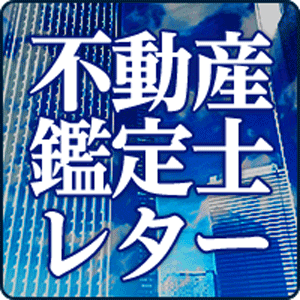共働き世帯が増え続けている。今や住宅需要のボリュームゾーンと位置付けられるまでに増えており、長期的にみても共働き世帯は増加の一途をたどっていくことが見込まれている。これまで、核家族としてひとくくりにしたファミリー層を主な需要層と捉えて住宅を供給してきた在り方も、大きな曲がり角を迎えている。
これからの社会を支えていく若年層、子育て層を中心とした住宅のニーズに応えていくためには、共働き世帯の生活実態や志向をしっかりと受け止めて応えていかなければならない。
進む女性の社会進出
男女共同参画白書によると、90年代にそれまで主流だった専業主婦世帯数を共働き世帯数が上回り、以降、その差が年々拡大してきた。15年には、共働き世帯は1114万世帯を数え、専業主婦世帯の687万世帯を大きく上回っている。産休、育児休暇をはじめとした職場環境の改善が進み、保育施設などのインフラ整備も徐々に進んだことで、女性の社会進出が広がりを見せていることが背景にある。並行して社会における女性の活躍を推進する政策が推し進められており、共働きの増加に拍車がかかっている。こうした社会の変化は、既に住宅市場にも大きな影響を及ぼしつつある。
新築マンション市場では、共働きを理由にして通勤時間が短い職住近接の立地、生活利便性のよい立地が重要視される傾向にあると、あるマンションマーケティング会社は分析している。また夫婦の収入を合算することで資金力も高く、販売に停滞感がみられる中でも好立地、高価格帯、都心に近い物件の販売は好調を持続しているとし、「ディベロッパーは強気の価格設定が可能」と指摘している。
二世帯住宅が増加
一方、二世帯住宅の需要が近年、再び伸び始めていることに象徴されるように、戸建て住宅においては同居もしくは近居といったニーズが高まっている。家事、育児の支援を親世帯に頼る共働き世帯が増えているためだ。大手住宅メーカー系のシンクタンクの調査によれば、フルタイムの共働き世帯は、近居でも7割が、親世帯と1時間以上離れて暮らす世帯においても2割が子育てにかかわる何らかのサポートを親から受けている実態が明らかになった。同グループでは、二世帯住宅で培った設計や生活提案のノウハウを、共働き世帯の住宅にも広く生かしていく方針だ。
通勤時間の短縮と子育てサポートは、今の共働き世帯にとって最大の関心ごとになっている。家庭生活の豊かさをそこに求める傾向が今後も高まっていくことは明らかだ。そうした期待に応えるところに、住宅を供給する側の大きなチャンスがあるはずだ。