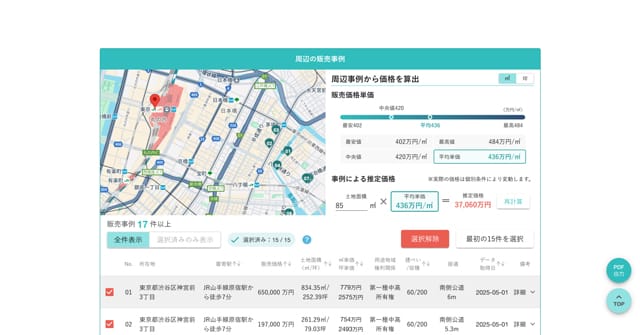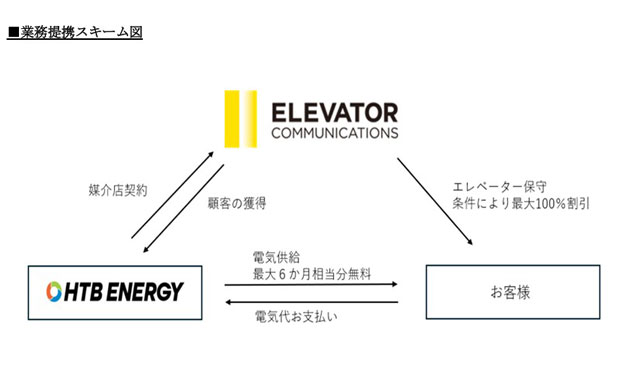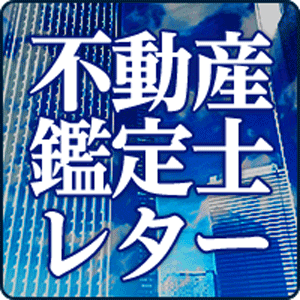戦時体制を支えるため1941(昭和16)年に導入された「正当事由制度」が今も借家法には残されている。その不合理さを回避するため00年3月に「良質な賃貸住宅供給促進法」によって創設されたのが定期借家権である。
そのため、定期借家は正当事由がなくても期間が満了すれば貸主が賃借人を追い出せるという点ばかりが強調されるが、定期借家を活用する最大のメリットは貸主・借主双方の「賃料増減請求権」を排除する特約が有効になる点である。
◇ ◇
近年、分譲マンション価格が高騰し、中古価格も上昇しているため一般庶民の間では購入を諦め、賃貸に切り替えるケースも増えているという。しかし、その賃貸も需要が増えているためか家賃が上昇傾向にある。そして、本紙調査(5月14日号1面)によれば都心部などでは新規賃料ばかりか入居中の賃借人に対しても更新時での値上げ要請が増え始めているようだ。
もちろん、値上げ要請があったからといって直ちに応じる必要はないが、借り手のほうは気分が落ち着かない。とくに、家賃はこれまで長い間、横ばいか微落傾向にあったため値上げ要請はショックでもある。
賃貸住宅入居者が今後安心して居住するためには家賃を固定化する契約にすればいい。あたかも住宅ローンで変動ではなく固定金利を選ぶ心境だ。
それが可能なのが定期借家である。定期借家は貸主と賃借人が対等で自由に契約を結べるようにするために創設されているので、契約期間はもちろん、期間中の家賃を特約で固定させることができる。普通借家では賃料固定化の特約をしても、それは賃借人の減額請求権を奪うことになるため無効となる。
賃料を固定して仮に期間5年の定期借家契約を結ぶと、普通借家ならその間2回払うことになる〝更新料〟の負担もなくなる。
一方、賃料の固定化は貸主にとっても一定期間の賃料収益を確定させることができるというメリットがある。たとえ人気エリアの物件であっても建物が年月を経るにつれ家賃下落のリスクがあるからだ。
依然低い普及率
それにしても定期借家権の普及率は依然として低い。アットホームの23年度調査によれば首都圏の賃貸物件に占める割合は約5%以下である。ただ、詳細に見ると東京23区の70m2超(大型ファミリー向け)マンションにおける定期借家割合は30.7%と突出し、神奈川県も21.1%と高い。しかし50~70m2(ファミリー向け)になると23区でも10.2%、神奈川で4.4%と低下する。要するに富裕層が住む広めの物件では定期借家の割合が比較的高い。
ということは、良質な賃貸住宅を供給するという定期借家の目的は高い家賃を払うことができる富裕層市場には貢献できているという穿った見方をすることもできる。
ただ、定期借家はむしろ一般庶民層のための制度と考えたい。「良質な賃貸にほどほどの家賃で安心して暮らしたい」――賃貸住宅の使命は本来そういうものだろう。
更に言えば、家賃並みと言われるローンだが、それを30年以上払い続けても返済完了後に自分の資産とすることを望むのか、それともローン並みの家賃を払ってもライフスタイルに応じた、しかも分譲マンションに引けを取らないような賃貸に暮らすのか、その選択がもっと自由におおらかにできる社会が理想ではないか。
70m2以上のファミリータイプともなれば物件数が極端に少ない現状の賃貸市場ではそれが難しい。本格的成熟社会に向かう日本社会にとって分譲も賃貸も共に大事な社会インフラとなる。
両市場がそれぞれの社会的役割を踏まえ、価格や家賃設定の前に、住まいの本質とはなにかを求めて競い合うようになれば、どちらの市場にも活気が生まれ、良質な住まいがあふれ、人々の豊かな暮らしを支えることができる。