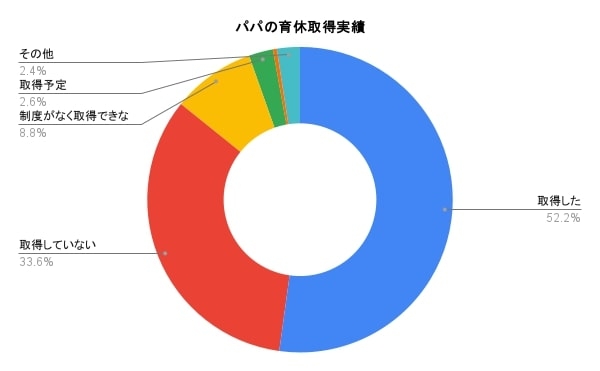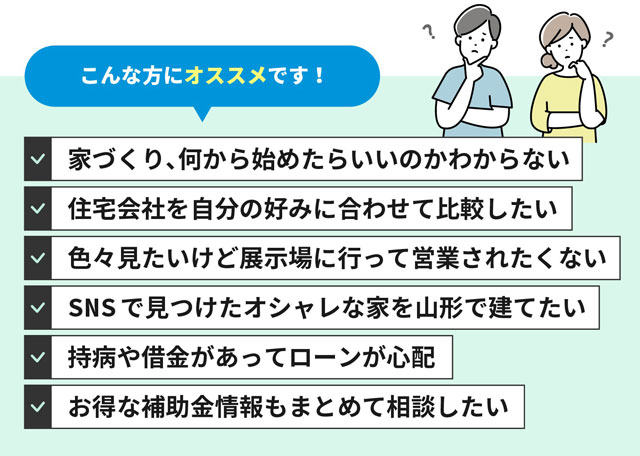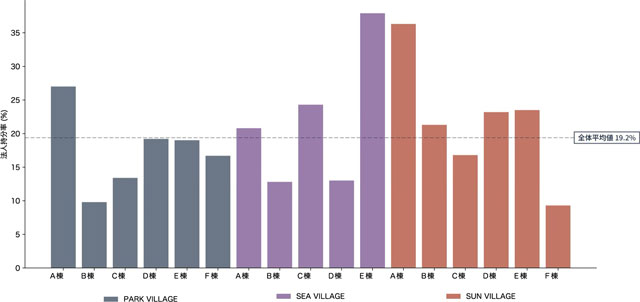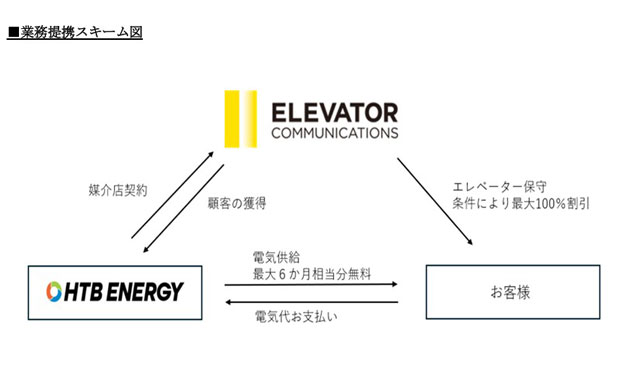近年、カスタマーハラスメント(カスハラ)に対する問題意識が高まっており、不動産業界でも対応の動きが顕在化している。昨年には国土交通省がマンション標準管理委託契約書を改訂し、カスハラ対策の規定を新設。今年5月には、全日本不動産協会の研究機関が「対策要領」を策定した。まだ〝業界を挙げて対応〟という段階ではないものの、こうした姿勢は積極的に応援したい。
▼というのも、カスハラ対策に実効力を持たせるためには、事業者の対応が欠かせないからだ。評価や雇用への影響を考えれば、従業員がカスハラに毅然とした対応をとるのは極めて困難。経営側が収益を優先し、理不尽な顧客であっても現場に対応を求めてきた構造が、これまでカスハラが野放しにされてきた要因との指摘は多い。
▼パーソル研究所が6月に公表した、サービス職へのカスハラに関する調査によると、「カスハラ被害後の会社の対応」は「被害を認知していたが何も対応はなかった」が最多の36.3%。相談後のセカンド・ハラスメントは、「ひたすら我慢を強要された」が11.0%で最も多かった。
▼こうした構図は、セクハラやパワハラなど多くのハラスメントにも当てはまる。加害者の責任は当然として、更に「それを容認・黙認する企業や社会の風潮こそが最大の課題」との認識が徐々に広がったことで、今般の不動産業界の動きにもつながっているのだろう。