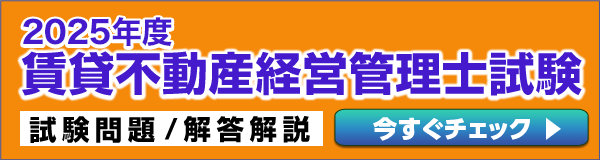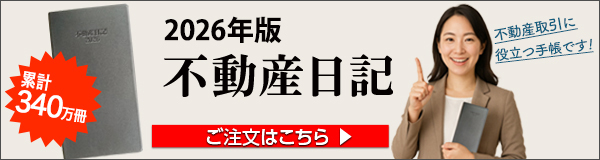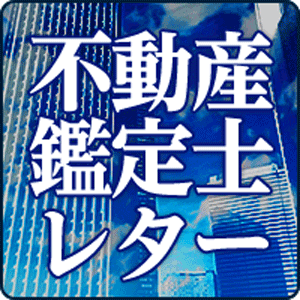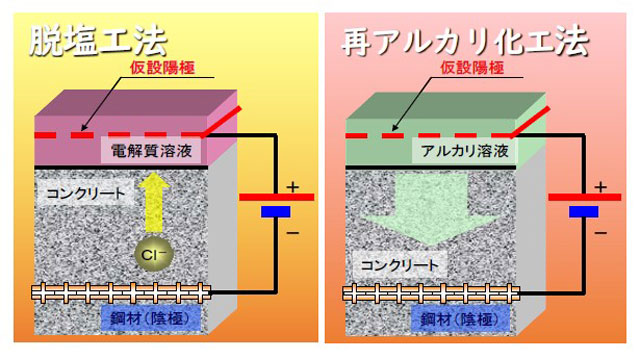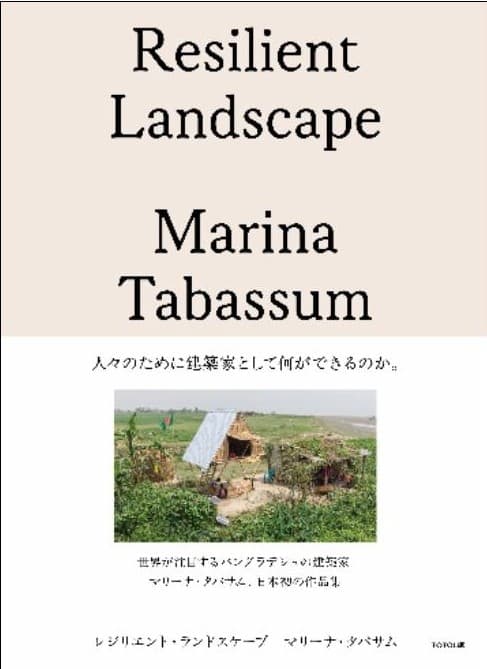不動産取引における調査は「買主の購入目的」と「(買主に説明し尽くせるという)自分の納得」この2点を満たすまで行うのが良い。当然、現状の正しい姿を把握し、重要事項説明(以下、重説とする)の各項目を埋める不動産調査は必須となるが、これは最低限の話だ。不動産の調査は調査をしようと思えば際限なく行えてしまうほど、その幅は広く深い。そのためどこかで区切りをつけることになるが、一般的には売買契約までの時間との関係で「まぁここまでか」となりやすい。
しかし、それでは不十分。冒頭の「買主の購入目的」と「自分の納得」まで行えば買主も満足する取引になるのでトラブルになりづらく、リピートにつながりやすくなる。そのラインを目指して不動産調査を行っていくようにしよう。
まず「買主の購入目的」に沿った調査は不可欠だ。これをしておかないと、例えば「結局、私の希望する3階建ての家は建てられるんですよね」と突っ込まれたときに答えられなかったり、引き渡し後に「区役所で3階建ては難しいと言われたのですがどうしてくれるのですか」とトラブルとなる。そのため、買主の購入目的を確認したら、「問題なく3階建ては出来ます」、「高さが10メートル未満なら可能です」などと回答ができるように購入目的の成就に関連する調査はすべて行っていこう。具体的には土地や一戸建てなら各種条例や、建築基準法上の取り扱い、建築基準法等以外のその他法律、現地の状況、近隣関係などである。マンションなら管理に係る重説報告と隣家との関係だろう。買主の購入目的によってはこの辺りを詳しく調査をしていこう。
また、「自分が納得」するまで調査をすることも必要だ。買主に説明をするにしても自身が調査し尽くしていれば「この説明で間違いないです」と言い切れるようになる。要は自信を持って説明ができるようになる。不動産関係者以外の買主は、皆さんの調査結果や重説を聞いても本音は「よく分からない」が感想だろう。
ただ、皆さんが自信を持って説明しているのか、自信がないのかは分かるはずだ。筆者も重説が終わり買主にいかがですか?と聞いたときに言われることがある。それは「正直難しい内容なので分からないけど、あなたが自信をもって問題ないですと言ってくれたのでそれで良いです」ということだ。買主の納得を得るために、まずは自身が納得できるように調査をする、プロとしてはその辺の姿勢は持っておきたい。
まとめとする。表題の「不動産取引の調査はどこまで行うべきか」は、現状の正しい姿を把握した上で、重要事項説明の各項目+買主の購入目的+自分の納得の3項目を満たす範囲を調査していく。もしくは、この辺りを目安に調査をすることと言えるだろう。
■ □ ■
【プロフィール】
はたなか・おさむ=不動産コンサルタント/武蔵野不動産相談室(株)代表取締役。
2008年より相続や債務に絡んだ不動産コンサルタントとして活動している。全宅連のキャリアパーソン講座、神奈川宅建ビジネススクール、宅建登録実務講習の講師などを務めた。著書には約8万部のロングセラーとなった『不動産の基本を学ぶ』(かんき出版)、『家を売る人買う人の手続きが分かる本』(同)、『不動産業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書』(技術評論社)など7冊。テキストは『全宅連キャリアパーソン講座テキスト』(建築資料研究社)など。