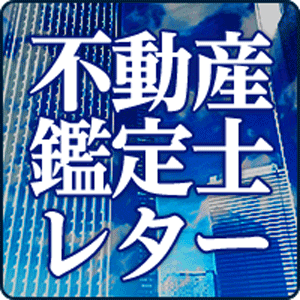中小建築会社の倒産が増えている。帝国データバンク(TDB)の調査によれば24年の建設業全体の倒産件数は1890件、過去10年で最多となった。そのうち、従業員10人未満の会社が1742件で全体の92.2%を占めている。建築コストの高騰で利幅が縮小しているのが最大の要因だ。
コスト上昇分を受注金額に上乗せすると、他社との受注競争に勝てないので無理してでも安い価格で受けることになる。そうすると、建材や人件費高騰が続いているため、途中で資金不足に陥る。施主への値上げ交渉も難しい。資金繰りを良くするためには、新たな工事を受注して初回金をそちらに回すしかない。いわゆる〝自転車操業〟なのでいずれは行き詰まる。コロナ下で借りた「ゼロゼロ融資」の返済負担がそれに追い打ちをかけているという側面もある。
建築会社が建物完成前に倒れると、個人投資家などの施主が大損害を被るのはもちろん、下請け会社も未収金を抱えて苦しむことになり、ヘタをすれば連鎖倒産となる。そうした〝倒産リスク時代〟を迎えて、今はサラリーマン投資家が新築マンションを建てる動きがピタリと止まったという話もある。
倒産しない中小
昔から「不動産屋さんは倒産しない」と言われてきたが、それはモノではなく〝情報〟を扱う産業だからである。筆者の家の近くにも〝一人社長〟の不動産屋があるが、少なくともここ20年、お客さんが出入りしているところは一度も見たことがないのに営業は続いている。TDBによれば仲介業者の倒産は過去最多となった23年でも120件にとどまり、24年は若干減少した。過去最多を記録した背景には賃貸需要の低迷(転勤や親元からの独立の減少など)、家賃・引っ越し費用の高騰などによって個人の転居ニーズが減少したことなどが挙げられている。つまり、客付けに特化した仲介会社が多かったのではないか。コロナ下でも一定の管理戸数がある仲介会社は生き残っているはずだ。
つぶれない、つぶれにくい構造をもつ中小不動産会社の使命は、まさにそこにある。どういうことか。仲介業者の場合、契約したら「さようなら」ではなく、自社の仲介で家を購入した人とその家には仲介後も関わっていく姿勢がこれからの仲介業者の在り方だと思う。オーナーから物件の管理も任されている仲介会社ならオーナーの資産管理会社として子々孫々まで関わっていく責務がある。そうした姿勢や理念は会社の規模にかかわらず可能である。要するに〝地域と共に歩む〟という覚悟である。
しかし、小さな不動産会社がこれから何十年も何百年も会社を存続させていくためにはどうすればいいのか。その答えは一つしかない。地域に住む人たちから求められる会社になるということだ。
管理物件のオーナー、その管理物件に住む入居者、仲介で家を購入してくれたお客さん家族とはもちろん、地域に暮らすサラリーマン、商店主、お年寄り、子供たち、すべての人たちとの交流を大切にし、地域にコミュニティを育てていく努力をしていけば、地域の人たちから「なくてはならない会社」という評価が得られるはずだ。そうなれば、〝100年企業〟も〝200年企業〟も夢ではない。
疲弊する町
今は地域も町も人々の交流がなく、疲弊している。〝向こう三軒両隣〟のお付き合いがある家は少ないだろう。昔ながらの商店街が残っている街は珍しいから、ときどきテレビが取材に来る。〝床屋談義〟ができる床屋もない。町会に若者が顔を見せないから、お年寄りと若者たちとが交流する場がない。
その疲弊した地域を再生し、人々が心に潤いをもてる街づくりができるのは地域と共に歩む覚悟を決めている地元密着の不動産会社だけである。