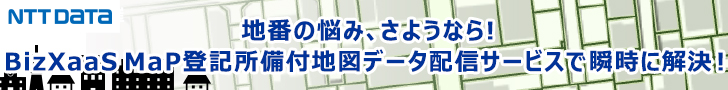国と業界6団体で構成する「宅地建物取引業リスキリング協議会」が9月17日発足した。大手、中堅、中小全ての不動産業従事者全体の資質向上を目指す。DXの推進、空き家問題の深刻化、コンプライアンス重視の傾向など不動産業を取り巻く新たな環境変化に対応できる人材確保が急務となっているためだ。
環境変化はマンション市場でも起こっている。首都圏では16年に初めて新築マンションの供給戸数を中古マンションの成約件数が上回って以来、流通市場はその存在感を増しつつある。現在は新築(2.5万戸)と中古(3.5万戸)を合わせて約6万戸の市場だがその約6割を中古が占める。
そうした中、仲介業務を担う専門家として唯一の「士業」となっている宅地建物取引士が果たす役割と責務は大きい。中古市場で物件を探すユーザーにとって、信頼すべき専門家といえば宅建士だからだ。日本ではこれまで企業のブランドや信用力で不動産会社を選ぶユーザーが多かったが、近年は個々の宅建士の能力、人柄、誠実さなどを基準に選ぶ傾向が強まっている。そのため自社のホームページ上で社員の職歴、得意分野、趣味、モットーなどを紹介する不動産会社も増えている。そうしたユーザーのニーズに応えるためにも不動産業界は、不動産専門家としての知識、能力、仲介実績などがユーザーに分かりやすく、かつ客観的基準のもとに公開される新たな制度の創設を検討すべきだろう。それはリスキリング協議会が大きな目的としている業界全体の底上げにもつながっていく。仲介を依頼するユーザーにとって、個々の宅建士の力量にばらつきがあっては安心して中古住宅を求めることができず、市場の拡大・活性化は期待薄となる。
では、能力や知識のレベルが均一化すれば流通業界の発展は約束されるだろうか。実はその先に宅建士に求められる最も重要な要素がある。それは、依頼者からの信頼を得るために不可欠なコンプライアンス意識だ。コンプライアンスは法令順守にとどまらない。人間としての誠実さ、職業人として高い倫理観を持つことだ。
首都圏で供給される新築マンションの数に比べて、常時中古市場に売り出されている数(在庫)はその約2倍。選択肢の幅が広がるほど、不動産専門家として提供すべき情報量も増える。依頼者の利益を守るための細心の注意力が求められることになる。
業界は今ようやく本格的なストック時代を迎えた。これまでは国民の新築志向が住宅着工を増やし内需拡大の柱となってきたが、今後は中古住宅流通市場の活性化がその役割を担っていかなければならない。そのためには依頼者が安心して媒介業務を託せるようにコンプライアンス意識が浸透した業界に変革し、連携するリフォーム市場と共に新たな〝内需拡大〟の柱になっていくことを期待する。