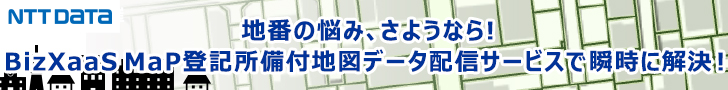他者(ヒト)が住んだ瞬間に〝中古〟と呼ぶ、それは日本人ならではの感性である。しかし、わが政府は16年前の2009年に長期優良住宅法に基づく「長期優良住宅認定制度」を始めている。にもかかわらず、いまだに築1年の長期優良住宅をも〝中古〟と呼ぶことを許しているのはなぜか。それは新築住宅優先の思考から国民も業界も政府も脱却できていないからである。
◇ ◇
09年と言えば前年秋のリーマンショックの影響で首都圏新築マンションの供給戸数が08年の7万2000戸から3万6000戸へと急落した年である。その後は13年の5万戸台まで回復したがそこをピークに供給戸数は減り続け、16年には新築マンションの供給戸数がついに中古マンションの成約件数を下回る。そのときから、時代は中古市場に主役の座が移り始めていたのである。
実は本コラムで「中古という言葉」をテーマにするのは24年2月6日号以来である。ちなみに、その時の見出しは「百害あって一利なし 単に住宅と言えばいい」とした。 今回再度取り上げた理由は、先々週の住宅新報(10月28日号)に、タカマツハウスが実施した戸建て住宅購入予定者の意識調査「8割超が〝資産価値を重視〟」という記事を見つけたからである。
また、同号1面では新築マンション市場でも供給戸数が絞られる中、資産価値重視の傾向が強まっていると報じている。つまり、マンションも戸建ても購入者の多くが資産価値を強く意識するようになってきたということである。そうであればなおさら、買った瞬間に「中古」と呼ぶ慣習は直ちにやめるべきではないか。
活性化の足かせ
考えてもみてほしい。今日本には約6500万戸の住宅がある。それに対して毎年供給される新築住宅は約80万戸。総ストックのたった1.2%に過ぎない。そのわずかな新築住宅のために、なぜ全ストックの資産価値を貶めるような〝中古〟という言葉を使わなければならないのか不思議である。そもそも国土交通省が流通市場の活性化に取り組んでいるのは何のためか。既存住宅の市場での流動性を高め、資産価値を維持・向上させていくためである。 その一方で相変わらず「中古」という言葉を使い続けることは市場活性化の足かせにしかならない。
築年志向を脱却
首都圏のマンション市場では現在、数年前に売り出された中古マンションが新築時を上回る価格で取引される事例がいくつも目撃されている。当然である。マンションの生命線でもある好立地の土地は既にほとんど開発尽くされ、新たに売り出されるマンションよりも過去に開発された中古マンションのほうが立地的にはるかに優れていることが多いからである。数年の築年数など気にしない人たちが増えている。
そうした資産価値を重視する人たちは取得した住宅の資産価値が維持・向上されていく施策を望んでいる。「中古」という言葉の最大の弊害は「新築よりも安いことが中古の魅力」という誤ったメッセージを伝えていることである。新築よりも安いことを最大のメリットとしている限り、流通市場の発展は望めない。なぜなら、安いことを理由に買った人は築年と共に自分の住まいの資産価値が落ちていく(安くなっていく)ことを認めざるを得ないからである。
そうではなく、これからの流通市場は「住宅を買った瞬間に今度は売り手の立場になる」ことを国民が理解し、そうした売買の繰り返しの中でしか資産価値を維持していくことができないことを共通認識としていかなければならない。今、日本の既存住宅の流通比率(ストック比)は0.3~0.5%。首都圏でも0.4%で欧米の2~3%に比べかなり低い。これを日本は持家の住み替え率が低いからと諦めてしまってはならない。