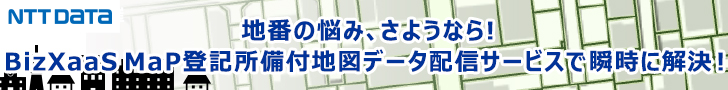投資
-

投資法人みらい 12月16日上場へ 将来はインフラ・森林も
住宅新報 11月22日号 お気に入り投資法人みらいが12月16日、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場する。このほど東証から承認を得た。三井物産グループと、独立系アセットマネジメント会社であるイデラキャピタルマネジメントがスポンサー(続く) -

売上高4%増に 森ビル・中間決算
住宅新報 11月22日号 お気に入り森ビルの17年3月期中間決算は、売上高1521億円(前年同期比4.3%増)、営業利益383億円(同17.9%減)、経常利益308億円(同25.7%減)、当期純利益154億円(同50.0%減)。増収減益だったが各事業は期初の予定通り進ちょくし(続く) -

再エネ活用による 地方創生への道(3) 全国太陽光発電等推進協理事赤川彰彦 環境と観光産業の市場規模 交流人口増加と継続性が鍵
住宅新報 11月22日号 お気に入りエネルギーは、生活や事業を行う上で不可欠の基礎である。化石燃料はCO2を排出し、原発は安全性に問題がありテロの標的施設にもなる。その点、再エネは安全にして環境負荷が小さく、地域性、普遍性と分散型の特徴(続く) -

点検・不動産投資 新成長分野への展開 宮城大学事業構想学部教授田辺信之 ■33 「インフラ」 (15) 前田建設取締役常務執行役員岐部一誠氏に聞く 中計に〝脱請負NO1〟盛る
今回は、前田建設工業でインフラ事業に取り組む岐部一誠取締役常務執行役員(経営企画担当兼事業戦略本部長)に、同事業に取組んだ経緯や現状、今後の有望分野、課題などについて、話をうかがいます。前田建設は、仙(続く) -

健美家(けんびや) 収益物件市場動向レポート (1) 1棟アパート編 成約利回り 主要都市は過去最低に
不動産投資と収益物件の情報サイトを運営する健美家(けんびや)が、今回から6回にわたり、サイトに登録された物件について調査(四半期毎)した内容を報告する。1回目は個人投資家に一番人気がある「1棟アパート」(7(続く) -

働き方改革 業務場所を自分で決める リモートワーク導入1カ月 リクルート住まいカンパニー人事部ダイバシティ推進G 大庭千佳氏に聞く
住宅新報 11月15日号 お気に入りリクルート住まいカンパニーは、働き方の選択肢の一つとして、10月からリモートワークを本格導入した。従業員は自分の都合に応じて、自宅やカフェ、レンタルオフィスといった会社のオフィス以外の場所でも業務を行(続く) -

米国大統領選、不動産市場への影響 JLL日本リサーチ事業部長赤城氏 不確かさあるが歓迎 米国経済の急成長を期待
住宅新報 11月15日号 お気に入り日本時間11月9日の米国大統領選挙で、共和党候補のドナルド・トランプ氏が勝利したことを受け、翌10日にJLL日本リサーチ事業部長の赤城威志氏が不動産市場への影響について見解を発表した。 「想定外の結果によ(続く) -

決算 大幅な増収増益に サンケイビル
住宅新報 11月15日号 お気に入りサンケイビルの17年3月期第2四半期業績は、売上高562億100万円(前年同期比42.8%増)、営業利益78億6800万円(同153.9%増)、経常利益72億1700万円(同241.3%増)、当期純利益49億5500万円(同406.2%増)だった。五反田サ(続く) -

決算 新規事業も好調 サンフロンティア不
住宅新報 11月15日号 お気に入りサンフロンティア不動産の17年3月期第2四半期業績は、売上高189億600万円(前年同期比47.1%増)、営業利益51億7400万円(同45.4%増)、経常利益48億4000万円(同45.0%増)、当期純利益34億2000万円(同25.9%増)だった。主(続く) -

再エネ活用による地方創生への道(2) 全国太陽光発電等推進協理事赤川彰彦 自治体の導入状況 課題は財源・人員・経験不足
住宅新報 11月15日号 お気に入り地球は今や温暖化により危機的状況にある。IPCCの第5次評価報告書(14年)によると過去133年間に世界平均気温は0.85℃上昇、海水面は過去110年間に計19センチ上昇。2100年の最悪シナリオでは、気温は2.6~4.8℃の上昇(続く) -

点検・不動産投資 新成長分野への展開 宮城大学事業構想学部教授田辺信之 ■32 「インフラ」 (14) いちごECOエナジー社長五島英一郎氏に聞く サスティナブルな事業に発展
(前号からの続き) ――実際にメガソーラー事業を運営していく中で、維持管理面でもいろいろな苦労があると思います。 万全な監視態勢 その一つが、気候変動への対応だ。もちろん、外部評価機関による発電予測を元(続く) -

今後の経済担う「ミレニアル世代」 働く場の柔軟性重視 企業の生産性に影響も
住宅新報 11月8日号 お気に入り次世代を担う人材として注目を集める「ミレニアル世代」。1980~2000年の間に生まれた世代を指し、日本では全人口の2割ほどを占める。デジタル機器やインターネットが普及した環境に育ち、好景気も経験していない(続く) -

不特法事業参入へ 投資家層拡大狙う 武蔵コーポレーション
住宅新報 11月8日号 お気に入りアパートなどの収益物件の買い取り再販とその管理を手掛ける武蔵コーポレーション(さいたま市、大谷義武社長)はこのほど、業績説明会を開き、今後の事業戦略として不動産特定共同事業法に基づく小口投資商品の販売(続く)