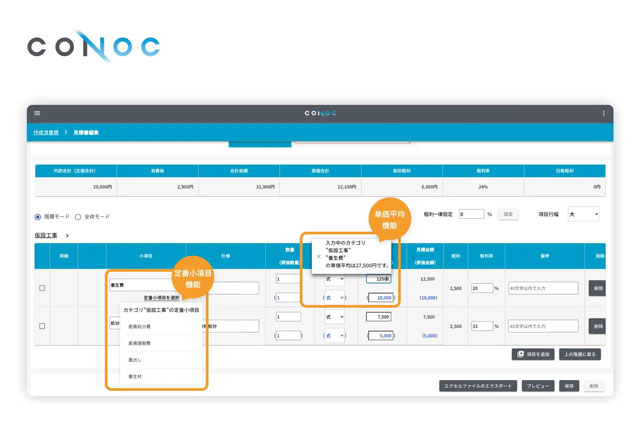20年は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大に伴い、全国的にインバウンド観光客をはじめ人の往来が激減したことで、不動産市場でも取引に慎重な動きが拡大。そのため、今回の地価公示では、商業地を中心に地価の下落傾向が鮮明に見られた。他方、コロナ禍を受けた新たな需要の兆しもうかがえる。【1面に関連記事】
21年の地価公示を地域別で見ると、三大都市圏の変動率が地方圏より大きくなった。三大都市圏における全用途平均は0.7%下落(前年比マイナス2.8ポイント)、商業地は1.3%下落(同マイナス6.7ポイント)となり、東京圏、大阪圏、名古屋圏のいずれも8年ぶりに下落に転じた。住宅地については0.6%下落(同マイナス1.7ポイント)となり、東京圏が8年ぶり、大阪圏が7年ぶり、名古屋圏が9年ぶりに下落に転じている。
特に大阪圏の商業地は1.8%下落(前年比マイナス8.7ポイント)と最も大きな変化が見られた。前年に大幅上昇となった道頓堀、宗右衛門町、心斎橋では、国内外の観光客が減少したため軒並み二桁マイナスに反転している。
東京圏の住宅地を見ると、東京23区の上昇は高級住宅地を中心に環境・利便性の良好な地点が多い港区、目黒区の2区のみ。隣県では一部の市区町村が都心近接などを背景に上昇が継続したものの、その範囲は狭まっている。
地方圏では、全用途平均(0.3%下落)と商業地(0.5%下落)は4年ぶりに、住宅地(0.3%下落)は3年ぶりに下落。地方四市では全用途平均(2.9%上昇)、住宅地(2.7%上昇)、商業地(3.1%上昇)のいずれも上昇を継続したものの、上昇率は縮小している。
今回はコロナ禍の影響を受けた初めての地価公示となる中、変動率プラスの都道府県数は住宅地が8(前年比12減)、商業地は7(同17減)。同じく変動率プラスの都道府県庁所在地では住宅地が16(同17減)、商業地は15(同25減)となった。都道府県の地価下落率は2%台までにとどまっており、リーマンショック後の影響が見られた地価公示(09年、10年)と比較して、落ち込みは小さい。
「移住の選択肢」で上昇も
地価上昇率の上位地点を見ると、前年同様、1位は住宅地、商業地共に北海道の倶知安町となった。コロナ禍に起因する取引件数の減少などで上昇率の縮小は見られたものの、住宅地が25.0%上昇、商業地が21.0%上昇と高い上昇率を維持している。倶知安町周辺の別荘地エリアでは、新型コロナ収束後を見据えた開発計画も進行。駅前エリアの商業地では、北海道新幹線の延伸等に伴う利便性向上への期待感も後押ししているようだ。
また、首都圏に近い別荘地では、静岡県熱海市(熱海駅前の住宅地)や長野県軽井沢町(住宅地および商業地)で地価が上昇。「軽井沢では、従来の首都圏の高所得層を中心とした別荘地需要に加え、コロナ禍を契機とした移住等も増加。多拠点居住の選択肢となっている」(地価公示室)という。