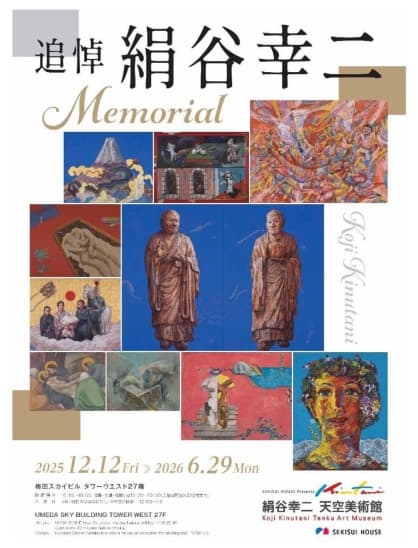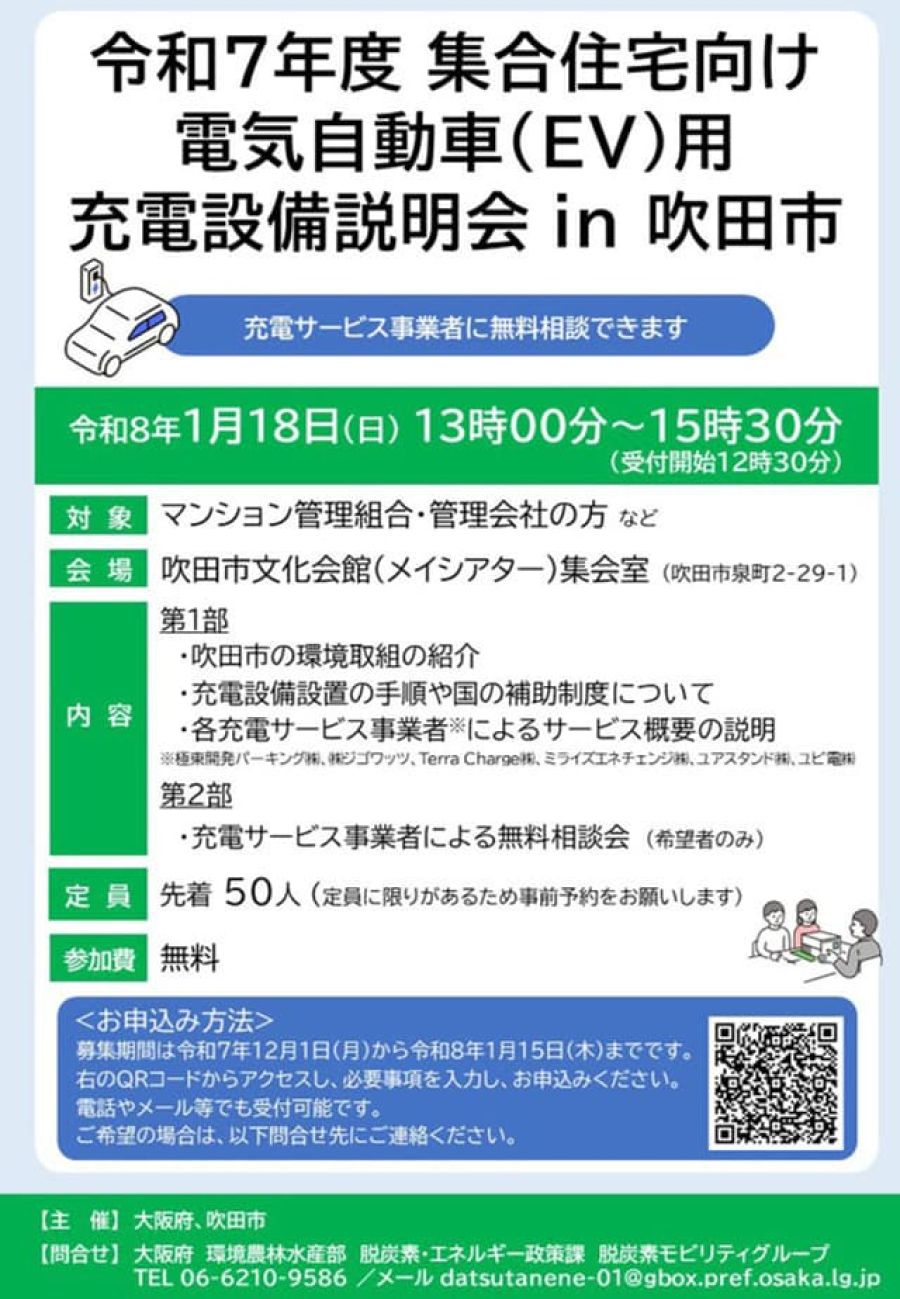小田急不動産と小田急ハウジングはこのほど、川崎信用金庫協力の下、神奈川県川崎市で「人生100年時代の今だからこそ家族で知っておきたい相続と認知症対策の基礎知識」セミナーを開催し、各社の顧客ら約20人が参加した。講師として小田急不動産、金融機関、法務局、社会福祉協議会担当者が登壇。〝資産凍結〟の現状のほか、自筆証書遺言書保管制度や成年後見制度などを解説し、事前対策の重要性を訴えた。
川崎信用金庫の吉田英和氏によると、同金庫に寄せられる相続関連相談件数は近年急増しており、今年は11月時点で既に昨年度を上回っているという。例えば代表的な相談事例が、相続が発生したことによる預金口座の凍結だ。夫が亡くなり、残された妻が生活資金である夫の口座から年金が引き出せなくなると、日々の暮らしにも支障をきたす。一刻も早く凍結を解除したくても、遺言書などがないと、相続人共有の財産として配分など様々な調整が必要になる。吉田氏は、「残された家族は心身共に疲れている中で、こうした問題にも向き合わなければならない。更に相続人間で合意が得られなければお金の出し入れができない状況が長く続いてしまう」と述べ、万が一に備えて自分の意思を表明しておくための「遺言」を用意することが有効な対策だとした。
もう一つ増えている相談が認知症に関する内容。金融機関は本人の判断能力に懸念があると判断すると、詐欺などの犯罪や不正使用で財産を失わないよう口座を凍結する。そうなると本人の介護費や老人ホームへの入居費用として使う場合であっても家族は引き出すことができない。吉田氏は、「相続の場合は発生した後、法律に沿って手続きを進めていくので明確だが、認知症は何を持って判断能力が不十分であるかを判断するのが難しく、正解がない」と、対応の難しさを述べた。老老介護など複合的な課題もあり、有効な対策として「成年後見制度」を挙げた。
こうした課題は預貯金だけでなく自宅などの不動産の扱いにも当てはまる。
実家の売却時に
小田急不動産の宮野実氏は「〝自宅の終活〟事前に確認しておきたいこと」と題し、これまで営業現場で経験した事例を基に、「不動産についても元気なうちに事前確認を進めておくことが大切」と述べた。例えば、特に戸建て住宅の場合は隣地との境界線や接道の幅員、地中埋設物、権利関係などだ。実際に実家を相続した子供が売却しようとしたときに、隣地所有者と境界の認識が異なり筆界の承諾印をもらうことができず、希望する形の分筆ができなかったケースや、相続登記未了のまま何代も経過していたため相続人を追うことができず、そのままになってしまったケースもあったという。
宮野氏は、「土地・建物の権利書や隣地等と取り交わした約束事など、ぜひ確認して家族で共有してほしい」と話した。
そのほか、セミナーでは、横浜地方法務局川崎支局担当者から今年7月に始まった「自筆証書遺言書保管制度」の手続き方法について、川崎市社会福祉協議会担当者から「成年後見制度」の種類や申し立ての流れなどについての説明も行われた。





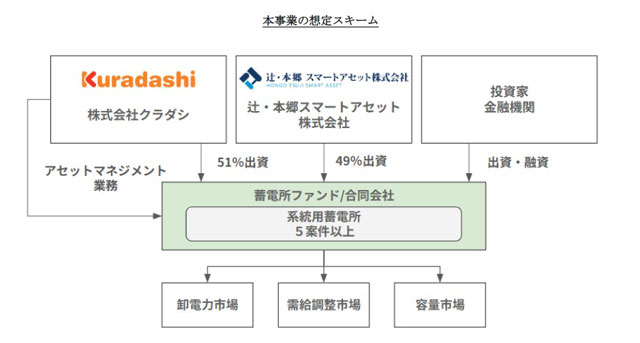


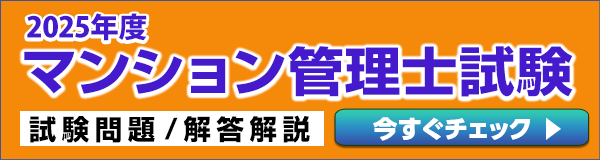
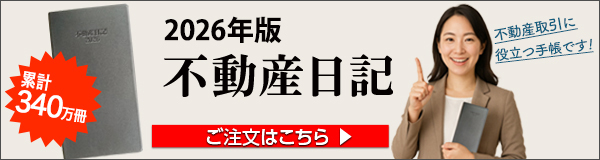

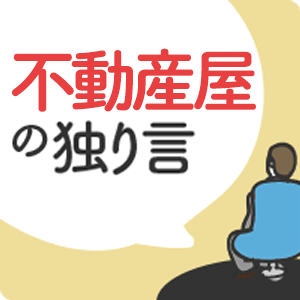

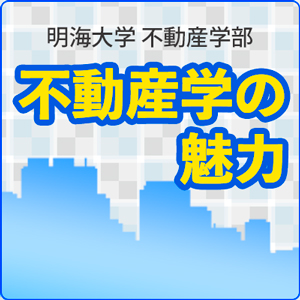
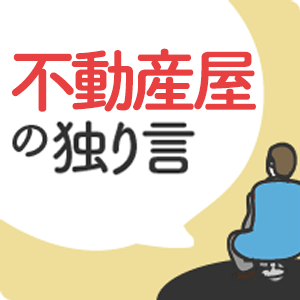


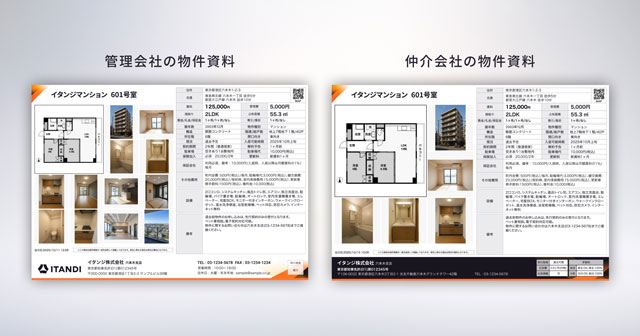
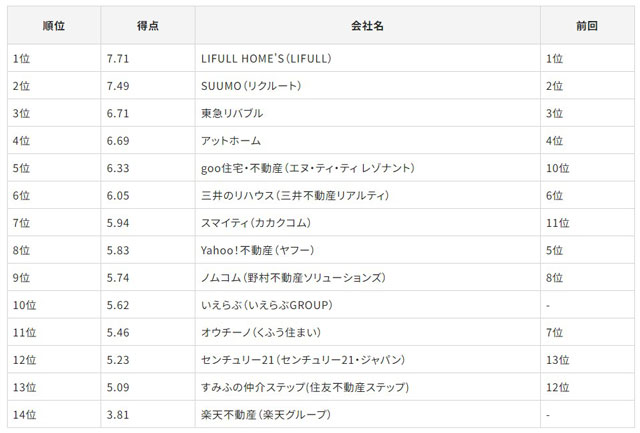
.jpg)
.jpg)