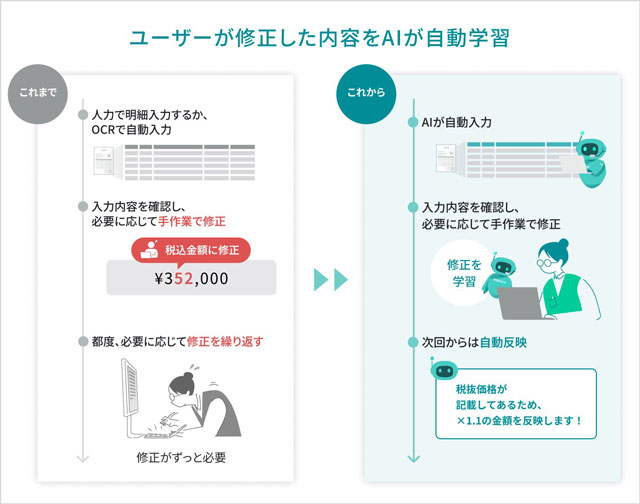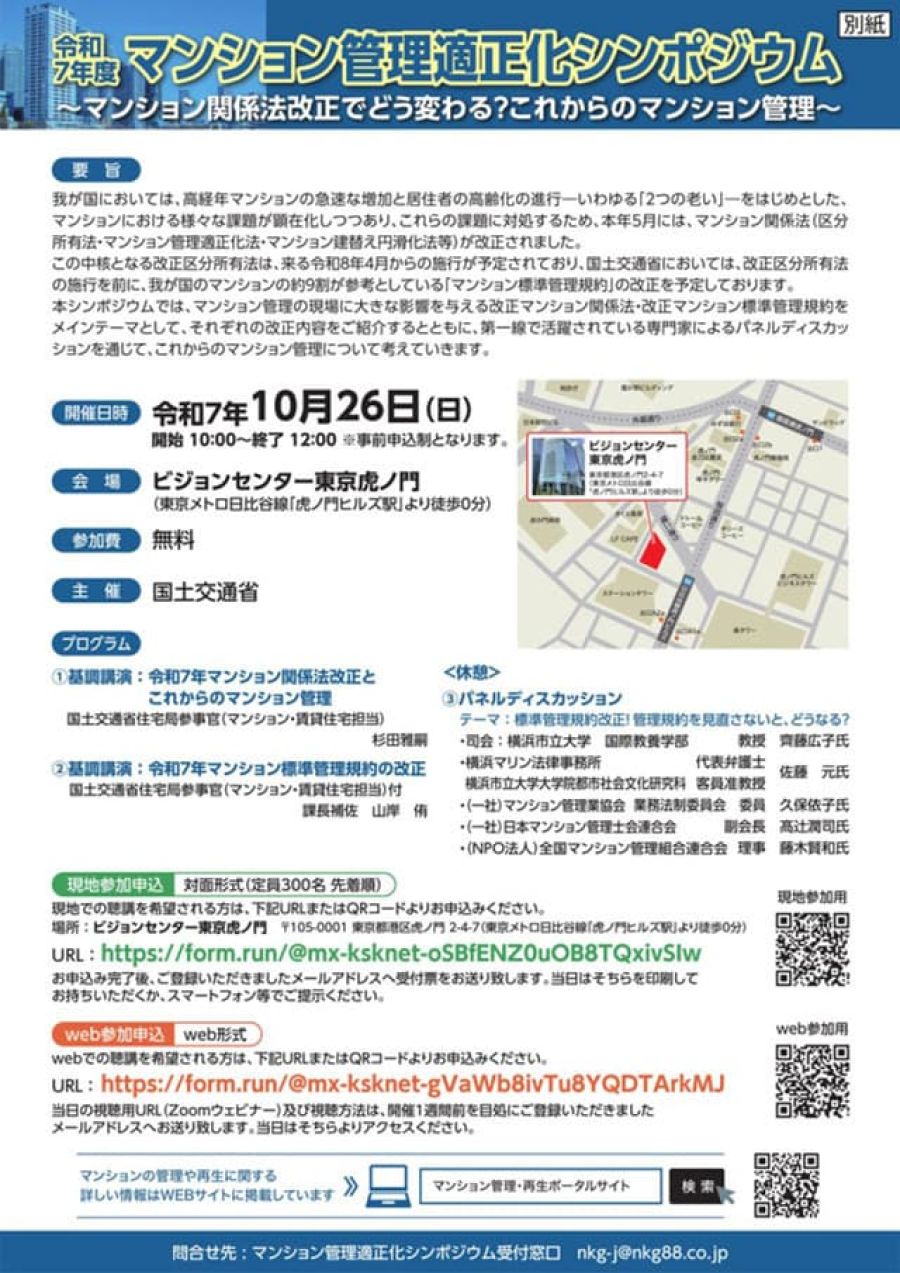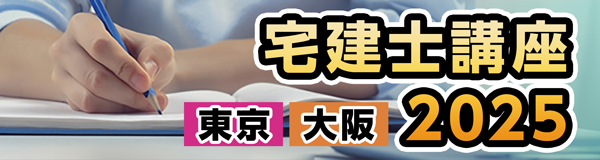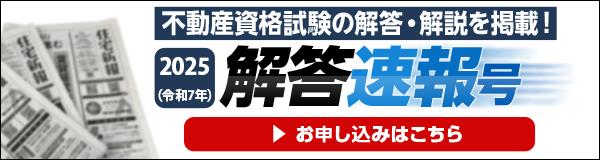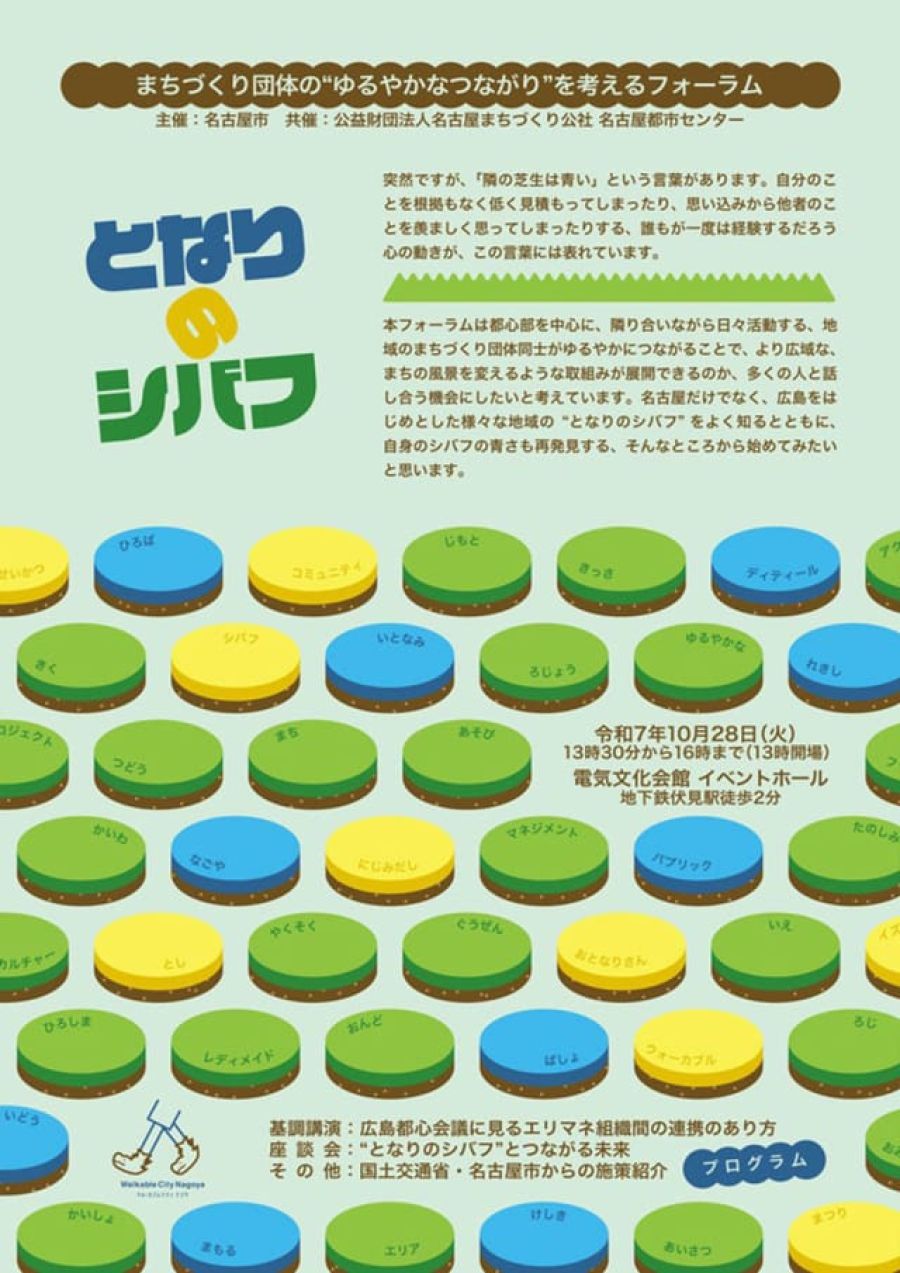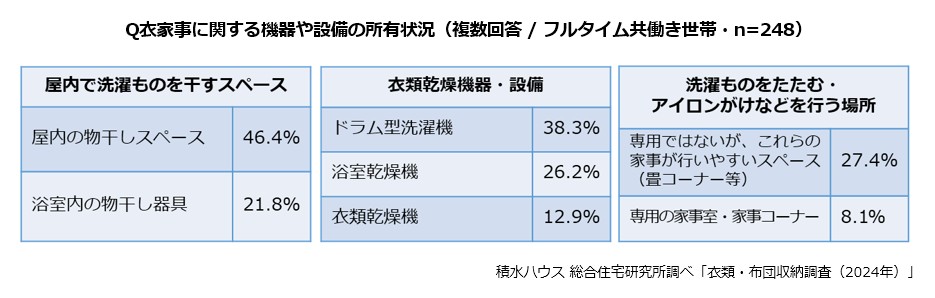国土交通省は3月17日、「第4回不動産IDルール検討会」を開催し、中間とりまとめ案について委員の合意を得た。今後、事務局では3月中に中間とりまとめおよびガイドラインを公表する方針。4月から各不動産の共通コードとしての不動産IDの活用がスタートする。
中間とりまとめ案は、不動産IDの基本ルールをはじめ、活用に向けた前提、利用拡大に向けた今後の方策などで構成される。まず、ルール整備の目的として、土地・建物いずれも幅広い主体で用いられる共通番号が存在せず、同一物件かどうかの判断に手間を要する日本の不動産の課題を指摘。不動産IDのルールを整備し、不動産関連情報の連携・蓄積・活用や消費者への的確な情報発信を図ることで、不動産業界全体の生産性および消費者利便の向上、不動産DXの推進を支えていく考えを示す。
具体的なルールの項目では、不動産IDとして、不動産登記簿の不動産番号(13桁)と特定コード(4桁)で構成される17桁の番号を使用する点を明示。特定コードは不動産番号のみで対象を特定できない場合に一定のルールに基づき付し、それ以外では「0000」の4桁を使用(上図参照)するなど、記述のルールを整理した。
また、活用の際の留意点として、「個人情報保護法との関係」や「IDとひも付けたデータの利用」などを整理した。特に「IDの入力・登録(ひも付け)」に関しては、土地と住宅を合わせて販売する際や複数筆を集約した土地の取引などの際にどのIDを入力すべきかという意見が多く寄せられた点を考慮。事務局では入力案を示しつつも、「複数のID入力を想定しうる場合、ユースケースに応じてあらかじめどのIDを入力するかは明確化する」とし、中間とりまとめにおいて整理していくこととした。
事務局では、一連の検討過程において「建物、土地のID化の必要性について委員の間で理解が進んだ」と評価した上で、情報のひも付けにおける作業手間やメリット体験など、活用に向けた仕掛けの必要性を課題と受け止める。「管理や保証分野からの関心の声が聞かれることに加え、物流やまちづくりなど関係部局との連携も課題。様々な主体の参加を促し、ルールやユースケース・メリットなどについて周知を図る」(事務局)とし、新年度以降も不動産番号をより簡易・低廉に確認できる仕組みの検討を進めていく考えを示した。
同検討会の結びのあいさつで長橋和久不動産・建設経済局長は「課題はあるものの、ルールづくりまで合意形成が図れたのは大きな前進。国交省では活用に向けた環境整備とルールの周知を丁寧に進めていく」と述べ、業界への更なる連携強化を呼び掛けた。