不動産の調査前には机上調査を行って、おおよその実勢価格を把握していったほうがいいだろう。実勢価格とは実際に売れる価格のこと。目に見えて分かりやすい物件の面積や形状といった数字や形以外にも、目に見えない需要供給関係、エリア相場、競合相手などをデータ等で判断していかなければならない。そのため、算出者の考え方や評価方法次第で実勢価格はまったく異なるものになる。
そこでオーソドックスな方法をご紹介する。
実勢価格の把握は坪単価(もしくは1m2当たりの単価)と面積を乗じて出した基礎価格に敷地形状といったデータで補正し、時価評価を出していく。その上で大まかに(1)需要と供給、(2)エリア相場、(3)競合相手、この3つでその増減を判断して出していく。
なお、坪単価等は、(1)レインズ(指定流通機構・主に成約事例を見る)、(2)ポータルサイト(スーモ、ホームズ等)のデータを用いるのが基本だ。レインズが使えない場合は、同じく成約事例が登録されている国土交通省「土地総合情報システム」で確認してもいい。
時価評価を算出したら最初に(1)需要と供給を判断する。レインズで同じエリアでの売り出し事例と成約事例の数を見ていき、その関係性を読んでいく。売り出し事例が多いのに、成約事例が少ないというのであれば、需要は低いと判断し実勢価格は低めに見ていく。類似物件を参照して減額の調整をする。逆に現在の売り出し物件が少ないのに過去の成約事例が多いのであれば、供給に比して需要は高いと判断し、実勢価格は高めに調整を行う。
続けて(2)エリア相場。エリア相場とは、そのエリアに住む人が「買ってもよい」と思える価格帯のこと。エリアに住む人の年収や資産背景によって左右される。レインズでどの価格帯が売れ線なのか、また多く成約している中心の価格帯を見て把握していく。エリア相場内なら強気な価格設定でもいけることが多く、超えるなら弱含みとなる。(3)競合相手は、レインズ、ポータルサイト掲載の類似物件の内容と価格を見比べ、よほど優劣がなければ競合物件としてマークし、価格等を決めていく。消費者は面積や立地など目や数字で見て分かり易い差は理解できるが、そうでないものの差は受け入れにくい。価格差は理解されず、単に「高い」となって売れないことになる。需要が低いエリアだと、なかなか成約しないため、競合相手よりも安い価格が実勢価格になることも多い。以上が実勢価格を把握する3点だ。この3点を総合して時価評価を調整していき実勢価格を捉えていく。参考にしていただければ幸いだ。
【プロフィール】
はたなか・おさむ=不動産コンサルタント/武蔵野不動産相談室(株) 代表取締役。
2008年より相続や債務に絡んだ不動産コンサルタントとして活動している。全宅連のキャリアパーソン講座、神奈川宅建ビジネススクール、宅建登録実務講習の講師などを務めた。著書には約8万部のロングセラーとなった『不動産の基本を学ぶ』(かんき出版)、『家を売る人買う人の手続きが分かる本』(同)、『不動産業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書』(技術評論社)など7冊。テキストは『全宅連キャリアパーソン講座テキスト』(建築資料研究社)など。


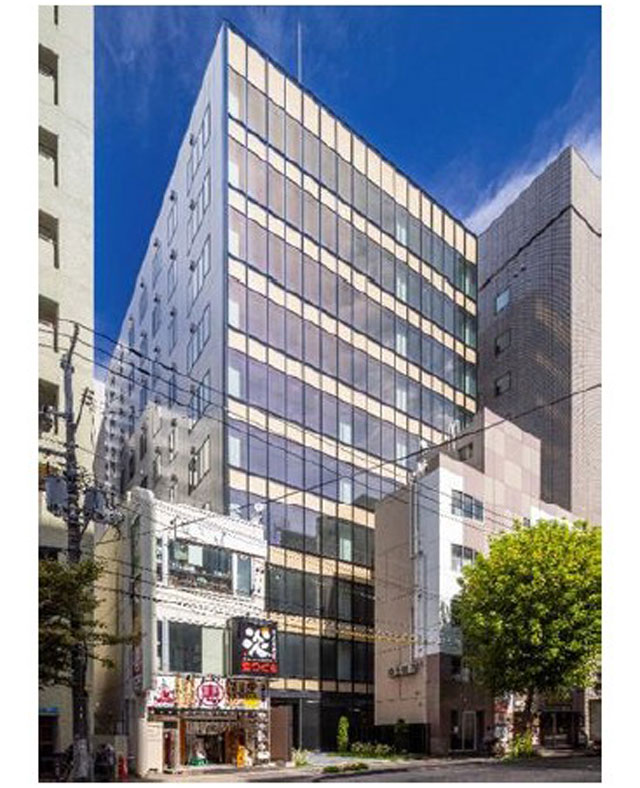





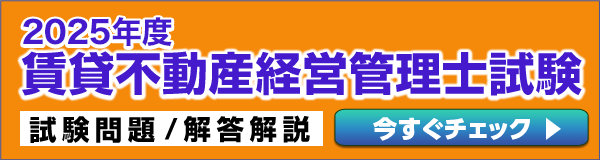
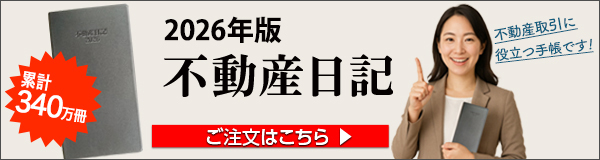





.jpg)



.jpg)

.jpg)
