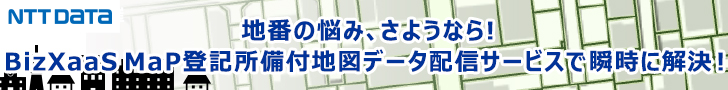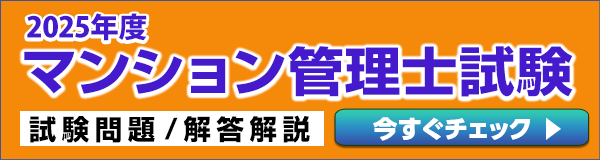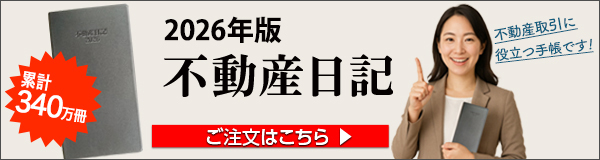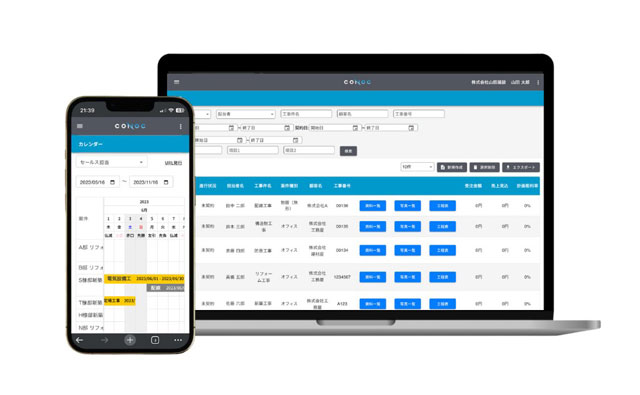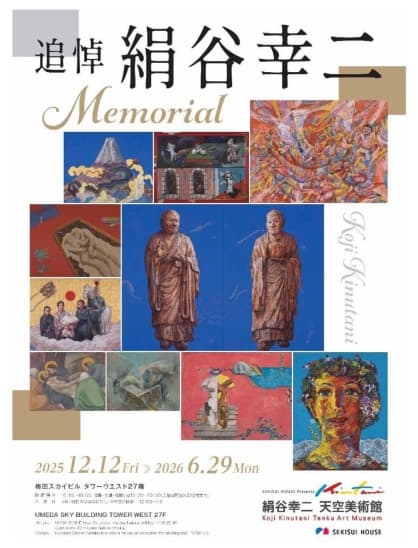「公道か私道かの管理種別と、認定されている道路幅員、道路境界の査定の有無を教えてください。また道路台帳図をいただけますか」
都市計画法、各種条例、建築基準法と来て最後はそれ以外の法令の調査となる。続いて道路課で対象不動産の前面道路の道路法関連の調査を行う。ポイントは「誰が道路管理者でどの範囲を管理しているのか」だ。そのため公道(管理者は公共団体)か私道(管理者は所有者(個人))か、認定幅員(管理している道路の範囲)や、道路境界が確定しているのかを調査していく。なお、道路所有者が個人でもイコール私道ではなく、公道の場合があるから注意が必要だ。特に行き止まりではなく、通り抜けられる道路は「ここは私道ですね」と、公道となっているケースがある。筆者もこれでよく失敗した口だ。所有と管理は別の話なので、道路所有者が個人でも誰が管理者なのかを確認をしておいた方が良いだろう。
管理者が公共団体(公道)の場合、上下水道やガス管の埋設管工事で道路占有の許可はスムーズだが、それ以外(私道)だと原則、道路所有者の道路掘削の承諾書がないと道路占有等の許可が取りづらい。もしくは、埋設管工事ができないこともあるので、注意が必要となる。また、公道だと道路の補修は公共団体で行うが、私道だと原則所有者が費用を出して行うことになる。この辺りも買主に説明が必要となるので管理者が誰なのか、公道か私道かの確認が不可欠と言えるだろう。調査の最後は必ず窓口で道路台帳図等を取得しておこう。
後は対象不動産に関連する法令を各担当課の窓口で確認をしていく。
宅地内で盛土等を行う場合は許可基準を調査するために宅地審査課(盛土規制法)、工場やクリーニング店の跡地なら土壌汚染の有無や対策を調査するために環境課(土壌汚染対策法)、分譲地での売買なら開発許可などを調査するために宅地開発課(都市計画法)、地目が田畑なら売買の際の許可や届出を調査するために農業委員会(農地法)、埋蔵文化財包蔵地かどうか調査するために生涯教育課(文化財保護法)などで調査を行う。
各種法令は専門的な用語が多く、手続きの流れも複雑なので、窓口で説明書面をいただくか、事務所に戻ってホームページから関連書類をダウンロードして確認し、必ず自分自身で買主にどのような制限等がかかるのか理解をしておこう。
こちらで法令上の制限の調査は駆け足だが終わりとなる。
市区町村役場では他に防災課で浸水履歴を、地域自治課で町内会について、河川に隣接するなら河川課で管理幅や深さを調査することになる。やることが多いが、1つ1つ確実に調査をしていこう。
◇ ◆ ◇
【プロフィール】
はたなか・おさむ=不動産コンサルタント/武蔵野不動産相談室(株)代表取締役。2008年より相続や債務に絡んだ不動産コンサルタントとして活動している。全宅連のキャリアパーソン講座、神奈川宅建ビジネススクール、宅建登録実務講習の講師などを務めた。著書には約8万部のロングセラーとなった『不動産の基本を学ぶ』(かんき出版)、『家を売る人買う人の手続きが分かる本』(同)、『不動産業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書』(技術評論社)など7冊。テキストは『全宅連キャリアパーソン講座テキスト』(建築資料研究社)など。