7月の参議院議員選挙では、「外国人への対応」が大きな争点の一つとなった。当初は国民負担軽減策等が主流だったものの、実際の選挙戦では、「外国人に厳しい対応をとるか、共生を重視するか」といった姿勢の違いが注目された。そして、外国人による不動産取得のあり方も関心を集めた論点の一つだ。この点については、不動産業界も当事者の一端として、何らかの見解を定めておく必要があるだろう。少なくとも、「我関せず」では業界に対する社会的信用の面でリスクがある。
とはいえ、「外国人と国内不動産」は以前から議論や懸念のあったテーマであると同時に、選挙の過程で指摘されていた言説には、内容の荒い面も目に付いた。安全保障から不動産価格の高騰、民泊の問題まで、次元の異なる話がひとまとめにされている印象だ。今後、国として何らかの対応を図るのであれば、まずそうした個々の論点の精査から始めるべきだ。
例えば、重要土地等調査法に基づく調査(内閣府24年12月公表)によると、23年度中に外国人・外国系法人が取得した土地・建物は計371件で、土地面積は約3.8万m2。件数の約55%は中国系だった。この実態が、我が国の安全保障にとって憂慮すべき事態かどうか、また注視区域の設定や規制の強度は適切か、そういった部分は大いに議論すべきだろう。
他方、「外国人の投機的購入で住宅が高騰し、日本人が買えなくなっている」という言説も一部にあるが、客観的な根拠は乏しい。率直に言って、土地の希少化や事業コスト上昇など、販売価格高騰の要因に対する解像度が低い。更に言えば、大手不動産開発会社等に取材した限りでは、外国人の存在感自体は小さくなくとも、市場のすみ分けから一般的な実需層向けの物件価格への影響は低い。加えて、国籍に関係なく「投機的取引自体が問題」との指摘もある。
国は一般的なイメージにとらわれず、論点を整理した上で、EBPM(根拠に基づく政策立案)を重視した対応を検討するべきである。そして国民的な関心の高まりを好機とし、あいまいな態度ではなく、外国人による不動産取得の可・不可について明確な基準を示すことが求められている。
とはいえ不動産業界にとっては、顧客との取引制限にもつながるテーマであり、経営への影響に対する懸念は否めない。しかし、「法に触れない限り、外国人に対する事業と利益追求は自由」と開き直るのは、やはり業界全体にとって好ましいとは言えない。土地や建物の取引は、その地域の形を良くも悪くも変える可能性を持つ。業界団体・事業者とも、外国人との取引で生じ得る中長期的リスクにも意識を向けるべきだろう。国の対応を待たず、業界が高いモラルを持ち、「不当な差別は許さず、同時に地域社会の安定にも責任を持つ」という態度を示すことを期待する。


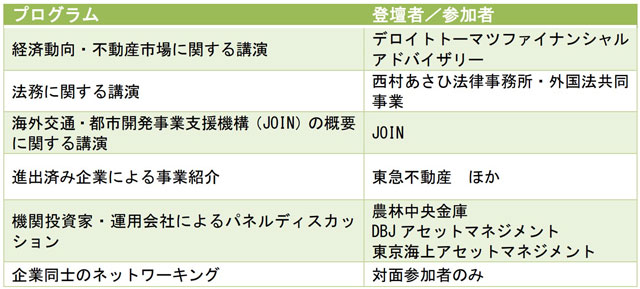




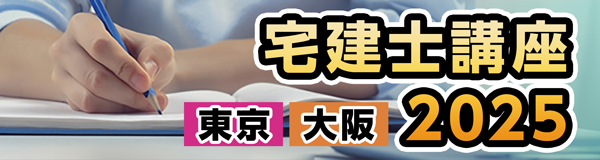
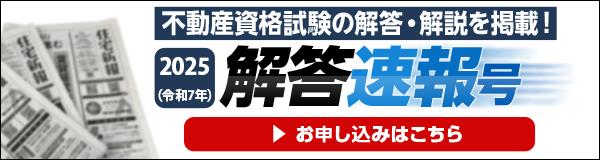






.jpg)


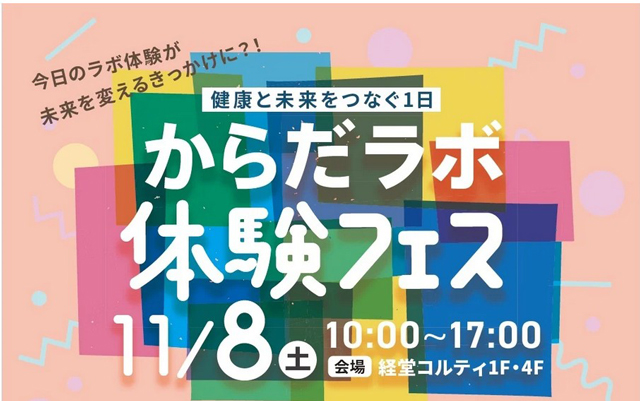
.jpg)
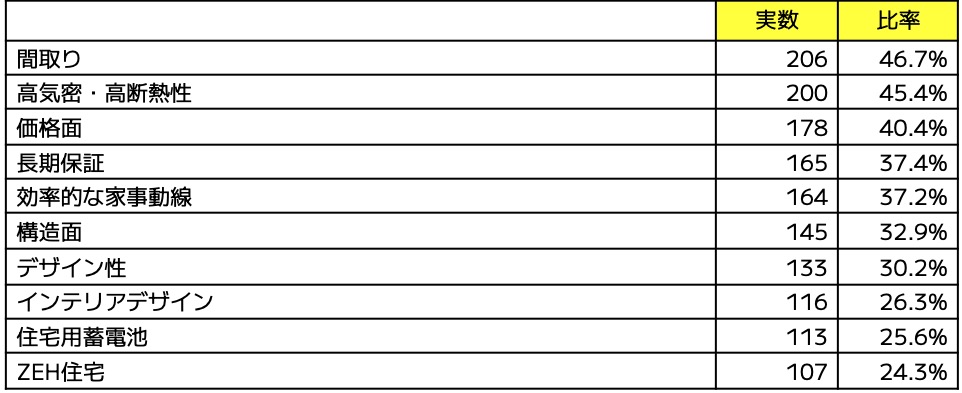
.jpg)
