住まい・暮らし・文化
-

価値創造の源泉 建築と不動産のあいだ 高橋寿太郎 (13)新しい設計者の職域 建築法規をマネジメントする
建築と不動産のあいだに立ったときに見える、建築設計の仕事を取り巻く小さな変化も、年々おぼろげながら輪郭が見えてきました。今年の9月、そうした15組の多様な活動がまとめられた書籍が出版されました。『リノ(続く) -

地域活性化に尽力 積極的にイベント開催 リゾン(埼玉県朝霞市) 和光市 越後山土地区画整理事業 日本不動産学会 田中啓一賞を受賞
住宅新報 11月15日号 お気に入り埼玉県の朝霞、志木、和光、新座の4市で土地の有効利用に伴うビル、賃貸マンション、アパート、駐車場などの賃貸管理から、戸建て分譲まで幅広い事業を展開するリゾン(埼玉県朝霞市)。17年に創業60周年を迎える同(続く) -
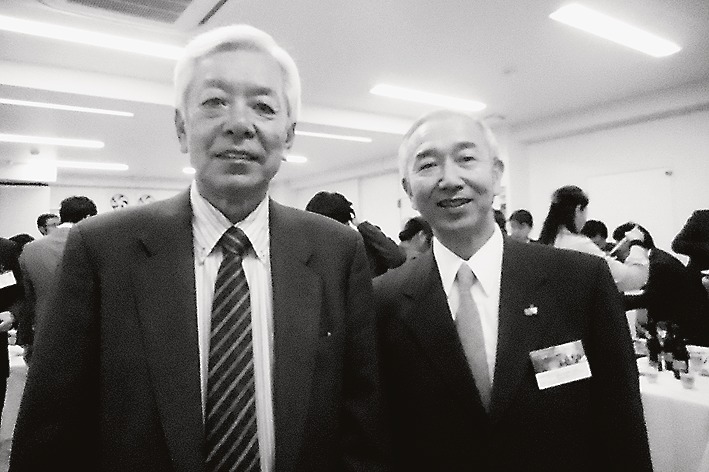
環境省の「省CO2モデル事業」説明 日本シェアハウス協
住宅新報 11月15日号 お気に入り日本シェアハウス協会(山本久雄会長)は11月8日、都内で会員総会を開いた。全国から約60社が参加。6部会(事業者交流、法務研究、女性応援事業開発、事業物件開拓、入居者開拓、新規事業開発)の活動報告に続き、弊紙(続く) -

つながる 人・仕事 ◇3 〝社会インフラ〟になるシェアハウス
住宅新報 11月15日号 お気に入り賃貸住宅を、持ち家を持つまでの〝仮住まい〟ではなく純粋な住まいとして捉えた場合、重要なファクターである「住まいとしての安心感」はどこから生み出されるのだろうか。当然、造り方も住み方も自由度が高い持ち(続く) -

居場所をもとめ 今宵も一献 (39) 北前そば「高田屋八重洲2丁目店」(東京・八重洲) お馴染みの懇親会場に
「FCは店長で選ぶ」と題して、ここで紹介したのが今年3月だった(3月15日号)。FCはどうしてもマニュアル優先で面白みに欠けるが、それだけに店長と店員の個性、人間性が〝隠し味〟にならなければならないと書いた。(続く) -

エネファーム搭載分譲 戸建てが累計1000戸 三井不レジ、東ガス地域で
住宅新報 11月8日号 お気に入り三井不動産レジデンシャルが新築分譲戸建て「ファインコート」シリーズで採用している東京ガスの家庭用燃料電池「エネファーム」を搭載した住宅の累計販売戸数がこのほど、1000戸に到達した。14年3月から東京都、(続く) -

プレハブ協 ゼロ・エネ住宅70%超へ エコアクション見直し 太陽光発電の普及がカギ
住宅新報 11月8日号 お気に入りプレハブ建築協会はこのほど、11年のスタートから5年が経過した「環境行動計画・エコアクション2020」の15年実績および中間時点の計画見直しをまとめた。建築物省エネ法や合法木材利用促進法が新たに成立し、住宅(続く) -

受注回復で増収増益 積水化学・住宅 中間決算
住宅新報 11月8日号 お気に入り積水化学工業・住宅カンパニーの17年3月中間期連結決算は、前期から新築請負の受注回復が続いたことに加え、生産工場効率化の進展により増収営業増益となった。売上高は2377億円(前年同期比1.6%増)、営業利益は171(続く) -

不動産伸び増収増益 旭化成ホームズ 中間決算
住宅新報 11月8日号 お気に入り旭化成ホームズの17年3月中間期連結決算は、宣伝自粛の影響と不動産部門への一部業務移管による建築請負部門の落ち込みを、賃貸管理戸数の増加、マンション分譲などの不動産部門がカバーしたことで、増収営業増益(続く) -

減益も受注好調 パナホーム 中間決算
住宅新報 11月8日号 お気に入りパナホームの17年3月中間期連結決算は、前年同期水準の売上高を確保した一方、人材や拡販施策、販売用地などへの先行投資を積極化したことで減益となった。売上高1623億円(前年同期比0.4%減)、営業利益16億6100万(続く) -

売上総利益率が改善 三井ホーム 中間決算
住宅新報 11月8日号 お気に入り三井ホームの17年3月中間期連結決算は、リフォーム、リニューアル事業が増収となったものの、新築事業の期首受注残高が前期を下回っていたことから、売上高は1068億円(前年同期比1.0%減)の減収となった。また、新(続く) -

高まるインバウンド需要(下) がん健診で来日し不動産投資
住宅新報 11月8日号 お気に入りアンドリュー氏ががんの三大療法と共に、がんの新たな予防や治療の方法として挙げるのが、「免疫細胞療法」や「がん遺伝子治療」などの最先端治療。第4のがん治療といわれる免疫細胞療法は、体内の免疫細胞(NK細胞(続く) -

価値創造の源泉 建築と不動産のあいだ 高橋寿太郎 (12)若い建築家の変化 30年後の問題意識を共有
この数回、建築家の歴史的な視線や、伝統的な仕事の方法、その文化習慣の一片を見てきました。次に最近起きている建築界の動向を紹介したいと思います。そこから不動産業界が学ぶこともあるからです。 日本は(続く)









