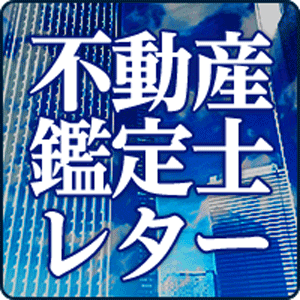(前号からのつづき)
昔、先輩記者に言われた。自分の見方・考え方、推測が正しいかどうかを取材するのがジャーナリストで、世の中に起きていることを可能な限り客観的に伝えるのがリポーターだと。ではその自分の見方・考え方はどこから生まれるのかといえば、リポートを数多くしていれば自然に生まれてくるもので、もしなにも生まれてこないとすれば、それは記者という仕事に向いていないのだと。
◇ ◇
その頃(80年代後半)の私が最も関心を抱いていたのは、「ひとはなぜ住まいを購入するのか」ということだった。当時の私はこう考えていた。マイホーム、マイカーという言葉に象徴されるように、家も車も〝所有する〟こと自体が目的化しているのだと。なぜなら当時は、住まいを選ぶに際して、なぜ住まいを購入するのかを考えるひとは少なくて、だれもが人よりもなるべく早く住まいを持ちたいという空気が社会に満ちていた。
今思うと、そうした解釈もある一面を突いていたと思う。しかし、それだけでは理解できなくなってしまったことが、今起きている。Z世代をはじめとする今の若い世代も「いずれは持ち家に住みたい」という所有志向が約6割に達しているからである。
80年代に家を購入した人たちは、土地は必ず値上がりするので、購入すれば資産形成になるという思惑があったが今はすでにそういう時代ではない。
にもかかわらず持ち家志向が過半を占めているのはなぜか。それは地価が右肩上がりの時代にはなかった〝将来への不安〟が若い世代に蔓延し始めたからだと考える。
若者の75%
カーディフ生命保険の調査(22年9月実施)によれば、最大の将来不安は「老後資金」で20代ではそうした不安を抱く若者が75%にも達している。その理由のトップは「年金でもらえる額が少なくなる」という不安(確信?)である。つまり、確かに地価の右肩上がりはなくなったが、それでも東京の都心や都心近くであれば、ローン返済後はいくばくかの資産形成になるのではないかという計算があるのだと思う。
ただ、今の若い世代の特徴は将来不安に心を悩ませつつも、住宅ローンに縛られることにも抵抗感があり、ライフステージに応じて住み替えるなど今の生活を楽しみたいという思考が大人世代よりも強いということである。
例えばYKKAPが実施した「住まいに関する意識調査」(22年3月実施)によると、Z世代(15~24歳)も持ち家志向は57%と大人世代とあまり変わらないものの、「ライフステージに応じて住み替えを希望するかしないか」の問いについては、大人世代が3対1の割合で希望しない層が多いのに対し、Z世代はほぼ半々となっている。
地価の右肩上がりが期待できないこれからの時代では、ライフステージに応じて持ち家を買い替えての住み替えは現実的ではない。ということは今の若い世代は将来不安から「持ち家志向」をベースとしながらも、一方では賃貸による軽いフットワーク志向も持っているのではないか。少なくともかつての大人世代のように所有すること自体を目的化しているわけではない。
難しくなる選択
つまり、これからの世代の住宅ニーズは複雑化していく。所有か賃貸か、所有するとしてその時期は今かまだ先か。今後勤務先が変わることはあるかないかなど、住まいの選択に関わる要素は複雑化する一方だ。
ここから導き出される結論は、住宅営業はその根底から変わらなければならないということだ。単に不動産を売ったり貸したりするという発想ではなく、顧客の人生設計全体に関わり続け、その時々のライフステージに必要な商品を提供していくというビジネスモデルに変革していかなければならない。
住まいだけでなく保険や投資商品などの相談にも応じる総合サービス業への転身が求められている。