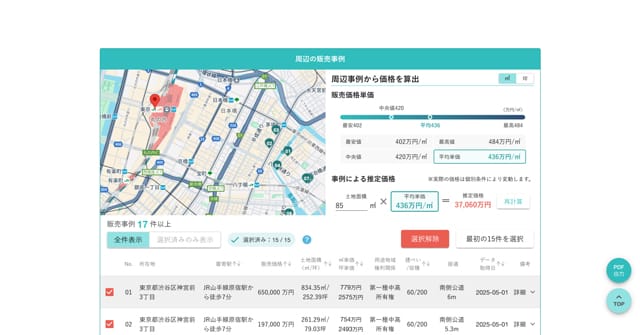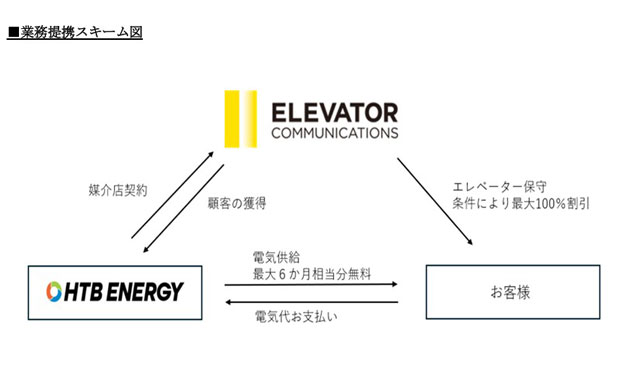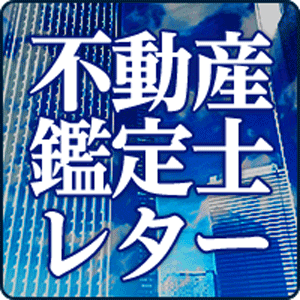マンションの管理問題では建物の老朽化と入居者の高齢化を意味する「二つの老い」という言葉がしばしば使われる。しかし、建物の老朽化が問題であることは分かるが、入居者の高齢化はなぜ〝問題〟なのか。高齢だからといって経済的に弱者とは限らない。不確定要素が多い今の日本社会では、現役世代のほうが経済的困窮者に陥る可能性が高いかもしれない。
◇ ◇
秋の臨時国会で審議入りが見込まれる改正区分所有法では管理組合の集会決議に「出席者による多数決」という仕組みが導入される。例えば共用部分の大規模な変更、管理規約の変更などは現行法では全区分所有者の4分の3以上の賛成が必要だが改正案では集会出席者(委任状含む)の4分の3以上で可能となる。
所有者不明物件(住戸)などへの対応が狙いだが、今後は管理に無関心で総会に参加したこともないような人たちを管理組合が無視し、従来のように参加を促す努力を怠るようになるのではと懸念する声もある。〝無関心派〟を無視する傾向が強まればマンション管理はかえって混迷化していくことにならないか。
マンション管理に詳しい大木祐悟氏は「集会出席者の4分の3以上ということは(定足数は過半)、極論すれば全区分所有者の37.5%(=0.5×0.75)の賛成で決議が出来てしまう」と指摘する。賛成者の数が5割の無関心派よりも少ない。
もちろん、マンションに住む以上、「管理に無関心」という姿勢は本来許されないわけだが、高齢者が気力の衰えから〝関心を失う〟という状況に陥ることを責めることはできない。
それは年を取れば誰にも起こり得ることで、入居者の高齢化が問題になるのはそういうことではないか。これに限らず、長寿化時代のマンション管理には不可抗力といえる問題が多くなることを覚悟しなければならない。
成熟社会の弁え
建物区分所有法は62年前の1962年に施行された。初めての東京オリンピックが開かれる2年前だ。高齢化問題はまだその影すら見えず、人口も経済もすべてが右肩上がりで希望にあふれていた。そうした時代につくられた法律が半世紀を優に超えた今、超高齢化、所有者不明、所得格差、工事費高騰など多くの問題を抱え、あえいでいる。
人も社会も同じで、右肩上がりの若い時代は〝今〟が永遠に続くと思いがちだが、年を経て成熟社会になれば、先行きのことを考えるわきまえが必要になる。当初、区分所有法が想定していたマンションの規模はせいぜい2百戸程度までではなかったか。
それが今は千戸を超えるタワーマンションが出現している。そうした大規模マンションが100年後か、いずれ〝終活期〟を迎えるとき、区分所有法で対応可能なのだろうか。ということもあってか、当初から〝終活〟の方法を決めておく定期借地権マンションが近年見直され始めている感がある。
定借マンションは50年以上の借地契約期間が終了すると借地人側(準共有者)が建物を解体して更地返還するか、建物の保存状況が良いと地主が判断して無償譲渡を受けるかのどちらかとなる。
つまり、一般の分譲マンションが何十年後かは分からないが、建て替えも売却も大規模リノベーションも組合集会で決議できないままスラム化していく危険性をはらんでいるのに対し、定借マンションはその恐れがない。準共有者で組織する管理組合が最後になすべきことが法律に定められているからである。
右肩上がりが終わり、今がこのまま続くという保証のない社会では契約(公正証書)で未来を担保するしかない。 定借は成熟社会を冷徹に、そして豊かに生きる知恵なのかもしれない。事業者は、そうした定借の新たな社会的使命を認識し、定借住宅が更に多くの国民から支持されるよう、真に豊かな住まいとは何かを突き詰め、その商品設計に工夫を凝らす努力を怠ってはならない。