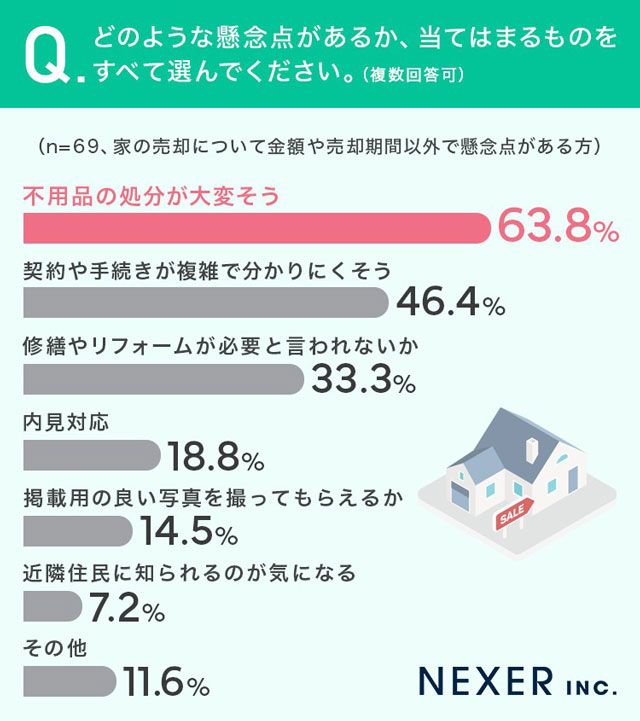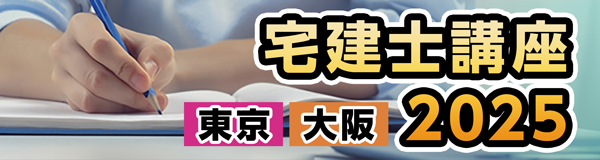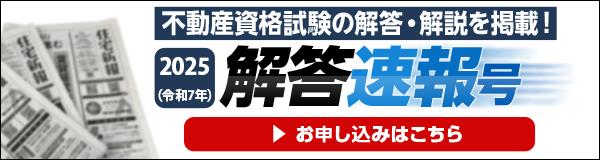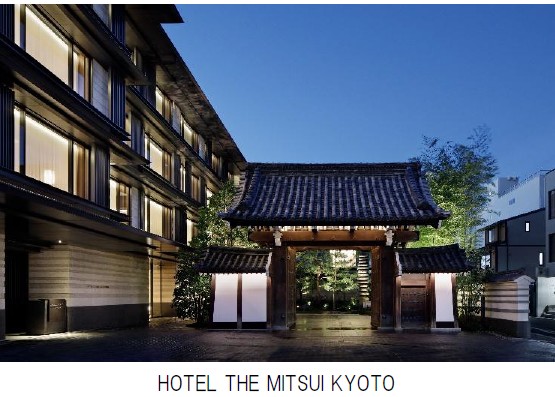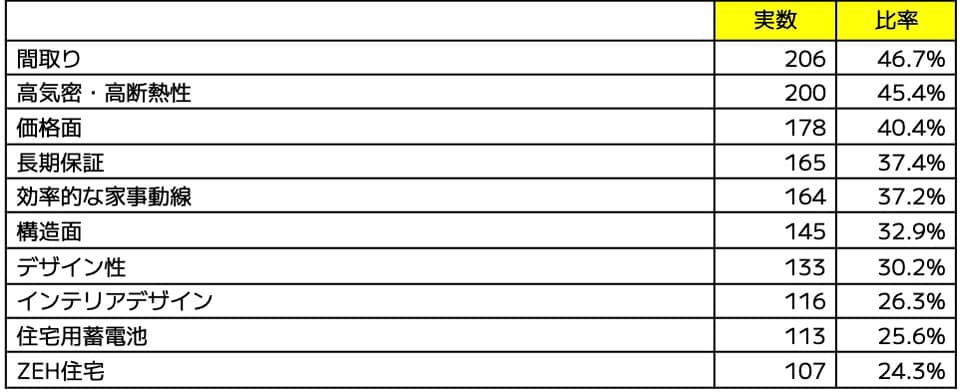少数与党体制による国会運営が始まった。新年度予算案及び各法案の成立へ向け、各党との濃密な議論が求められることとなる。
住宅・不動産業界にとっても、2025年は今後の住宅政策を考える議論の年だ。国交省では昨秋、有識者による「住生活基本計画」の見直し議論が始まった。これは住宅政策の根幹となる10年計画で、おおむね5年に一度の見直しを行うものだ。21年度を初年度とする現行計画では、「社会環境の変化」「居住者・コミュニティ」「住宅ストック・産業」という3つの視点から8つの目標を設定。子育て世帯数の減少や住宅ストック、気候変動及び災害対策、多様な住まい方、DXの進展など住生活に関わる施策を総合的に推進する。同省によれば、成果指標の進ちょくはおおむね順調のようだ。
今回の見直し議論では、昨今の社会経済情勢の変化や居住ニーズの多様化、住生活を支える担い手の確保、生産性向上といった課題と共に、「50年ごろの将来見通しを踏まえる」と、不確定要素の高い未来にも射程を向けた点が特徴的だ。そして、主な論点として、「住まうヒト」「住まうモノ」「住まいを支えるプレーヤー」に着目する。25年度末の改定を目指し、月1回程度の議論を重ねていく。
議論の先に何を見据えるか。重要なのは、改定された計画が住まい領域のステークホルダーを広く巻き込み、住宅政策の実効性を高めていくことだ。従来政策の総括を含めた網羅的な計画では、バランスありきで迫力に欠ける。取り組みの推進力が弱く、現状維持の域を出ないテーマが散見される可能性があるからだ。時代の変化速度と計画策定タイミングがマッチするかも疑問だ。それならば、不確実性が増す時代の指針として、住宅政策を推進する覚悟を盛り込むことに意義があると考える。
当然、覚悟の持ち主が行政だけは意味がない。論点の中で提示された「住まいを支えるプレーヤー」が議論に積極的に関与し、当事者意識を高めることが重要だ。そのためには、現時点の解決策や提言から早急に計画を固めようとせず、柔軟な議論運営に努めなければならない。例えば、新陳代謝を図るため既存の事業領域外のプレーヤーを発掘する。それは、空き家解決のヒントを持つ異業種や就職前の学生、留学中の外国人かもしれない。また、事業者自身が学び直しを通じて、自己変革を図るのも有用だろう。経験値と新領域を掛け合わせ、想定外のシナリオを引き出す。その可能性について、国、業界、事業者それぞれが期待を持ち、国民に発信できる計画となることが重要だ。
議論は、新たな業界像を醸成する創造的な場でもある。住居や住宅政策も、しなやかに変化できるものだと思う。住宅政策の発展に物申すプレーヤーを大いに巻き込み、国民の未来に対する約束事を力強く発信してほしい。