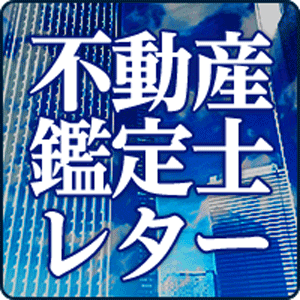大手不動産会社では近年、社内からアイデアを募り、新規事業を発掘しようとする動きが真剣味を増している。もちろんその実現は容易なことではないが、人口減少や単身世帯の増加など社会構造が大きく変化し始めた今、既存の事業だけではいずれ立ち行かなくなることも確かだ。企業として成長していくためには事業の多角化を模索する必要がある。
これまでに実際に立ち上がった事業をみると、「家事代行サービス」、一人暮らしの高齢者が卓上に置いて家族と画面越しに会話できる「タブレット」、コミュニティ運営付きの「職住一体型賃貸レジデンス」など生活ニーズを深掘りしたものが多い。これらは一定の需要はあるものの、マンション分譲などに比べるとニッチな市場でもあり、大企業が本業では参入しにくいという事情もある。しかし今はまだニッチでも10年後、20年後は分からない。介護と仕事の両立に悩んでいる人、一人暮らしの不安を抱えている人、空き家の処分や活用について相談したい人など社会構造変化から生まれる新たな個々のニーズに寄り添うことは大手といえども欠かせない。
注目すべき点がもう一つある。それは会社の風土改革だ。新規事業を生み出そうとする一連の動きが社内を活性化することが分かってきた。選考を重ねる過程、管理職と役員とが議論する過程、あるいはグループ企業からの意見を収集するなどの過程で、社内に新たな風が吹き込む。近年は、会社がイノベーションを促す装置として、オフィス空間に社員同士の雑談や異なる部署間の交流を促すスペースが設けられていることが多い。それと同様に、新規事業創出のためのアイデアを社員から募集し、それを全社態勢で議論することもイノベーションを起こす風土づくりにつながっていく。
また、新規事業創出作業には社員のキャリアアップを促す効果もある。例えば、ある企業では最初の選考をパスして事業化検討段階に進むと、アイデアを提出した社員はそれまで所属していた部署から異動して一定期間、事業化検討作業に専念することになる。その間に得られる様々な知識・体験、イノベーション的思考などは、たとえアイデアが実現に至らなかったとしてもその社員を人間的に大きく成長させることができる。
新規事業創出部門に一定数の専従社員を置くことについて、外野からは「大企業だからできること」との冷ややかな見方もある。しかし会社や当事者らの〝真剣度〟はそうした冷ややかさとは全く異なる。大企業には大企業同士の熾烈な競争がある。そこで勝利するには時間は掛かっても長期的視点で優秀な人材を育成していくことが有効な方法となる。「ヒト・モノ・カネ」は言い古された言葉だが、長期的視点で社員を育成するという「ヒト」重視の姿勢こそ、不透明な時代の今、企業戦略の重要な柱となる。