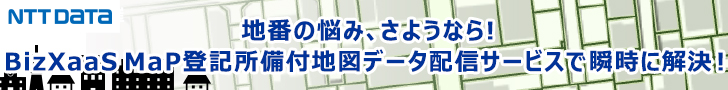総合
-

大阪府大と市立大統合へ 25年、森ノ宮に新キャンパス
住宅新報 2月4日号 お気に入り大阪府と大阪市、公立大学法人大阪の三者は、大阪府立大学と大阪市立大学を統合し、新大学の設置を進めている。19年4月に両大学の設置法人を統合した公立大学法人大阪が発足し、19年8月に「新大学基本構想」を策定(続く) -

改正民法で何が変わる 監修・東京グリーン法律事務所 弁護士 伊豆隆義 ▶(3) 追完請求・代金減額請求
住宅新報 2月4日号 お気に入り旧法では売買の目的物に隠れた欠陥(瑕疵)があった場合、瑕疵担保責任の規定により、損害賠償を請求するか、売買の目的を達することができない場合に契約解除をすることしかできませんでした。 しかし、例えば(続く) -

230人が合格実務経験審査 19年度再開発プランナー試験
住宅新報 2月4日号 お気に入り再開発コーディネーター協会は1月31日、19年度再開発プランナー試験(実務経験審査)の合格発表を行った。合格者は230人。合格者の平均年齢は36.0歳で女性の合格者は44人と昨年度から14人増えた。同試験は筆記試験と(続く) -

501人が合格 19年度ビル経営管理士試験
住宅新報 2月4日号 お気に入り日本ビルヂング経営センターは1月31日、19年12月8日に全国6会場で実施した「ビル経営管理士試験」の合格者発表を行った。受験者673人のうち、合格者は501人(合格率74.4%)だった。受験者は昨年の659人から14人増加(続く) -
東大工学系研究科、長谷工 講堂・ラウンジをリノベ
住宅新報 2月4日号 お気に入り東京大学工学系研究科、長谷工コーポレーションは1月30日、「HASEKO―KUMA HALL」を開設した。築50年の工学部11号館の講堂とラウンジを、長谷工コーポレーションが設計施工を寄付してリノベーション。空間デザイン(続く) -

連携活動インタビュー 東海大学副学長 内田晴久氏 実体験の学びを学生たちに
住宅新報 2月4日号 お気に入り――連携協定を締結。 「超少子高齢化に、不動産をもっと地域の活性化に役立てたいと描く公社と、当大学の山田清志学長が提唱するQOLの向上の理念がうまくマッチした。QOLを東海大学では、いわゆる生活の質でな(続く) -

創立60周年記念式典、盛大に 兵庫宅建 本部・支部が一丸でまい進
住宅新報 2月4日号 お気に入り兵庫県宅地建物取引業協会(松尾信明会長)は1月27日、創立60周年記念式典を盛大に開催した(写真)。会場の神戸市内のホテルには、井戸敏三兵庫県知事や久元喜造神戸市長をはじめ、約300名が出席した。 同協会は(続く) -

各地の新年会
住宅新報 2月4日号 お気に入り頼りになる大阪宅建 阪井一仁・大阪府宅地建物取引業協会会長 17年に策定した「大阪宅建ビジョン」は今年で3年目となる集大成を迎える。10年後の私たちが理想的な姿を実現するため、日頃からすべての会員が意(続く) -

地域が変わるインバウンド 交流人口増加がもたらす恩恵 124 雪は世界に誇る観光資源だ(2) ニセコは世界のスキーリゾート
雪質の良さを世界発信 日本のスキー場の素晴らしさを世界に初めて発信したのが、北海道のニセコだった。00年以降、良質なパウダースノーを求めるオーストラリア人が訪れるようになったのが始まりだ。その後、スキ(続く) -

第3四半期は増収増益 積水化学工業住宅C
住宅新報 2月4日号 お気に入り積水化学工業は1月30日、20年3月期第3四半期決算を発表した。住宅カンパニーでは期初受注残(建物)を生かし、売り上げの平準化が奏功。売上高3702億円(前年同期比3.6%増)、営業利益224億円(同12.0%増)の増収増益。(続く) -

幸福論的 『住宅論』 住宅評論家 本多 信博 77/100 改正意匠法の波紋 住まいが変われば社会が変わる
特許庁の改正意匠法が4月1日施行される(5面記事参照)。不動産としての建築物の外観や内装デザインを知的財産権として保護するのが目的。これが今後住宅・不動産業界に大変革をもたらすのか否か、業界の関心も徐々(続く) -

居酒屋の詩 (84) 久々の宴の苑に香る梅 外の闇より浮かび出でしか
夜遅くから東京も大雪になると見られていた1月27日、我が新聞部の新年会が開かれた。冷たい雨が降りそそぐ中、虎ノ門ヒルズ近くの「厨」に集結。昔と比べると、同じ部署仲間による飲み会が随分と少なくなったよう(続く) -

残したい情景~文化的歴史的所産を巡る~ 第38回 鳥取県 日野町 一般財団法人 日本不動産研究所 「たたら製鉄」が礎の根雨地区 癒やされる情景を後世に
鳥取県南西部に位置する日野町は、昭和34年の人口約9000人をピークに減少し、現在は約3000人である。少子・高齢化、過疎化が進行する林業中心の山間部の町で、根雨地区は、官公署その他店舗の集積する日野町の中心(続く)