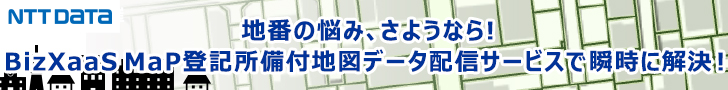住まい・暮らし・文化
-

寮跡地に低層マンション 旭化成不レジ 最多1億円台
住宅新報 1月22日号 お気に入り旭化成不動産レジデンス(東京都千代田区、池谷義明社長)は1月12日から、東京都杉並区荻窪3丁目で販売する分譲マンション「アトラス荻窪大田黒公園」のモデルルーム事前案内会を開始した。同マンションは旭化成の社(続く) -

加盟店100カ店に子育て世代から高い支持 ジブンハウス
住宅新報 1月22日号 お気に入り住宅購入サイトの運営や住宅チェーン事業を展開するジブンハウス(東京都港区、内堀孝史社長)は昨年12月、規格住宅販売のFC(フランチャイズチェーン)・VC(ボランタリーチェーン)加盟店で100カ店を達成。1月11日時点(続く) -

業界各社トップ 年頭訓示 新たな時代の幕開けに
住宅新報 1月15日号 お気に入り住まい手の幸せ追求 仲井嘉浩・積水ハウス社長 当社グループは第4次中期経営計画の基本方針に基づく3つのチャレンジでロケット成長を目指している。 1つ目は、コア事業である戸建て住宅事業における新ビ(続く) -

米国企業の株式追加取得 住友林業 豪州と合わせ1万戸視野に
住宅新報 1月15日号 お気に入り住友林業は1月2日、米国の全額出資子会社Sumitomo Forestry America,Inc.(米国ワシントン州ベルビュー市)を通じてDan Ryan Buildersグループの持ち株会社であるDRB Enterprises,LLC(DRBE社、米国メリーランド州フ(続く) -

ダイキンと東大が〝協創〟 空気の価値化で技術創出へ
住宅新報 1月1日号 お気に入りダイキン工業(大阪市北区)と東京大学は昨年12月17日、共同研究や人材交流などを推進する包括的な「産学協創協定」を締結した。東大の五神真総長は「包括総合的な分野をカバーする東大と、一点突破で集中しているダ(続く) -

リノベーションが好調シャッター事業に手応え YKKAP
住宅新報 1月1日号 お気に入りYKKAP(東京都千代田区、堀秀充社長)は昨年12月21日、本社で記者懇談会を開き、18年度の活動状況を説明した。 18年度の業績(国内外の合計)では、売上高を4318億円(前年比103%、計画比96%)と推計。営業利益は223億(続く) -

ウッドステーション 木造パネル住宅の施工公開 早大と国産材の供給研究も
住宅新報 1月1日号 お気に入りウッドステーション(以下WS、千葉市美浜区、塩地博文社長)と早稲田大学創造理工学部は昨年12月15、16日、早大西早稲田キャンパス(東京都新宿区)の中庭で大型木造パネル工法住宅の施工公開を実施した。来場者は両日(続く) -

住友林業 新3DCADを開発 光にこだわり高画質追求
住宅新報 1月1日号 お気に入り住友林業はエンターテインメント業界を中心にデジタルコンテンツ関連ビジネスを展開するシリコンスタジオ(東京都渋谷区、梶谷眞一郎社長)と共同で、3次元住宅プレゼンテーションシステム(3DCAD)を開発した。昨年12(続く) -

米国で住宅事業進出 ミサワ
住宅新報 1月1日号 お気に入りミサワホームは1月に完全子会社のミサワホームアメリカを通じて、米国テキサス州で住宅の建設、販売を手掛けるインプレッションホーム社(IH社)の株式51%を取得し、米国での住宅事業に進出する。 IH社はテキサス(続く) -

賃貸住宅で新商品 東建コーポ
住宅新報 1月1日号 お気に入り東建コーポレーション(名古屋市中区、左右田稔社長)は昨年12月17日、高耐震鉄骨造の賃貸住宅「シェルル ユーロピュア」(写真)を発売した。 外観は「伝統と現代の融合」をコンセプトに、建物全体を美し(続く) -

凸版印刷 伝言・情報を表示する壁材開発 IoT建材で100億円目指す
住宅新報 12月25日号 お気に入り凸版印刷(東京都千代田区、金子眞吾社長)は12月12日、東京ビッグサイトで開催された展示会「住宅・ビル・施設Week2018」で、ディスプレーと化粧シートを組み合わせた壁材「インフォウォール」、体組成計と床材を組(続く) -

建築費用は平均2807万円 リクルート住まいC 注文住宅トレンド調査
住宅新報 12月25日号 お気に入りリクルート住まいカンパニー(東京都港区、淺野健社長)は12月4日、18年注文住宅動向・トレンド調査を実施し、その結果を発表した。調査対象は1年以内に一戸建て(新築・建て替え注文住宅)を竣工した建築者、今後2年(続く) -

北欧の幸福な暮らし提案 スウェーデンH 駒沢にモデルハウス
住宅新報 12月25日号 お気に入りスウェーデンハウス(東京都世田谷区、岡田正人社長)は12月24日、東京都世田谷区駒沢の駒沢公園ハウジングギャラリー内にモデルハウスをオープンした。建物の概要は構造が木質パネル工法の2階建て。延べ床面積が233(続く)