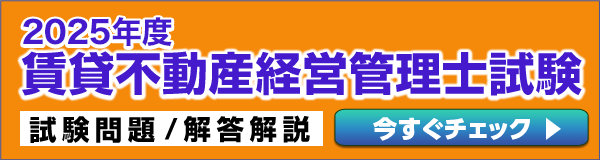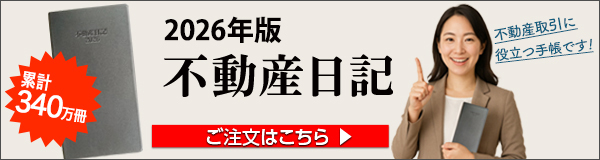不動産取引現場での意外な誤解 記事一覧
-
不動産現場での意外な誤解 売買編142 旧民法下の「家」はどのようにして設立されたか?
Q 前回は、旧民法下における「家」の制度の骨格部分についての話がありましたが、その家の制度と戸籍法との関係を知りたいのですが。 A 家の制度は、旧民法にその主要部分の規定があり、その家の制度を手続的(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編141 旧民法時代の「家制度」とはどのような制度か
Q 以前の〔売買編〕の最後に、旧民法時代の「家」の制度がどのようなものであったかを知ることは、所有者不明土地における所有者の探索の上でも非常に重要だということが書かれてありました。 A その通りです(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編140 改正民法605条の3はどういう趣旨の規定か
Q 改正民法605条の3の「合意による不動産の賃貸人たる地位の移転」という見出しの規定は、その前の605条の2の「不動産の賃貸人たる地位の移転」という見出しの規定と関連があるように思えるのですが、条文だけを(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編138 貸ビルの購入者は滞納賃料の請求ができるか?
Q 前回、貸ビルの売買に伴う賃貸借契約の承継についての話がありましたが、そのビルの借主に賃料滞納者がいた場合、その滞納賃料債権が新所有者に引き継がれるのでしょうか。 A 当然には引き継がれません。(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編137 貸ビルの売却前の明け渡し合意は承継される?
Q 貸ビルの売買で案外多いのは、貸ビルが古いために建て替えが必要だということで、売主側が買主に対し、「入居者は、すでに次の契約更新時までに建物を明け渡すことを条件に賃料の減額に応じている」として、あ(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編136 店舗の借主が死亡したら契約はどうなるか?
Q 店舗の賃貸借で借主が死亡した場合、契約関係はどうなるのでしょうか。 A 借主が死亡したということは、個人ということですから、その店舗の賃借権は相続の対象になります。したがって、相続人が複数であれ(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編135 貸ビルの売買で既存の看板は撤去できるか?
Q 業務用ビルの賃貸仲介の常識として知っておきたいのですが、貸主には借主に対し、建物の外壁に看板を設置させる義務があるのでしょうか。 A 義務まではありませんが、借主からの要求があれば、ビルの品位を(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編134 商業ビルで途中の業種変更を禁止できるか?
Q 賃貸物件が商業ビルのような場合に、テナントの「目的外使用」ということで問題になることもあるのではないでしょうか。 A あります。建物の「目的外使用」については、複合ビルの場合に多く問題になります(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編133 大家が勝手に貸すと言ったが、断れるか?
Q 当社は、先日A業者から、大家が勝手に借主と次のようなやりとりをしてしまったために、契約の締結を断れずに困っているという相談を受けました。その理由は、仲介業者であるA業者の所に、既に先客が申込みをし(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編132 通常の賃貸借では面積不足の責任は生じない?
Q 前回の賃貸借編の記述を読んでいると、通常の建物賃貸借契約においては、面積に多少の誤差があっても貸主は契約不適合責任を負わないように感じているのですが、そういう理解でよいのでしょうか。 A 必ずし(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編131 建物の数量指示賃貸借というのはあるのか?
Q 建物賃貸借契約締結後、実際の面積と契約書の面積に誤差があった場合にトラブルになるケースがありますが、賃貸借契約の場合にも「数量指示賃貸借」というのはあるのでしょうか。 A あります。そういう賃貸(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編140 超長期相続登記未了土地の所有者を知るには?
Q 以前の〔売買編132回〕の記述の中に、明治30年から一度も相続登記がされていない土地のことが出ていましたが、なぜ登記がされなかったのでしょうか。 A その理由は、以前にもお話した通り、相続人側の事情か(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編139 抵当権も20年で消滅時効にかかる?
Q 以前(売買編第122回)、判例は、賃借権の時効取得を認めているという記述がありましたが、どうも納得がいかないのですが。 A それについては、賃借権は賃料の支払先がどうなっているのかという問題があるので(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編138 所有権放棄制度の対象となり得る土地は?
Q 前回までで、所有者不明土地における土地活用の重要ポイントは、公共事業と地域福利増進事業だと分かりました。 A そのために、特措法が土地収用の手続を合理化し、補償金についての従来の収用委員会裁定を(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編137 特措法38条の家裁への申立権の適用範囲は?
Q 相続財産管理人制度について、民法951条が「相続人のあることが明らかでないときはその財産を法人として扱う」としていますが、これはどういう意味でしょうか。 A この制度は、相続人がいるかいないか分から(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編136 所有者不明土地の収用は誰が決めるのか?
Q 前々回で、相続財産管理人制度は民間事業者も利用できる可能性があるということでしたが、それは民間事業者が、所有者不明土地で地域福利増進事業を行う場合の話ですよね。 A その通りです。民間事業者が、(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編135 戸籍を見れば相続関係がすべて分かるか?
Q 所有者不明土地においては、相続財産管理人制度(民法951条以下)や不在者財産管理人制度(民法25条)を利用し、相続人を探索することができるということですが、この制度を利用するときの両者の違いがよくわかりま(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編134 相続財産管理人制度は民間事業者も利用できる?
Q 前回出ていた相続財産管理人制度(民法951条以下、特措法38条)は、その制度利用を国や地方公共団体に限定せずに、「特定所有者不明土地」において民間業者が行う地域福利増進事業(特措法6条以下)の際にも利用で(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編133 相続人が判明しない場合の最後の手段は?
Q 前回のこのコーナーの記述によると、所有者不明土地に関する特措法の「所有者不明土地」は、所有者がいることは分かっているが、何人いるかが分からない土地も含まれるようですが、それでよいのですね。 A (続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編132 相続人が全員分からなくても相続登記は可能か?
Q 前回、所有者不明土地と「空き家」は関係あるということで、さいたま市内の空き家が紹介されていましたが、その空き家の土地は、本当に特措法でいう「所有者不明土地」になるのでしょうか。 A その空き家の(続く)