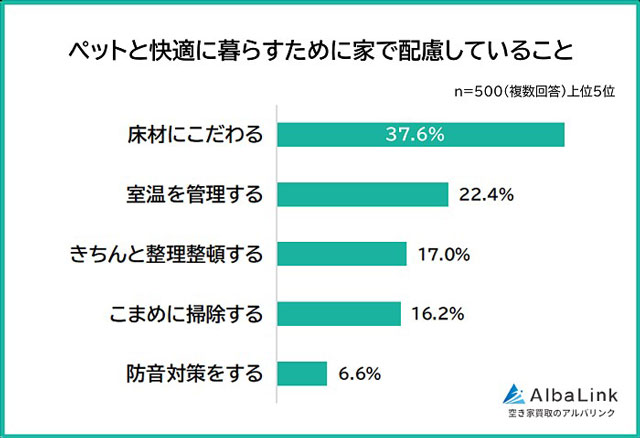不動産取引現場での意外な誤解 記事一覧
-
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編243 建物賃貸借契約で手付の交付は必要なのか?
Q.前回(第242回)、やはり建物賃貸借契約では「契約書の持ち回り」による契約締結方法には問題があると思いました。 A.確かに問題がないとは言えません。しかし、かと言って慣行的に行われている契約方法をやめる(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編242 賃貸での契約書の持ち回りは問題がないのか?
Q.前回(第241回)、建物賃貸借契約の仲介をする場合、「契約書の持ち回り」で契約を締結することが多いとありましたが、そのような契約方式は問題がないのでしょうか。 A.問題がないとは言えませんが、そのような(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編241 賃貸借契約で手付が交付されることはあるか?
Q.前回の賃貸編(7月22日号)の、建物賃貸借契約で「借主が手付を支払っても、契約書が作成されなければ契約は成立しない」との東京地裁の判例には驚きました。 A.確かに、賃貸借契約は「諾成契約」ですから、法律(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 売買編250 仲介業者に仲介責任が生じないケースはある?
Q.前回は、業者売主の物件を仲介した際、仲介業者が間違った重要事項説明をした責任が両業者の共同責任になるとのことでした。 A.はい。その場合の両当事者には、買主に対しそれぞれ業法35条の重要事項説明義務と(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 売買編249 業者売主物件の重説を仲介業者が間違えたら?
Q.宅建業者が自社物件を売る際に他の業者に仲介依頼をすることがありますが、仲介業者が買主に対し間違った重要事項説明をし損害を与えた場合、その責任はどうなりますか。 A.その場合、間違った説明をした仲介業(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 売買編248 業者売主の場合の違約金は常に代金の20%?
Q.今回は、業法39条の「手付の額の制限等」の規定についてです。この規定では、宅建業者が売主になっている場合の手付金の額は売買代金の「20%以下」でなければならないとされていますが、それはなぜですか。 A.(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 売買編247 いわゆる「手付なし契約」は業法違反か?
Q.前回、一般の個人が売主になっている物件の仲介においても、仲介業者の関与の仕方いかんによっては業法47条3号の手付に関する信用供与の禁止規定に抵触する可能性があるとのことでしたが、そのような場合の売買契(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 売買編246 手付に関する信用供与禁止規定の対象者は誰?
Q.宅建業法47条は、「業務に関する禁止事項」の第3号に手付に関する信用供与の禁止規定を定めています。この規定は、具体的にはどのような行為を禁止しているのでしょうか。 A.国土交通省のガイドラインによれば(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 売買編245 売買予約後の取得土地の転売はなぜ許される?
Q.前回は、宅建業者が開発許可取得条件付きで土地を購入し、それをそのまま転売することは、その条件が「停止条件」であることから、宅建業法33条の2第1号の規定により、原則としてできないということでした。 A.そ(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 売買編243 個人施行の公的開発事業にも開発許可が必要か?
Q.土地区画整理事業と市街地再開発事業の話が続きましたが、これらはいずれも「個人施行」のものもあるということでした。 A.その通りです。この2つの事業は、個人施行のものも含めて、いずれも都市計画事業とし(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 売買編242 土地区画整理事業と市街地再開発事業の違いは?
Q.前回の土地区画整理事業の説明の中に、その事業が健全なまちづくり・都市づくりのための事業であるとありましたが、それは本来、国や地方自治体が行う事業ではありませんか。 A.基本的にはその通りです。ただし(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 売買編241 土地区画整理事業とはどういう事業か?
Q.売買編240回(5月13日号)にあった土地区画整理事業とはどういうものでしょう。 A.雑多な土地を統合し、その中に道路や公園などの公共施設を整備し、健全なまちづくり・都市づくりを行うための計画的な宅地造成事(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編240 契約は手付が支払われても成立しない?
Q.建物賃貸借契約では、通常連帯保証人を立てることが前提です。このような場合、契約後に借主が連帯保証人を立てられなくなったら、契約はどうなりますか。 A.契約は成立するが、借主には連帯保証人を立てる義務(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編239 借地権が譲渡(売買)されたら敷金はどうなる?
Q.借地権付建物売買の話が続きましたが、今回は、借地権が譲渡された場合の「敷金」の承継問題です。 A.借地権(賃借権)の譲渡は、賃貸人の承諾さえあれば可能ですが(民法612条(1))、その場合、従来の借地契約の内(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編238 借地権譲渡の承諾に地主の実印は必要か?
Q.前回(第237回)の最高裁判例では、借地権付建物売買において、土地に欠陥があった場合、その土地についての契約不適合責任(従来の「瑕疵担保責任」)の追及を、必ずしも否定していないように見えます。 A.はい。(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編237 借地権付建物売買での土地の欠陥は誰の責任?
Q.前回、借地契約における土地の借主の土地に対する修繕権限の行使に触れましたが、借地人が地主の承諾を得て、借地権を建物と一緒に第三者に譲渡した際の土地の欠陥についての責任はいかがでしょう。 A.1991(平(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編236 借地人は土地の欠陥について修繕ができるか?
Q.賃貸編第223回では、建物賃貸借契約における借主からの修繕権限の行使について言及していました。この借主からの修繕権限の行使とは、土地の賃貸借の場合にも適用があるのでしょうか。 A.当然あります(民法607(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編235 借地で増改築禁止特約がなければ増改築は自由?
Q.旧借地法時代から続く借地契約には増改築禁止特約が定められていないものもあるそうですが、このような土地は増改築が自由にできますか。 A.原則的には自由にできます。その借地上の建物は借地人の「所有物」だ(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編234 借地条件の変更が裁判所に認められるには?
Q.前回(第233回)、当事者間で定めた契約条件に合わない建築物でも、裁判所に借地条件の変更を申し立てることにより、建築が可能になるとありました。 A.はい(借地借家法17条)。ただし、裁判所が借地条件の変更を(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編233 借地契約では約定違反の建築物も建てられる?
Q.前回は、借地権付分譲マンションの地代の滞納問題でしたが、最近は新たな借地契約の締結があまりなく、土地の賃貸借についての知識が希薄になりそうです。 A.確かに新たな土地の賃貸借はあまり聞きませんが、今(続く)