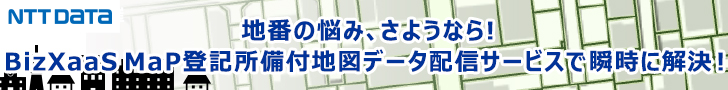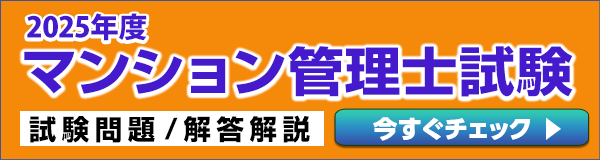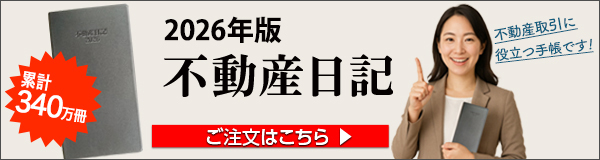不動産取引現場での意外な誤解 記事一覧
-
不動産現場での意外な誤解 売買編189 未完成物件の契約締結制限は賃貸も含まれる?
Q 不動産の「青田売り」をするには、事前に建築確認等の手続きを経なければなりませんが、このような契約の締結が制限されるのは、売買と交換の場合だけで、「賃貸借」の場合には制限を受けないと聞きます。それ(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編188 他人物売買物件仕入れ時の手付後払い契約は可能?
Q 当社は、ある会社と他人物を仕入れて転売する契約を締結することになっていますが、資金繰りの関係で、その他人物を仕入れる際の手付金を転売時の手付金で支払うことを考えています。このような契約は、法的に(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編187 告知義務と守秘義務はどちらが優先する?
Q 宅建業者間でよく話題になるのは、自殺物件の取り扱いです。このような物件の売買の場合、仲介業者はその自殺の事実を買主に告知すべきなのでしょうか。 A 一般論としては、その事実は業法47条1号の「重(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編186 宅建業者間の取引では重要事項の説明は必要ない?
Q 業法の規定の中には、宅地建物取引宅建業者間の取引には適用されないという条項があるそうですが、それは何条に規定されているのですか。 A 78条(2)に規定されています。その規定は、宅建業者間の取引に(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編185 35条の重要事項と47条の禁止事項はどう違う?
Q 宅建業法上の重要事項というのは、同法35条のものばかりでなく、47条1号の「重要な事項」も重要事項だという人がいますが、その意見は正しいのでしょうか。 A 正しいと思います。 Q すると、35条違(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編184 重説義務違反は「過失」でも処分の対象になる?
Q 宅建業者がいつも心配しているのは、自社の社員が重要事項の説明を「うっかり」しなかったときも処分の対象になるのかということです。 A それは、内容のいかんによると思います。いかに重要事項といえど(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編183 借地権付建物売買の仲介報酬に上限はあるか?
Q このたび借地権付きの建物の売買を仲介するのですが、借地権(土地賃借権)については、地主がその譲渡承諾の対価として承諾料を要求しています。こうした場合に、その対価(承諾料)の額を基準にした仲介報酬を請(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編182 令和3年の民法改正で業務上最も身近な問題は?
Q 今回は、業務上最も身近な問題としての法改正の話をうかがいます。 A 今回も、所有者不明土地関連から始めます。例えば宅建業者が、これから郊外部や地方部でマンション分譲事業を行うための用地を買収す(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編180 賃貸物件を現状で競落する場合の注意点は?
Q 賃借権の対抗要件(物件の引渡し:借地借家法31条)を備えた借主が入居している賃貸物件を売買した場合、その物件の買主(新所有者)が新貸主になるという改正民法が既に施行されています(民法605条の2)が、この規定(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編179 借家人が死亡した場合の賃借権相続の行方は?
Q 前回は、借家人が離婚した場合の妻の財産分与による賃借権の承継問題が取り上げられていましたが、今回は、借家人の死亡による賃借権の相続問題をお聞きします。まず最初に、賃借権相続の一般的な話からお願い(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編178 妻は離婚後も借家に住み続けられるのか?
Q よくある話として、アパート住まいの夫婦が離婚した場合に、妻は生活のためにそのまま住み続けたいと希望し、夫のほうはアパートを出ていくのがほとんどです。そのような場合に、妻はそのままアパートに住み続(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編177 更新料の支払いを拒否したらどうなるか?
Q 建物賃貸借契約においては、通常契約期間を2~3年程度にし、その期間満了と同時に契約を更新するのですが、賃料改定が難しい昨今では、あらかじめ一定の更新料の支払いを約定し、それに代える方法がとられてい(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編176 依頼のない賃貸仲介でも報酬は請求できるか?
Q 不動産取引においては、それが売買であれ賃貸借であれ、宅地建物取引業者の仲介によって契約が成立すれば、その契約成立と同時に仲介報酬請求権が発生し、依頼者は仲介業者に対し約定の報酬額を支払わなければ(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編175 賃貸仲介で宅建業法上の説明以外に説明義務は?
Q 賃貸物件を仲介する場合の重要事項説明については、宅建業法35条に規定があり、その具体的な内容は同条1項に説明項目が列挙されておりますが、その1項には「少なくとも」と規定されているため、その範囲がどこ(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編174 ガレージ部分のある立体駐車場は建物か?
Q 前回、戸建ての店舗であっても、1階と2階が構造上独立している場合には、2つの建物として別々に賃貸借契約が締結できると書いてありました。このように、建物の一部であっても、賃貸借契約の対象になるという考(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編173 2階が独立住居になっている店舗の貸し方は?
Q 店舗の賃貸借において、その建物が戸建ての場合、2階部分を独立した住居として貸せる場合があります。しかし、このような場合においても、通常は2階部分を店舗と一体で借主の住居あるいは倉庫・事務所等として(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編172 老朽建物の賃貸時の修繕特約のポイントは?
Q 前回掲載された、老朽建物の賃貸借に関する貸主の修繕義務に関する判例を読むと、基本的には、貸主には賃料に見合うだけの修繕義務しかないと言っているように見えますが。 A 基本的にはその通りです。した(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編171 老朽建物の修繕義務はどのように判断される?
Q 以前に掲載された〔賃貸借編第158回〕の記述の中に宅地建物取引業者が古い建物の賃貸借を仲介する場合の注意点として、建物の修繕義務に関する基本的な考え方は、「修繕をしなければ、建物を用法に従って使用す(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編180 敷延部分を隣人と共同利用したら私道になる?
Q 宅建業者は、敷地延長物件(以下「敷延物件」という。)を取り扱うことがありますが、中には、その敷延部分の間口が2メートルに満たないため、その不足分を隣地所有者から借地したり購入したりして建築基準法43条(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編179 袋地の位置指定道路は全部を通行できない?
Q 前回、公道から公道に通り抜けできる位置指定道路であれば、他人の道路(私道)であっても、原則として第三者が通行できるが、そうでなければ通行は認められないということでした。 A その通りです。なぜなら(続く)