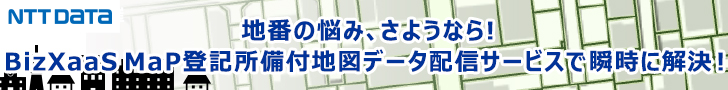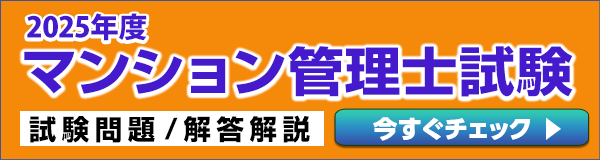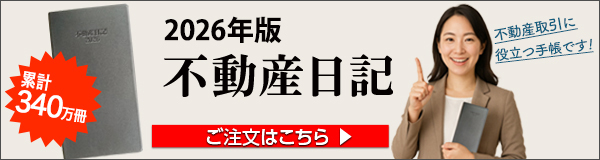不動産取引現場での意外な誤解 記事一覧
-
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編194 敷金返還請求権は譲渡制限付でも譲渡できる?
Q.店舗などの賃貸借の場合には、多額の敷金を差し入れていることが多いことから、借主が賃貸借契約の存続中に、敷金について譲渡制限特約付であるにもかかわらず、その返還請求権を第三者に譲渡することがあります。(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編193 極度額以外に保証人を保護するための規定は?
Q.前回の話ですと、賃貸借契約における保証契約締結後の増額賃料が保証の対象になるかどうかは、原則的には対象になるとしつつ、当事者の合意内容や信義則に照らし、判断することによって、結論が異なるとのことでし(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編192 民法448条(2)の規定は最高裁判例に反する?
Q.賃貸借の保証では、賃料が増額改定された場合、増額分も保証人が保証しなければならないのか、いつも疑問です。この点について、改正民法で新しい規定はありますか。 A.はい。保証契約全般の規定として、「主た(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編191 貸借契約の保証人が死亡したらどうなる?
Q.建物賃貸借の保証人が死亡した場合、保証契約はどうなりますか。 A.保証人の相続人が相続を放棄しない限り、相続人に保証人の地位が移転します(民法920条、925条、最判平成9年11月13日)。したがって、死亡まで(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編200 数量指示売買での面積超過は代金増額できる?
Q.数量指示売買による不動産取引で、その面積が表示された面積より超過していた場合には、その超過分は、当然に代金の増額請求ができますよね。 A.当然に請求できるかどうかは、その契約における数量指示売買の解(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編194 他人物売買での仕入の契約は履行の着手か?
Q.私達宅建業者は、種々のユーザーから用地の取得を委託されることがありますが、条件によっては用地取得の目処が立った段階で委託者と売買契約(転売契約)を締結することがあります。いわゆる他人物売買契約です(民(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編193 個人間売買での高額違約金設定は自由?
Q.前々回、違約手付との関係で、手付の額以上の違約金を定めることができると書いてありました。 A.その通りです。その場合は、当事者が「違約手付」を定めたのではなく、違約の場合の「損害賠償額の予定」として(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編192 代金の1%の手付金でも解約手付性を有する?
Q.前回、手付金には、解約手付であることを契約書に明記しておかなくても、当然に解約手付性を有するとのことでしたが、手付解除の場合には、その手付金が自動的に相手方への損害賠償の予定額になるということです(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編191 手付には違約手付としての性質も含まれる?
Q 私達宅建業者が日常使っている売買契約書には、手付金が解約手付として定められていますが、その手付金には違約手付としての性質もあるのでしょうか。 A それは契約書を見てみなければ分かりませんが、違(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編190 保証人には建物の明け渡しの助力義務があるか?
Q 当社は、昨年借主が勤務している会社の社長(個人)を保証人にして建物賃貸借契約を締結したのですが、この借主がよく賃料を滞納するので、保証人から、「これ以上の滞納が続くようであれば、建物の明け渡し(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編189 概括的クリーニング特約は無条件で有効か?
Q 前回は、敷金精算に伴うトラブルの解決法の話でしたが、今回は、そのトラブルのもとになる明け渡し時の原状回復義務についてうかがいます。 たとえば、賃貸借契約書に「明け渡しの際には、原状回復費用として(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編188 敷金返還トラブルで「少額訴訟」は有効か?
Q 建物賃貸借契約では、明け渡し時の敷金精算トラブルになることが少なくありません。これは、住宅の場合も店舗の場合も同じだと思いますが、いかがでしょうか。 A 住宅の場合、国交省が原状回復についての(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編187 築80年の建物であれば明け渡しが認められる?
Q 以前にもこの〔賃貸借編〕の相談事例として「老朽建物」の明け渡し問題が取り上げられていましたが、その結論としては、建物が単に「老朽化」しているということだけでは裁判所は明け渡しを認めないということ(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編186 賃貸で「使用損害金」を定めなかったらどうなる?
Q 宅建業者が日常使っている賃貸借契約書には、借主が約け定通りの明渡しをしなかったときは、貸主に対し「使用損害金」を支払うよう定められていることが多いのですが、そもそもこの使用損害金というのは、どう(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編185 賃料の仮差押以外に賃料から回収する方策は?
Q 前回は、貸主の債権者が、その貸主の有する賃料債権を仮差押えして債権を回収する方法が紹介されていましたが、その方法は、いわゆる無担保債権者が債権回収をする場合の方法でした。 今回は、その債権者(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編184 借主が支払う賃料債権が仮差押えされたら?
Q 前回は、賃貸管理会社が賃料の代理受領をしている場合の代理権の特殊性についての話でしたが、今回は、その借主が支払うべき賃料債権が貸主の債権者から仮差押えされた場合の対応についてうかがいます。 (続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編183 管理会社が行っている賃料の代理受領とは?
Q 当社は、賃貸仲介と賃貸管理の2つの仕事をしていますので、時々管理上の問題で借主とトラブルになることがあります。そのような場合に、当社が賃料の代理受領をしている関係上、借主から「今後は管理会社に賃料(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編182 延滞賃料は扶養義務者にも請求できるのか?
Q 前回、建物の借主が失業し賃料を滞納している場合の話が出ていました。そのようなケースで、もしその失業した借主が高齢のため新たな収入を得ることができないという場合は、その同居の家族に逆に扶養の義務が(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編181 賃借人の妻に対し延滞賃料の請求ができるか?
Q 最近は夫婦共働きの家庭が多くなっていますが、中にはそうでない家庭もあります。そのような家庭で、夫が失業し、賃料の支払いが滞っている場合、妻に対し賃料の支払いを請求することはできるのでしょうか。(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編190 農地転用を条件とする農地売買のリスクとは?
Q 前々回、手付の交付は売買契約の締結とは別物で、それは売買契約と手付の交付(手付契約)とは別個の契約だからということが出ていました。 A その通りです。「手付契約」というのは、当事者間で特段の定め(続く)