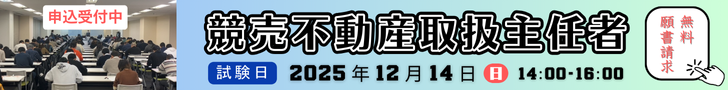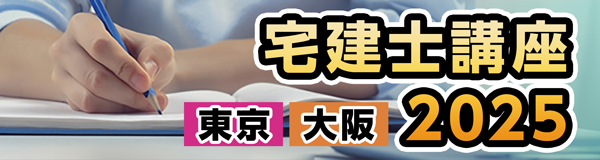マンション・開発・経営
-

三井不レジ、野村不、大成 月島三丁目南地区で再開発 住宅・商業・子育て支援施設を整備
住宅新報 11月29日号 お気に入り三井不動産レジデンシャル、野村不動産、大成建設の3社が東京都中央区で権利者と推進している「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」の権利変換計画が11月17日、東京都知事認可を受けた。同事業の区域面積は(続く) -

道玄坂二丁目南地区を再開発 渋谷エリアでホテル、オフィス整備 三菱地所
住宅新報 11月29日号 お気に入り三菱地所が東京都渋谷区道玄坂二丁目で参加組合員として新大宗特定目的会社など権利者と推進してきた「道玄坂二丁目南地区第一種市街地再開発事業」(敷地面積約6720m2)の権利変換計画が11月18日、東京都の認可を受(続く) -

明海大学不動産学部 不動産の不思議 学生たちの視点と発見 第461回 「珍しい」住宅 周辺環境と溶け込まない外観
【学生の目】 JR京葉線の新浦安駅から徒歩10分以内の住宅地を歩いた。第一種低層住居専用地域の住宅地は東京駅まで30分以内の好立地で、戸建て住宅やアパートが多く立地する。その住宅地でひときわ目を引く「(続く) -
.jpg)
都環会勉強会に三浦不動産業課長 不動産IT取引やトラブル事例など紹介
住宅新報 11月29日号 お気に入り今回は、国土交通省不動産・建設経済局不動産業課の三浦逸広課長と、経済産業省経済産業政策局総務課の奥家敏和課長が登壇。それぞれの立場から、国内外の経済・市場環境や国の政策について語った。 三浦課長(続く) -

不動産経済研調べ10月首都圏マンション 全エリア伸長で供給34.7%増 「秋商戦本格化」で契約率7割回復
住宅新報 11月29日号 お気に入り不動産経済研究所は11月21日、10月度の首都圏新築分譲マンション市場動向を公表した。供給戸数は2768戸(前年同月比34.7%増、前月比36.0%増)で、3カ月ぶりに前年同月比での増加へと転じた。戸当たり平均価格は6787(続く) -

デザインで変わる住まい(1) 阪急阪神不動産「ジオ京都御所北」 2022グッドデザイン賞 街になじむ意匠で〝心地よさ〟を
――京都御所の北側という立地について。 「周辺は御所のほかにも鴨川や寺社仏閣など、多くの人がイメージする京都らしさにあふれた立地で、学校や住宅に囲まれた閑静な住宅街。そこに暮らす人はもちろん、通り(続く) -

東急不、東急コミュ、東急リゾーツ&ステイ 入居者のリユースを支援 買取マッチングサービス提供
住宅新報 11月29日号 お気に入り東急不動産、東急コミュニティー、東急リゾーツ&ステイは、ウリドキ(株)が運営する買取マッチングプラットフォーム「ウリドキ」と業務提携した。リユースの促進と森林保全等の環境貢献を推進。東急不動産のオ(続く) -

インタラクティブな街づくりなどで講演 ビル経営C、新春オンラインセミナー
住宅新報 11月29日号 お気に入り日本ビルヂング経営センター(栗島明康理事長)は、23年1月26日に「新型コロナやロシア・ウクライナ情勢など環境が激変するビル経営を展望する~インタラクティブな街づくりと最新技術によるワークプレイスの進化~(続く) -
再開発で生まれる大規模緑地 都心・大手町に人を呼び込む リーシングなど経済効果も
住宅新報 11月22日号 お気に入り三井不動産と三井物産は、12月16日、「Otemachi One」(東京都千代田区大手町一丁目)エリアに約6000m2の緑地空間「Otemachi One Garden」をオープンする。このうち約3000m2が芝生広場を中心としたイベントスペー(続く) -

住友不動産、インド・ムンバイに進出 オフィス開発を本格化 2物件取得、当面3000億円投資目指す
住宅新報 11月22日号 お気に入り住友不動産は、インドの現地法人を通じてムンバイのオフィス開発を本格展開する。大手デベによる海外進出は現地資本との合弁が一般的だが、同社は、素地取得から開発許認可、商品企画、リーシング、管理までを直接(続く) -

地所レジ 災害に強いまちづくりイベント 杏林大、日航、三鷹市と協働開催
住宅新報 11月22日号 お気に入り三菱地所レジデンスは、杏林大学、日本航空、三鷹市と協働し11月12日と13日、杏林大学井の頭キャンパス(東京都三鷹市)で、全国15地域の特産品を集めたイベント「Craft Market@杏林大学」を開催し、同イベント内で(続く) -

東急不、北電など 石狩市でデータセンター事業 再生可能エネルギー100%で運営
住宅新報 11月22日号 お気に入り東急不動産は、北海道電力、IT基盤コンサル事業の(株)Flower Communications(東京都中央区、柳川直隆代表取締役)と、北海道石狩市で、再生可能エネルギー100%で運用するデータセンターの事業化について基本合意書(続く) -

脱炭素活動応援サービス 入居者の持続的な脱炭素活動支援 三井不レジ
住宅新報 11月22日号 お気に入り三井不動産レジデンシャルは、東京電力エナジーパートナーとファミリーネット・ジャパン(東京都港区、黒川健代表取締役)の協力の下、持続的な脱炭素活動を支援するサービス「くらしのサス活」を12月1日から開始す(続く)