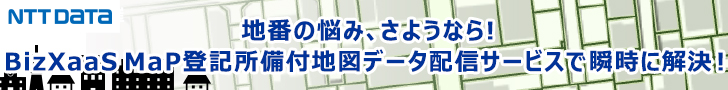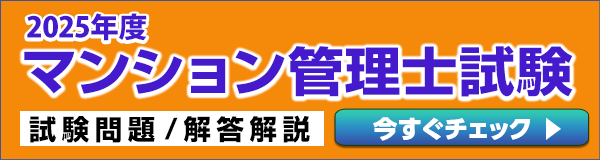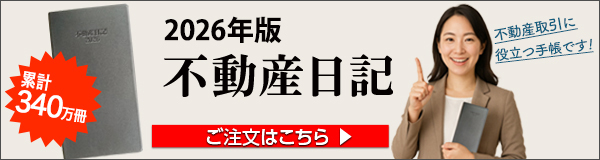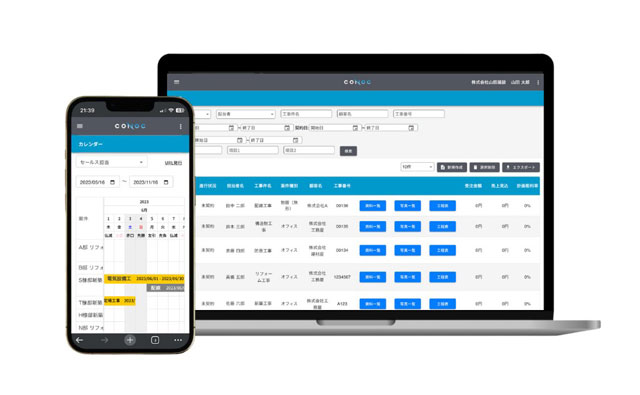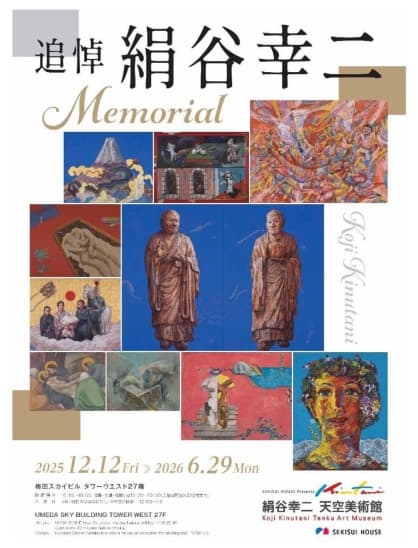吉田兼好は徒然草で「家づくりは夏をもって旨とすべし」と書いた。「家を造るときは、なによりも夏が快適に過ごせることを考えるべきだ。冬が寒くても、火を熾し、重ね着をすればなんとかなるが、夏の蒸し暑さは耐え難い」という意味だ。
前日本建築学会副会長で慶応大学理工学部名誉教授の伊香賀俊治氏は「この兼好の思想が今でも日本人のメンタリティーのどこかに残っている」と嘆く。伊香賀氏は住宅環境が住む人の健康にどのような影響をもたらすかについて研究している第一人者で、そのエビデンスに関する数多くの論文を発表している。
その代表的テーマが室温と健康との関係だ。冬の室温が18度C以下だと呼吸器系や心血管系の罹患、死亡のリスクさえ招くという。住まいづくりは夏ではなく、冬の室温にこそ気を払わなければならないことを長年の調査結果によるデータで証明している。例えば、年齢別調査では高齢になるほど室温の変動が健康に与える影響が大きく深刻であること、30歳男性の場合は朝が20度ぐらいまで暖かいと最も血圧が安定するなど、その詳細なデータに圧倒される。この伊香賀氏の論文は世界的に有名な国際医学誌にも掲載されている。実はWHOも18年に冬は暖かい部屋で暮らすことが健康維持につながるとして室温を18度C以上に保つことを勧告している。
板橋でシンポ
この伊香賀氏と前日本医師会副会長で聡伸会今村医院理事長の今村聡氏が基調講演を務めたシンポジウムが3月26日、東京・板橋区内で開かれた。今村氏は、「人々の心身の健康と住宅が密接な関係にあることは約200年前にナイチンゲールが病気の原因の半分は住環境の劣悪さが関係していると指摘した時代から分かっていたこと」と前置きしたうえで、「現代ではその科学的エビデンスが次々に明らかになってきている」と指摘した。にもかかわらず、日本ではいまだに住宅を自己責任と捉えていることが問題だとも述べた。世界では住宅は社会保障政策というのが常識だという。
シンポジウムは「ひと部屋耐震・断熱」運動を推進している「健康・省エネ住宅を推進する国民会議」(上原裕之理事長)が主催した。この運動について今村氏はこう指摘した。
「1部屋だけ断熱性能を高め暖かくしても、そこを出たら寒いということでは意味がないと批判する向きもあるが、そうではない。暖かい部屋で十分健康状態を保てば外に出ても健康は維持できる」
寒い家で長年暮らしていると病気になりやすいということだ。そしてこう締めくくる。「あとはこの運動をどう進めていくかだが、医師と建築家、医学界と建築学会、政府と自治体など様々な連携を進めることが大事。しかし、連携は口で言うほど簡単ではない。連携に向けて話し合う場を作れるのは結局自治体しかない」。
そもそも同シンポジウムは板橋区長や環境政策課、板橋区の医師会や建設業協会など〝板橋人脈〟を母体にしたもの。まさに板橋区を発信基地として全国に運動を広めていくという狙いがある。
主催者の上原裕之氏の本職は歯科医師だが、93年に新築した自宅兼診療所で目が染みるなどのシックハウスを経験。その後様々な政治活動を行う中で03年の建築基準法改正につなげ、有害住宅建材規制を実現した。「シックハウス問題は特にアレルギーに敏感な人を除けば既に解決している」と話す。
現在取り組んでいるのが、家の中でたとえ一部屋でも耐震化と断熱化を進めることで「命を守る」運動だ。上原氏は言う。
「住宅は本来医師と建築士が連携して建てるもの。戦前は住宅を所管していた内務省に医務技官がいたが国交省にはいない。今、ようやく厚労省と国交省、さらに環境省が加わった3省の連携体制が出来上がりつつある」