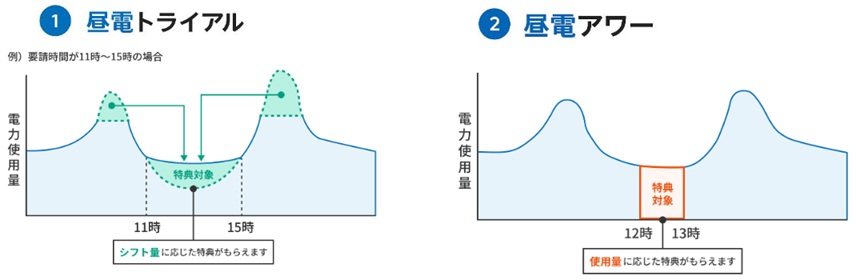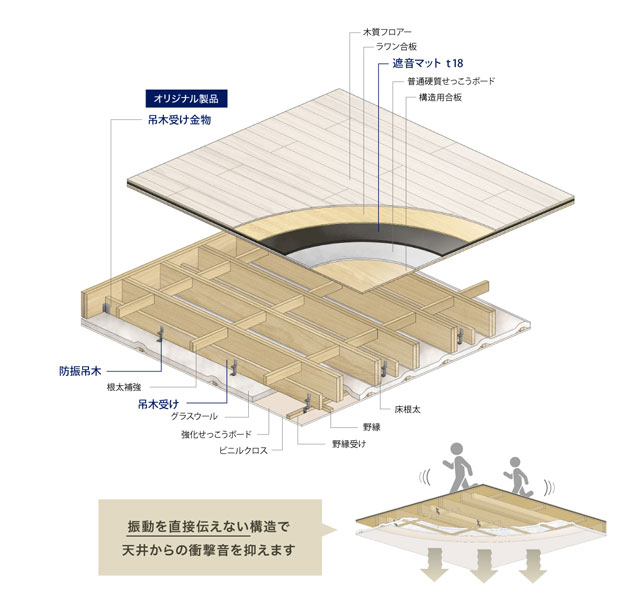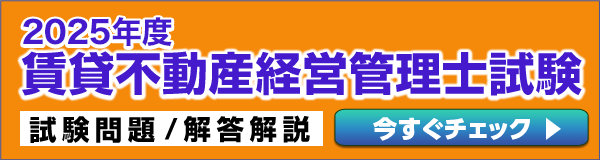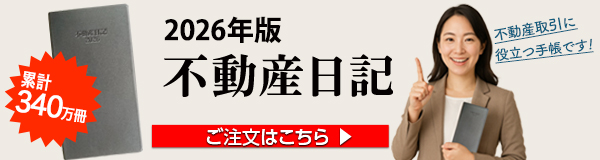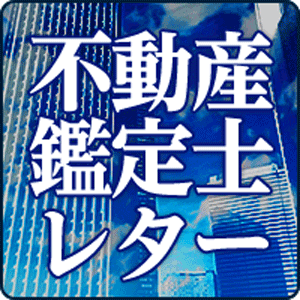地方の仲介力をより一層高める好機がきた。不動産仲介の現場でも、AIや生成AIツールの導入・検証が広がりつつある。AI査定システムによる査定資料の作成やレコメンド、AIが下書きを行う重要事項説明書案に加え、チャットボットを活用した顧客対応の一次応答や社内照会にも利用の芽が出てきた。もっとも、最終説明・最終判断は人(宅建士)が担う現行ルールに変わりはない。
だがAIは、属人化した業務を可視化し、経験や勘に依存してきた手順を〝再設計〟する契機になる。全国の宅建業者の大半は中小事業者で、人材確保や技能継承の難しさは共通課題だ。在庫や成約事例が分散しやすい地域ではデータ整備の負荷が高く、AIによる自動査定や需要分析、文書生成の補完効果は大きい。地方の仲介力を底上げする「業務の平準化ツール」としての期待は現実的だ。
一方で、AIが専門性や運用ルールの〝壁〟の外側にいる参加者を呼び込む力も見逃せない。情報収集・接客・与信補助が効率化されれば、不動産以外のIT企業や金融、暮らし関連のプレイヤーの参入障壁は相対的に下がる。人材の流動化は進むが、地場の仲介会社にとっては競合増加という試練も伴う。
論点は技術そのものではない。AI起因の誤情報、説明過程の不透明さ、責任の所在――これらは消費者保護と説明責任に直結する。現行制度はAIの「判断」自体を前提としておらず、あくまで人が責任主体だ。だからこそ、業界側で検証・根拠の提示・記録の作法を整え、倫理基準と役割分担を更新していく必要がある。
報酬のあり方も見直しが迫られる。AIが査定・資料作成・内覧前コミュニケーションを効率化すれば、対価は「成約手数料だけ」でなく、コンサルティングや伴走支援の定額メニュー等を含む〝サービスの多様化〟へ議論が広がる。現行の手数料上限の枠組みを前提としつつも、追加的な情報提供・手続き支援に価格を付ける発想だ。大手に有利な側面がある一方、地域密着型の中小事業者は住み替え設計・暮らし情報・アフター接点で差別化を図れる点に大きな強みがある。
備えるべきは「AIをどう使うか」よりも、「AI時代に何を守り、どこを強化するか」だろう。属人性を失うことは、同時に地域の信頼資本を失うことにもつながりかねない。国や業界団体は、AI導入ガイドラインの策定や中小業者向けの支援策に加え、倫理的判断や説明責任を担保する教育体系を整備すべきだ。
AI時代の仲介業に求められるのは、効率化ではなく〝信頼の再構築〟である。テクノロジーが人を代替するのではなく、人の判断を補完し、地域に根差した不動産サービスを支える――その未来像を描けるかどうかが、地方の仲介ビジネスの命運を分ける。