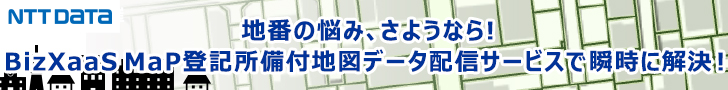総合
-

大言小語 幻想に生きる現代人
去年は各地で大災害が頻発した。地球温暖化が原因とすれば今年も同様か。ただ、国民の多くが最も恐れているのは近く起こるといわれている巨大地震である。 ▼その一つに首都直下型地震があるが、政府の地震調査会(続く) -

18年訪日外国人旅行者数 大台超えの3119万人 災害で鈍化もLCC増など奏功
住宅新報 1月22日号 お気に入り同統計結果発表と同日の記者会見で、田端浩観光庁長官は訪日客増加の要因について「LCC(ローコストキャリア、格安航空会社)等、航空便の増加が底上げにつながった。また(近年の)ビザ免除、免税店や多言語表示の拡(続く) -

業界団体が新年会開く
住宅新報 1月22日号 お気に入り全宅連・全宅保証 既存住宅流通促進策を推進 全国宅地建物取引業協会連合会・全国宅地建物取引業保証協会(全宅連・全宅保証、坂本久会長)は1月11日、東京都千代田区のホテルニューオータニで、新年賀詞交歓会を開(続く) -

グリーンボンドの発行条件を決定 住金機構
住宅新報 1月22日号 お気に入り住宅金融支援機構は1月11日、住宅ローン債権の買取代金を資金使途とするグリーンボンド「一般担保第255回住宅金融支援機構債権」(住宅金融機構グリーンボンド)の発行条件を決定した。同機構によると、住宅ローンを(続く) -

今週のことば 国際観光旅客税(1面)
原則として、船舶または航空会社(特別徴収義務者)が、チケット代金に上乗せするなどの方法で、日本から出国する旅客(国際観光旅客等)から徴収(出国1回につき1000円)し、これを国に納付するもの。1992年の地価税以(続く) -

ひと 柔軟さと安定感に自信 日立ソリューションズ・クリエイトのサムポローニア本部営業部長 大森貴夫さん
不動産などの登記情報を自動で一括取得し、データ管理・活用も可能な「登記情報取得ファイリングシステム」(以下、登記FS)。近年の人手不足やシステム化の潮流などを背景に、ニーズが急増している同システムの営業(続く) -

地域が変わるインバウンド 交流人口増加がもたらす恩恵 (80) 自然災害の教訓をいかそう(3) 復興に向け、SNSを活用
住宅新報 1月22日号 お気に入り復興力も日本の個性 昨年、7月に西日本を襲った大雨は、インバウンドにも影を落とし、韓国や台湾では対前年同月比でマイナスとなった。しかし、災害の中で前向きな要素もあったようだ。訪日観光に三十数年の実(続く) -

ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 52 日本住宅性能検査協会 外壁全面調査からADRへ
建築基準法第12条の改正により、08年4月1日から(1)特定建築物定期調査の部分打診、目視等により異常が認められたもの、(2)竣工後10年を越えるもの、(3)外壁改修後10年を越えるもの、(4)落下により歩行者に危害を加(続く) -

東日本レインズ 18年12月首都圏流通動向 中古マンション成約は微減、戸建ては増
住宅新報 1月22日号 お気に入り東日本不動産流通機構(東日本レインズ)はこのほど、18年12月の首都圏流通動向をまとめた。首都圏の中古マンションの成約件数は2987件で、前年比は0.8%減となり、微減だった。 成約価格については、m2単価、成約(続く) -

「売却の窓口」が特別講演 流通トレンドをテーマに
住宅新報 1月22日号 お気に入りインスペクションや瑕疵保険を中心とした、付加価値仲介で安心安全な既存住宅流通を推進するボランタリーチェーン「売却の窓口」(運営会社:価値住宅、東京都渋谷区)は、2月19日、渋谷区千駄ヶ谷のSYDホールで総会(続く) -

ERA 「働き方改革等に対応」 新春経営トップセミナーに100人
住宅新報 1月22日号 お気に入り不動産フランチャイズチェーン「ERA LIXIL不動産ショップ」を展開するLIXILイーアールエージャパン(東京都中央区、斎藤雄二社長)は1月10日、東京都内でERA新春経営トップセミナーを開き、全国から100人超のERA加(続く) -

輝く女性インタビュー 安部恵美氏 CHINTAI 賃貸暮らしをわくわくさせたい メディアディビジョン コンテンツグループ グループリーダー 編集部 編集長
住宅新報 1月22日号 お気に入り――PV数が急増。 「18年度に編集長に就任する前から、全国を取材で駆け回り、雑誌版に自分でも記事を載せてきた。せっかくの記事なのだからと考え始め、ウェブ版にも載せようと、記事コンテンツを1年ほど前か(続く) -
フィギュア 高橋大輔氏がコーディネート スカイコート マンション計画
住宅新報 1月22日号 お気に入り分譲や賃貸、管理事業などを手掛けるスカイコートは1月12日、創立50周年記念プロジェクトとして、フィギュアスケーターの高橋大輔氏がトータルコーディネートした投資用マンション『D―color』の第1号の完成発表会(続く)