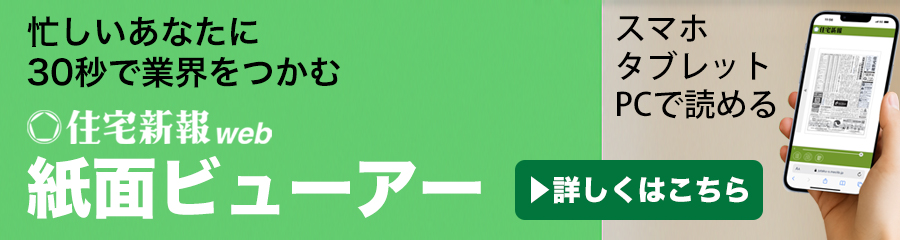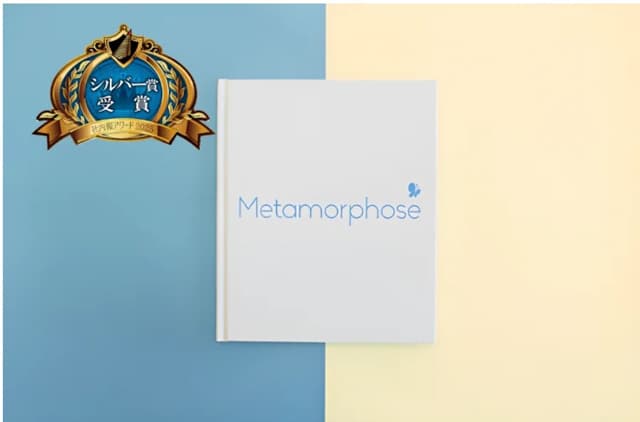不動産取引現場での意外な誤解 記事一覧
-
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(81) 借地人は他人の私道を通行する権利があるか?
Q 前回までの売買編では私道通行権の話が出ていました。土地の賃貸借の場合にも、前面道路が他人の私道であったら通行権の問題が生じるでしょうね。 A それは当然生じます。借地をした土地の所有者と前面道路(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 売買編(90) 幅員が4メートル未満の道路はすべて「2項道路」か?
Q 私は、先日都心部の下町の物件を仲介したときに、幅員が4メートル未満の道路で、それが「公道」だったためにセットバックが必要ない道路であると同業者から言われました。そこで、買主に何も説明しないで仲介し(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 売買編(89) 私道の通行権と配管のための掘削権は別か?
Q 前回、他人の私道の場合には通行権があっても負担が生じることがあるという記述がありましたが、その負担の中には通行料のほかに、道路の掘削承諾料といった負担もあるのではないでしょうか。 A その通りで(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 売買編(88) 他人の私道に通行権があっても、負担が生じる?
Q 前回、他人の私道については、通行権があっても負担が生じることがあるという記述がありましたが、それは私道の所有者が自らその私道の維持管理をしていたり、固定資産税等を負担してることがあるからですよね(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 売買編(87) 他人の私道に慣習上の通行権が認められるか?
Q 前回、分譲地の場合には他人の私道であっても原則として通行権があると書いてありました。そうなると、ほとんどの宅地は昔は誰かが分譲したものだと思います。ほとんど通行権があると考えてよいのではないでし(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 売買編(86) 私道の通行承諾がなくても売買契約は有効か?
Q 私達宅建業者は、契約の当事者に契約を守ってもらうために、契約違反をした場合の違約金条項や契約解除条項を定めていますが、改正民法は「軽微」な違反の場合には契約を解除することができないという条項が定(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 売買編(85) 契約不適合責任は買主が悪意でも問われるか?
Q 前回の記述の中で売買の目的物に「契約不適合」があった場合は、売主に損害賠償義務についての免責事由(不可抗力など)があっても、買主は代金の減額請求ができるというのがありました。ということは、追完請求(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 売買編(84) 改正民法に無過失責任の規定はあるか?
Q 売主に対する損害賠償請求は、改正後は売主に「帰責事由」がある場合に限られるという記述が、以前のコーナーでありました。これは、現行法でいう売主に「過失責任」がある場合ということでしょうか。 A 売(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 売買編(83) 代金減額請求権は一体どういう権利か?
Q 民法改正による買主からの代金減額請求権は、どういう権利なのでしょうか。 A 改正法の代金減額請求権の法的性質は、いわば契約の一部解除権とでもいいましょうか、いわゆる一般の「請求権」とは異なる買主(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 売買編(82) 売主に責任がある場合、減額請求+損賠請求ができるか?
Q 前回のこのコーナーで今年改正される予定の民法の瑕疵担保責任に関する規定が一番わかりにくいと書いてありましたが、売買の場合に代金の減額請求ができるケースというのは、現行法ではかなり限定されていまし(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 売買編(81) 数量指示売買での面積増減、代金清算は?
Q 売買編の問題については、昨年随分と民法改正に絡む話が続きましたが、その中でもやはり瑕疵担保責任に関する改正規定が一番難しく感じました。 A そうでしょうね。民法の最も基本的な考え方である意思主義(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(80) 太陽光発電施設でも、事業用定期借地は可能か?
Q メガソーラー施設が「発電所」だという考え方から、その土地の借用を「建物所有目的」の借用と考えることができるでしょうか。 A 確かに借地借家法に関する法律書の中には、「発電所」や「変電所」も事業用(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(79) 事業用借地でも、建物買取請求はできる?
Q 前回、借地借家法23条の事業用定期借地等に関する記述の中で、第2項の期間が10年から30年未満までの事業用借地の場合には、建物買取請求権に関する同法13条の規定は「適用しない」と書いてありました。このよう(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(78) 事業用借地と事業用定期借地の違いは?
Q 借地借家法23条の規定を見ると、以前は「事業用借地権」という見出しで定められていた事業用の定期借地が、「事業用定期借地権等」という見出しになっていますが、これは何か訳があるのですか。 A それは、(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(77) 入居者間トラブルは入居者が解決する旨の特約は有効?
Q 当社の賃貸管理物件では、あまり表に出たがらない貸主が多く、特に入居者間のトラブルについては、入居者が自らの責任で解決するという特約条項を定めています。しかし、このような特約は有効なのでしょうか。(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(76) 原状回復工事代金受領後の原状有姿賃貸はOK?
Q 原状回復工事のための借主との工事負担金についての合意が成立し、そのための敷金清算を完了したにもかかわらず、貸主が原状回復工事を行わず、そのまま次の借主に賃貸してほしいと言ってきました。よく、こう(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(75) ペット敷金の追徴などは公平に反しないか
Q 前回のペット敷金特約の話で、全額償却の定めが損害賠償額の予定になるとのことですが、不足が生じたときに追徴し、余剰が生じたときに返還しなくてよいというのでは、公平に反するのではないでしょうか。 A(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(74) ペット飼育可物件の明け渡しでもめないためには
Q ペット飼育可物件で明け渡し時にトラブルになることがあります。その原因の多くは、修復する工事個所の範囲の問題とその費用の分担比率の問題なのですが、こうしたトラブルが生じない、よい方法はないでしょうか(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(73) 事故物件の次の入居者への告知義務は
Q 事故物件の問題で、賃貸の場合には、事故後の2回目の入居者には事故のあったことを告知しないという公的住宅の場合の取り扱いがあるようですが、それは、裁判例があったということで、一律にそのような基準を設け(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(72) 事故物件の再募集までの期間と賃料減額率は
Q 前に自殺があった賃貸物件の売買についての仲介業者の調査義務の話が載っていましたが、そのような事故物件の再募集の時期や賃料の減額度合いなどについての話を伺いたいのですが、まず、自殺という事故物件の(続く)