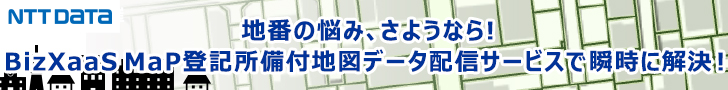社説「住宅新報の提言」 記事一覧
-
社説 増加する認知症患者 円滑な取引へ、知識武装を
厚生労働省によると認知症患者数は22年時点で443万人だが、30年には523万人、50年には586万人まで増加する見込みだ。しかし現在、認知症患者を法的に保護するための成年後見制度全体の利用者数は23年末時点で約25(続く) -
社説 住宅・不動産「巳年」を占う 国内外に潜むリスクを点検せよ
30年以上にわたりインフレと縁のなかったニッポンだが、地政学リスクという外的要因と歴史的な円安を受けて、さまざまな商品・サービスの値段が上っている。 念願のデフレ完全脱却宣言を政府は待ち望んでいる(続く) -
社説 住宅税制の抜本的改革 恒久的な負担軽減と簡素化議論を
師走に入り、今年も次年度税制改正へ向けた議論が本格化している。先の衆議院選挙の結果により少数与党となった自由民主党及び公明党は、税制を始め政策の検討に当たって、近年では異例の形となる野党との協議を行(続く) -
社説 賃貸業が鍵を握る居住支援 「地域包括」視点の成長戦略を
賃貸住宅は空き家対策と併せ、社会的な側面からも活用の重要性が増している。その鍵を握るのが、今年5月に成立し、来秋施行される「改正住宅セーフティネット法」だ。改正前の同法では、賃貸住宅の入居を断られる(続く) -
社説 入居者高齢化に備える 管理側に求められる意識改革
賃貸住宅市場では高齢者入居の敬遠が続いている。認知症発症や孤独死に対する警戒感が強いためだ。しかし人生100年時代を迎え、これからは今入居している人の高齢化への備えが必要になる。定期借家権契約でない限(続く) -
社説 10年経っても進まない地方創生 DXイノベーションを巻き起こせ
遅々として進まぬ地方創生。自由民主党の石破茂総理は、10月27日の衆議院議員選挙に挑むに当たり、「地方の振興で日本全体を元気にします」を選挙公約の一つに掲げた。2014年9月3日に初代の地方創生大臣として就任(続く) -
社説 人材不足は長期的課題 高度な人材育成が唯一の道
人材不足がますます深刻になっていく。求職者1人当たりの求人数を示す有効求人倍率は8月時点で1.23倍、新規求人倍率は2.32倍と高水準で推移している。今春に主要大手中堅企業を対象に本紙が実施した「住宅・不動産(続く) -
社説 石破新総理就任、手腕に注目 所得向上で「内需の柱」支えよ
10月1日、自由民主党の石破茂氏が我が国の新たな内閣総理大臣に就任した。異例の激戦となった総裁選を制し、同党内のみならず多くの国民の期待を背負っての船出である。山積する国内外の諸課題にいかに対応してい(続く) -
社説 「おとり広告」排除の仕組み構築へ 業界団結の情報連携加速を
秋の住まい探しシーズン。消費者にとって不動産広告を目にする機会の多い季節だ。今年4月には建築物の省エネ性能表示制度が始まるなど、広告表示の注目度が増している。 広告表示について、業界はこれまで「(続く) -
社説 単身者の居住環境改善へ ローン控除で取得支援を
若い世代の晩婚・非婚化で単身世帯が増加し、近年はそうした単身者による分譲マンション購入が増えている(本紙7月9日号1面参照)。その購入動機についてマンション販売の担当者は、「家賃を払い続けることへの抵抗(続く) -
社説 中古と高齢者に照準 住宅商品は社会学の観点で見直せ
人口減少と空き家の増加が止まらない中で、住宅・不動産業界は、住宅政策を都市経済学的な観点だけでなく問題を解決する社会学の観点から見直すことが求められている。マスプロダクションに基づく住宅産業の最大化(続く) -
社説 安全・安心と省エネ化を両立 健康長寿国へひと部屋断熱を
人口減少と高齢化が進むこの先、一人暮らしなど高齢者小世帯は確実に増加していく。中でも低所得層の高齢者小世帯という住宅弱者対策は長期的課題だ。来春には改正建築物省エネ法が全面施行され住み替え、買い替え(続く) -
社説 東京を出ていく子育て世帯 立地超えて「選ばれる街」目指せ
新型コロナウイルス禍による東京都への転入超過数の一時的な急減が収まり、現在は引き続き「東京一極集中の是正」が大きな課題となっている。しかし、国土交通省のまとめた24年版首都圏白書(6月18日閣議決定)によ(続く) -
社説 大雨災害の季節 業界団結で危機管理力高めよ
総会シーズン後半の6月下旬、各地で例年より遅めの梅雨入りが発表された。今夏は観測史上最も暑くなった昨年に匹敵する暑さが予測されるが、夏本番を前に、大雨・洪水災害への注意が一段と高まる季節だ。 激(続く) -
社説 公的不動産(PRE)に事業好機 不動産業界の目利き力に期待
日本銀行は6月の金融政策決定会合で追加利上げを見送り、慎重な姿勢を続けるが、国債の買い入れを減額する方針を決めた。次回7月の会合で減額計画を決めて事実上の量的引き締めに転じる。利上げに向け着々と下地を(続く) -
社説 賃貸住宅修繕共済を門戸開放 大規模修繕計画の普及、定着へ
不適切な維持・管理や修繕が原因となって、各地で老朽化した賃貸住宅に関わる事故が後を絶たない。借家ストックは2000万戸弱に上り、総住宅数の約3分1以上を占める重要な国民生活の基盤だが、民間の賃貸住宅は持ち(続く) -
社説 好業績目立つ大手決算 利益を人に投じ更なる成長を
主要な不動産会社の24年3月期決算が出そろった。特に大手では好調な業績が目立っており、コロナ禍による悪影響からはほぼ脱したと言える。実際に、ホテル事業などコロナ禍で低迷していたセグメントの回復が業績を(続く) -
社説 空き家900万戸時代 〝対策の先〟示す議論を
総務省が4月30日に速報集計として発表した23年10月1日現在の日本国内の総住宅数は6502万戸(18年調査時6241万戸)で過去最多を記録した。このうち空き家数900万戸(同849万戸)、空き家率13.8%(同13.6%)といずれも過去(続く) -
社説 区分所有法は限界か 容積や資金面での支援必要に
秋の臨時国会へ先送りとなった改正区分所有法案は主な改正履歴としては83年と02年に次ぐ3回目で多数決要件の緩和も最終段階に至った感がある。 例えば改正要綱によると建て替え決議の要件は、現行は区分所有(続く) -
社説 日銀、マイナス金利を解除 内需拡大に配慮する金融政策を
日銀はマイナス金利政策と長短金利操作(イールドカーブ・コントロール、YCC)の大規模金融緩和を解除した。形骸化していたETF(上場投資信託)とJリートのリスク資産の新規購入も停止した。2016年2月から8年余りの長(続く)